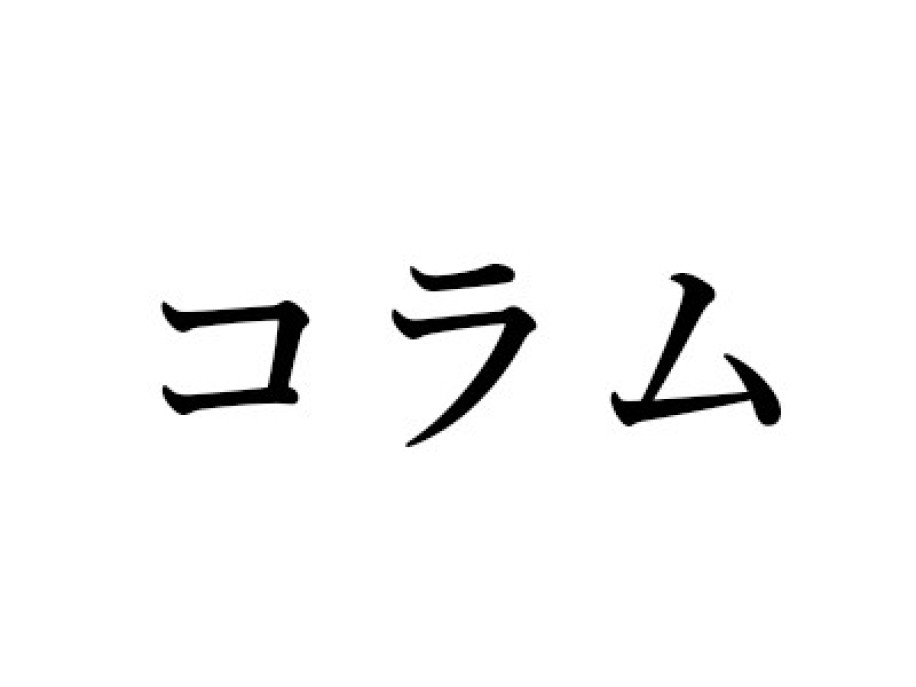書評
『花森安治の編集室 「暮しの手帖」ですごした日々』(文藝春秋)
「天才編集長」を描く元部下の思い伝わる
男なのにオカッパ頭。白いジャンパーに茶系のズボンの「銀座のゴジラ」。きわめつきのガンコにして絹のように柔軟。桂春団治とミステリーが好き。戦後雑誌界の風雲児、「暮しの手帖」編集長、花森安治。評伝ではない。六年間、花森の下で働いた、その目から「親方」の矛盾や体臭までも描きこんだ。
新入社員は自分の机がないのに驚いた。「一年間、なぜと訊くな」。入社式で花森は言った。職人にはリクツはない。最初のボーナスで“自前の”カメラとテープレコーダーを買わされた。しょっちゅうカミナリが落ち、ときに流れ弾が当たった。
「お当番」という役目がある。早めに出社し、湯をわかし、布巾(ふきん)をたたみ、商品テストのための研究室の空調に気を付ける。お茶くみ、昼のご飯炊き、夕食のしたく。近代合理主義で考えれば「バカバカしくてノイローゼになる」ような制度だったが、「暮しの手帖」社は家長花森を中心に大家族のように「暮し」をともにしながら雑誌をつくっていたのだった。
それはギリギリの、思想と体力を賭(か)けた闘いであった。某メーカーのアイロンを十八台も買って欠陥を指摘し、クーラーのテストのときは三交代で徹夜した。料理記事はプロが作ったのを編集者が記事にし、その通りに別の編集者がつくって皆で試食した。
花森の卓抜な仕事術は十分に伝わる。十八字三十行で、といえばピッタリその分量の口述ができた。商品テストの結果が発表されれば、六ケタの数字をたちどころに並べかえ、トップとビリの差を出した。
しかし、これまた「天才伝説」の再生産ではないか。評者は五カ月間「不正社員」であった森茉莉が、花森の仕事を見て感に堪え〈インチキだなあ〉と思ったとたん目があって〈全身、これインチキでね〉というように細い目を光らせたエピソードを読んだことがある。そこをもっと書いてほしかった。編集とは「丸い卵も切りよで四角」にする痛快なインチキなのだから。
本書を私は二度読み、一度目は「腹の底からけっとばしたい」専横な花森が、二度目は「ボヤいても尊敬し愛すべき」花森が立ち上がった。きっとこの本は強烈な個性と六年も共に仕事をした人の、自己セラピーの書にちがいない。
【単行本】
朝日新聞 1997年10月26日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする