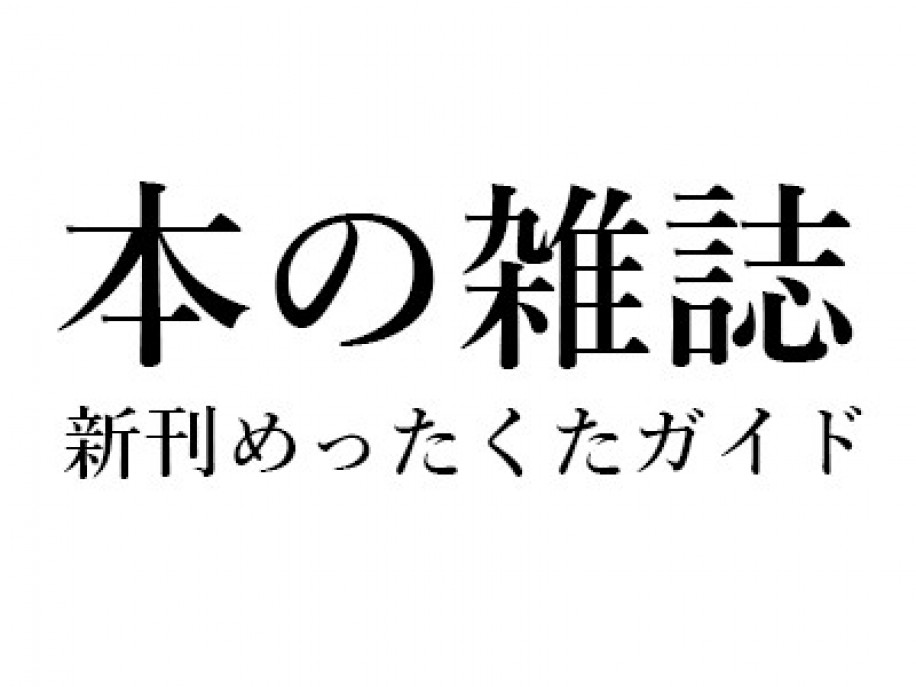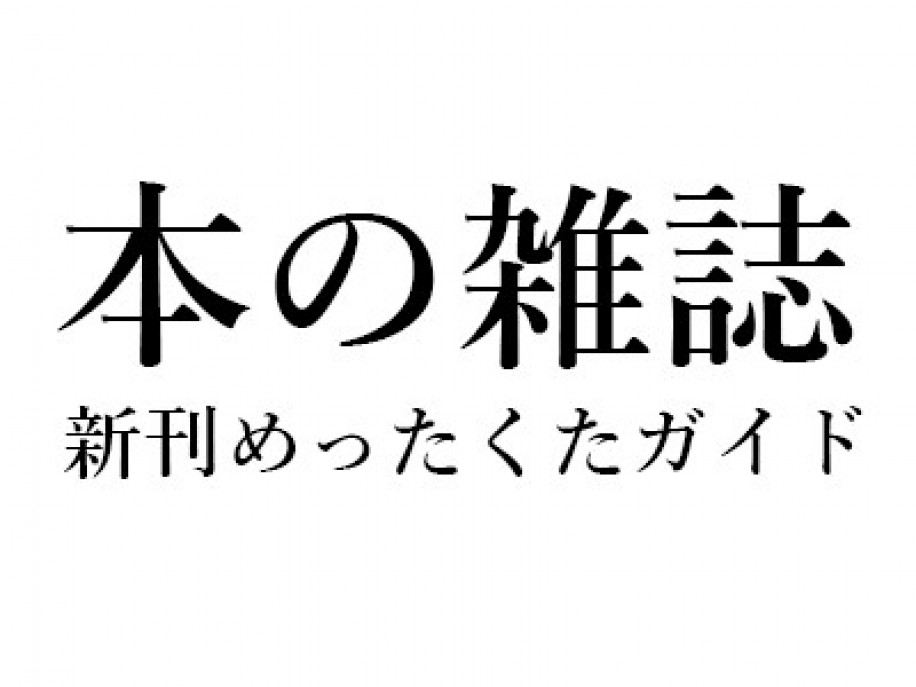文芸時評
大森望「新刊めったくたガイド」本の雑誌2001年4月号『タクラマカン』他
ブルース・スターリング短篇集『タクラマカン』の暴走と成熟
先月(事務局注:本原稿の掲載は2001年4月)のイーガン『祈りの海』に続いて、オールタイムベスト級のSF短篇集がまた一冊。ブルース・スターリング『タクラマカン』(小川隆ほか訳/ハヤカワ文庫SF)★★★★☆は、〝未来を描くSF〟の現在進行形である。本書の白眉は、後半に収められているチャタヌーガ三部作。物語性を無視して徹底的に細部に淫する「ディープ・エディ」の過激さはスターリングの面目躍如。いきなりこんなの読まされてもという人には、著者初のヒューゴー賞受賞作「自転車修理人」をおすすめしたい。ニール・スティーヴンスンばりのキャラクター小説で、とりわけ母親との会話は爆笑。作家的成熟を感じさせる余裕たっぷりのユーモアが絶妙の味わい。ハイテク・エスピオナージュを書かせると昔から天下一品の人だけに、巻末の表題作もすばらしい。タクラマカン砂漠に密かに建設された〝巨大星間宇宙船基地〟の正体と描写には茫然。小品ながら、インド映画の現場を描く愉快な異色作「聖なる牛」もいい。大森訳も一本だけ混入してますが(ラッカーと合作の「クラゲが飛んだ日」)これは誰がどう見てもラッカーのネタでしょう。巻頭の「招き猫」は、日本人読者にはやや気恥ずかしいかも。この『タクラマカン』と『祈りの海』を読めば〝短篇SFの今〟の最高水準がほぼ把握できるわけだが、歴史的な流れを知ることも重要。中村融・山岸真編の年代別傑作選《20世紀SF》全六巻(河出文庫)は、『②1950年代 初めの終わり』★★★★と、『③1960年代 砂の檻』★★★が出ている。前者では、フレデリック・ポール「幻影の街」が圧巻。六月十五日が毎日くりかえされる、CMだらけの街。だが、住人は誰もその異常さに気づかない……。「ダークシティ」も「13F」もホーガン『仮想空間計画』も青ざめる、人工現実SFの先駆的傑作。このオチはちょっと予想できません。定番の名作では、シェクリイの「ひる」、ヘンダースンの「なんでも箱」が今も読ませる。アンダースン「サム・ホール」、ベスター「消失トリック」、コーンブルース「真夜中の祭壇」あたりも上々の選択。あと、自分で訳してて言うのもなんですが、スタージョンの「たとえ世界を失っても」がめちゃめちゃ変な話で、『一角獣・多角獣』邦訳版から割愛されたのもよくわかる超絶ぶり。やっぱり五〇年代は侮れない。
それに対して、アメリカン・ニューウェーヴご三家を巻頭から並べた『砂の檻』は、やや疑問の残る選択。エリスンの「チクタクマン」、ディレイニーの「コロナ」はともかく、いくらなんでもゼラズニイが「復讐の女神」ってことはないでしょう。コードウェイナー・スミスのできそこないみたいな中篇で、当時はかっこよくても今読むと古臭い。本邦初訳のディクスン「イルカの流儀」もレベル的にどうか……といろいろ文句はあるものの、ディッシュ「リスの檻」、ウィルヘルム「やっぱりきみは最高だ」の収録は快挙だし、ラファティ「町かどの穴」は何度読んでも傑作。シルヴァーバーグ「太陽踊り」、オールディス「讃美歌百番」、ヴァンス「月の蛾」あたりが並ぶ後半もなかなか。
続いて国内のオリジナル・アンソロジーを二冊。日本SF作家クラブ編『2001』(早川書房)★★★は、新井素子、神林長平、田中光二、谷甲州などの全十一篇。著者別あいうえお順配列はどうかと思うし、値段に見合う水準に達しない作品も二、三あるが、ジャンルSFのショウケースとして貴重な一冊。荒巻義雄「ゴシック」は往年の荒巻短篇を彷彿とさせる力作。若手では、瀬名秀明の「ハル」が著者らしいロボットSFの秀作。藤崎慎吾は堅実で、三雲岳斗のパズラーも(内容的にはやや場違いだが)悪くない。しかしこの顔ぶれでもやはりいちばん目立つのは、「逃げゆく物語の話」の牧野修。森岡浩之や野阿梓にもっと冒険してほしかった気が。
〝ハイブリッド・エンタテインメント・アンソロジー〟と銘打つ『NOVEL21 少年の時間』(徳間デュアル文庫)★★★★のほうは、西澤保彦のミステリを除く五篇がSF。上遠野浩平「鉄仮面をめぐる論議」は虚空牙もので、コードウェイナー・スミスのパスティーシュとしてはゼラズニイより優秀。菅浩江「夜を駆けるドギー」は、2ちゃんねる用語が炸裂する現在形のペットロボットもの。平山夢明「テロルの創世」は、××××ネタのSFを意外にも(失礼)エレガントに処理した秀作。巻末の山田正紀「ゼリービーンズの日々」は、上遠野浩平『ぼくらは虚空に夜を視る』への返歌か。詩的なイメージが光る力作だが、説明しすぎて(ヒルベルト空間ネタがくどい)惜しくも傑作になり損ねた感じ。全体的にはきわめて対費用効果の高いアンソロジーで、続巻の『少女の空間』にも期待したい。
そのデュアル文庫からは、第一回小松左京賞最終候補に残りながら(新人じゃないという理由で)受賞を逸した北野勇作『かめくん』★★★★が出た。主人公のかめくんは、名前の通りのカメ。ただし本物のカメではない。木星戦争の兵器として開発された一種のカメ型ロボットなのである(レプリカントのカメなので、〝レプリカメ〟とも呼ばれる)。リストラで職を失い寮を追い出されたかめくんは、安アパートのクラゲ荘に引っ越し、新しい仕事をさがす。今度の就職先は、万博跡地にある倉庫会社。フォークリフトの運転ができるという特技を生かして、かめくんは意外と順調に働きはじめる。仕事帰りには商店街で買い物をして、部屋で好物のリンゴを食べる。休みの日には図書館に行って本を借り、アルバイトをしている大学院生のミワコさんとおしゃべりをする。かめくんは自分が本物のかめではないことを知っている。ただ冬眠のしかただけ思い出せない……。
という感じで、かめくんの日常がペーソス豊かなタッチで淡々と語られてゆく。その背後に垣間見えるSF設定と未来社会が魅力。機械知性の哀しみをかくもさりげなく痛切に描いた小説はかつてない。おもろうて、やがて哀しき傑作だ。
なお同文庫からは、山本弘の本格SF『時の果てのフェブラリー』の改稿版と菅浩江の星雲賞受賞作『メルサスの少年』も再刊。未読の人はお見逃しなく。また、前月出た浅暮三文の新作『夜聖の少年』★★は古き良きSFジュブナイルの香り豊かな少年小説だ。
ハルキ文庫《新ヌ ーヴエル世紀SF》叢書では、林譲治『侵略者の平和』三部作が完結。第三部『融合』★★★★は、技術レベルの低い防衛側が知恵と勇気で侵略者を撃退する、まさに『知性化戦争』ばりのレジスタンス小説だが、ブリン的なヒューマニズムとは無縁の結末に驚愕。『かめくん』と並んで、二一世紀日本SF最初の収穫。
都築由浩『レディ・スクウォッター』(電撃文庫)★★★は、宇宙描写が面白いのにキャラ立ちが弱くて話が古臭いので、むしろ三十代以上のおっさんSF読者向け。乙一『失踪HOLIDAY』(角川スニーカー文庫)★★★☆は、巻頭の短篇がジェントル・ゴーストものの佳作。
斉藤直子の日本ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞作『仮想の騎士』(新潮社)★★★☆は、いきなり関西弁で喋り出すカサノヴァを筆頭に、同時代の実在人物たち(サン・ジェルマン伯爵、ルイ十五世、ポンパドゥール夫人、メスメル)が入り乱れるおたく系妄想歴史小説。女装の騎士デオンのロシア潜入スパイ工作(史実)が抱腹絶倒。
恩田陸『MAZE』(双葉社)★★☆は、中に入った人間が消失する奇妙な遺跡の謎に挑むパズル小説。途中の議論は面白いが、もう少し論理を積み上げてくれないと満足できない。
ALL REVIEWSをフォローする