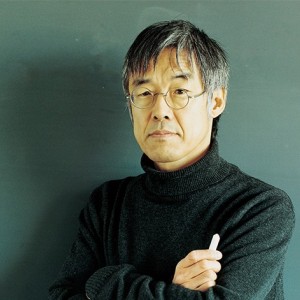書評
『ジュラシック・パーク』(早川書房)
クライトンくん、一生映画の原作を書くつもり?
いくら名作でも、飛行機の中で読む本としては『重力の虹』はかったるすぎるので、旅行鞄の中にはミステリーかSFの文庫本が入ることになる。ちなみに、一週間前のロンドンからの帰り読んでいたのは遅まきながらのパトリシア・コーンウェルの『証拠死体』(相原真理子訳、講談社文庫)で、暇つぶしにはいいけど、前半の伏線があまり活かされていないし、主人公ケイの元夫の正体も、ミステリーの読者としてはたいしたことのないぼくでさえすぐわかるし、真犯人もやっぱりという感じだったなあ。これなら、サラ・パレツキーの方がずっと上だろう――とかなんとか文句を言いながら結局最後まで読んじゃったのだった。やっぱり、飛行機の中で読むなら、ウィリアム・カッツやディーン・R・クーンツに限るけど、いつも同じ作家というわけにもいかないので、最近はマイクル・クライトンくんの本も鞄に侵入してきたのである。最初は『ジュラシック・パーク』(酒井昭伸訳、ハヤカワ文庫)で、もちろんスピルバーグの映画の原作だから読んだのだけど、びっくりしたねえ。だって、これ、スピルバーグの映画の原作だと知らないで読んだとしたら、絶対これはスピルバーグが映画化するに違いないと思うぜ、ふつう。
最初にティラノサウルスに襲われるところとか、最後の方で子供たちがヴェロキラプトルと厨房で対決するところとか、そのまんま映画になっているのだが、実をいうと、どこもかしこも映画を見ているような描写なんだね。
地上までまだ三メートル半。手さぐりをしてべつの枝をつかみ、からだを引きおろす。頭上の枝がランドクルーザーの重みでしなりだした。バキッ。またもや枝が折れ、ランドクルーザーが襲いかかってきた。こいつから逃れるすべはない。落ちてくる車より早くは降りられない。だからティムは手を離した。
からだがすーっと落下していく。
何度も枝でからだを打ち、あちこちが痛んだ。上からはランドクルーザーが、枝をへし折りへし折り、兇暴なけもののように襲いかかってくる
ここをクライトンは絶対映画のシーンとして書いたはずだし、そしてこの部分を映像化したスピルバーグの方が一枚上手だったことは、映画を見た人間ならわかるだろう。でも、映画で「すげえ!」と思ったところは、読むと特につまらないんだよね。
でもって、『ジュラシック・パーク』を読んでも懲りずにトライしたのが、『スフィアー球体ー』(中野圭二訳、ハヤカワ文庫)で、これは「海底に沈んでから少なくとも三百年は経過している宇宙船」が発見される話。未知の球体から未知の生物の謎のメッセージが発信される……というと、もちろんスタニスワフ・レムを思い出すけど、クライトンもちゃんとレムを参考にして書いたようであちらでもこちらでも「わかりやすいレム」(それからほんの少し「わかりやすいディック」)をやっている。おかげで、「わかりやすいレム」というのはあまり面白くないということだけはわかって、たいへんタメになったのだが、なんでこういうことになっちゃったかというと、この作品もやはり映画化を目指して書かれたに違いなく、本家のレムだってタルコフスキーが四苦八苦して映画化したというのに、それを噛み砕いてわかりやすくヒットする映画になるような原作を書こうなんて虫がよすぎるんじゃないかと思っているうちに寝てしまい、気がついたら成田に着いていたのだった。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする