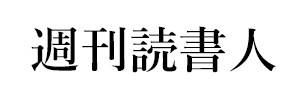書評
『近世の巨大地震』(吉川弘文館)
歴史学と防災学の架け橋に
ー「どこで何が起きたのか」を丁寧に読み解くー
日本は「災害大国」である。日本史教育・教養において、政治史、経済史、文化史などはよく取り上げられるが、「災害史」「歴史災害」はほとんど取り上げられない。しかし、日本は頻繁に災害に見舞われている。人々や社会がどのような課題解決をしながら被害や影響を乗り越えたのかという過去を知らなければ、未来への防災の意識や備えを推進することは難しい。
本著は「地震史料」を、近世の俳人などの史料まで広く収集している。そして、詳細な地理的情報のもとに、平易な読み下し文や解説、豊富な人々の体験談によって「自らが住む地域で過去に起こった被害」を知り、未来の防災への気づきにもつなげることができる。「歴史学と防災学の架け橋となる好著」である。
本書は前書『中世の巨大地震』の続編である。近世においても、1707年宝永地震や1854年嘉永の東海地震・南海地震といった南海トラフ周辺だけでなく、1703年元禄関東地震のような相模トラフや、1611年慶長陸奥地震などの千島海溝・日本海溝周辺で発生した地震、1833年出羽庄内沖地震といった日本海側で起こった地震など、大きな海溝型地震が発生した。
そしてこれらの前後には、現代の阪神・淡路大震災や熊本地震などのような、我々が生活する地面の真下で発生する内陸型(直下型)地震が発生した。まさに大地動乱の時代であった。
本書の特筆すべき点は三つある。まず、地図、地形図、絵図を多用しながら解説をすることで、「どこで何が発生したのか」を詳細に知ることができる。例えば、1703年元禄関東地震では、東海道から京都に帰ろうとした一行の日記『祐之地震道記(すけゆきじしんみちのき)』から、被害が大きい平塚宿ではなく、被害がそれほどではない大磯宿に宿泊したことを取りあげ、これは1923年関東大震災でも被害の大小関係は同じであり、地盤の特徴が被害を繰り返していることを解説している。
また本書は、地震時・地震後の人間の対応行動の記述も手厚い。1828年越後三条地震では、『文政度地震変事御糺答書(ごきゅうとうしょ)』から、42人の罹災家族の長の申上を読み下しながら物的・人的被害を紹介している。特に、朝食後の炉端での団らん中に家が倒壊し、梁や柱の下敷きになった人が亡くなり、下敷きにはならなかった人は隙間から這い出て助かっていた。これは、内陸型地震への対処における耐震の重要性は時代を超えた教訓であることを示唆している。
さらに本書は、取り上げたほとんどの地震について、近世史料から、家屋倒壊率(全潰率)や一村あたりの死亡者数を丁寧に計算し、集落を壊滅させるような死亡者を出す災害は津波と土砂崩れであり、活断層近傍では地震への備えが必要であるが、過去に津波・土砂災害が発生した地域の人間こそ、災害への気づき・備えが必要であることを述べている。
二十一世紀前半は地震活動期であることに加え、異常気象によって多数の巨大災害の発生が予測されている。しかし漠然とした知識やイメージのまま「本番」を迎えてはならない。歴史学の本書をきっかけにして、防災への気づきや備えを深めていくことは、本書の著者としても望んでいることであろう。そして、このような異分野の学問を結びつけるような試みは防災学においてますます重要になっていくことと思われる。
本書は「過去を知る歴史学」と「未来に備える防災学」を結びつけたことの他にも、学際的研究のシナジー効果を知るための絶好の著としても、重要な一冊となるであろう。
[書き手]:木村 玲欧( きむら れお)兵庫県立大学教授。著書に、『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)など多数。
ALL REVIEWSをフォローする