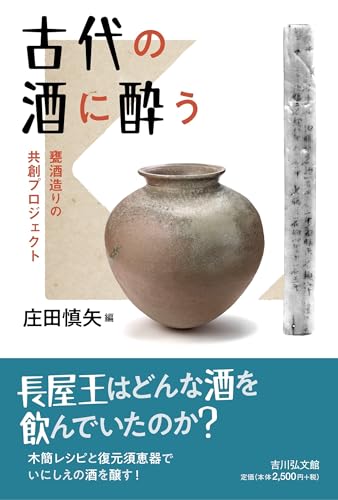書評
『安政コロリ流行記: 幕末江戸の感染症と流言』(白澤社)
「尾ひれ」にこそ人間社会の本質
江戸時代、パンデミックは珍しくなかった。浮世絵師の歌川広重(初代)も画人の鈴木其一(きいつ)も1858年の「安政コレラ」で死んでいる。当時の江戸は人口100万人。そこだけで3万人とも10万人ともいわれる死者が出た。安政コレラは江戸文学のルポルタージュを生んだ。仮名垣魯文(かながきろぶん)(野崎文蔵)は幕末・明治前期の戯作者・新聞記者だが、この人が『安政箇労痢(コロリ)流行記』というルポを書いてベストセラーにした。本書は、このコレラ本を翻刻、現代語訳し、解説したものだ。仮名垣は立派。ちゃんと長崎の出島にいたオランダ軍医・ポンぺの奉行所への勧告書を入手。コレラが隣国中国で流行し、来航したペリー艦隊のミシシッピー号での患者発生を報道。この船からコレラが日本に持ち込まれたと匂わせ「日本国のみ右病の流行するにあらざる…世界のわづらひ(パンデミック)」であると示した。さらには欧州で行われている感染対策を掲載。キュウリ・スイカ等の食禁、寝冷え防止、疲労防止、節酒、下痢をみればすぐ治療の五つだ。感染が激烈だった8月については日別の感染死者数まで載せている。さらには、幕府のお救いが「三才以下」にはなく、男は米5合、女は米3合の一律給付であったとも記す。前半はパンデミックの「事実」報道として完璧である。
ところが、このルポは後半になると、現代人には理解不能な記事のオンパレードになる。現実には存在しないはずの幽霊や疫病神、コレラの正体とされる狐狼狸(コロリ)なる意味不明の獣などが次々に登場する。話はそれるが、先日、私は勤務先の国際日本文化研究センター所長の井上章一さんと「歴史のミカタ」について対談した。話すうち、自分すなわち歴史学者の悪癖に気づいた。歴史学者は「事実」ばかりを重視して追いかける。井上さんは言った。事実から派生する「尾ひれ」が大事なのだ、と。事実でない「尾ひれ」がどのように付くか。そこにこそ人間社会の本質が現れるというのだ。
幕末、コレラの病原体は見えない。幕末人は見えないコレラにおののいた。見えないままでは不安である。嘘でもいい。コレラを可視化したい。その心理が働いた。そこで幕末人はコレラの正体=狐狼狸という架空獣の姿を脳内に作り、それを集団幻想として共有した。コレラという「事実」から派生した嘘の「尾ひれ」である。本書の解説部ではこれを疫病の「擬獣化」と呼んでいる。人家に忍び寄る妖しい害獣のイメージが狐・狼・狸(おおかみ たぬき)などと合体したのであろう。しかも、コレラは人に「取り憑く」狐狸(こり)と同一視された。元来、アメリカのペリー艦隊=異人が日本に持ち込んだと認識されていたから、アメリカは「憑き物使い」のイメージでみられていたと、本書は指摘する。おそらく、その通りであろう。幕末の攘夷運動には異人を狐狸の妖術使いに見立てる深層心理が働いていた。そして、この事実ではない嘘の「尾ひれ」のほうこそが現実の歴史を大きく動かした。感染力の強いコロナ変異株のまん延を前に、IOCと東京都と国は「恐怖の五輪」を開催しようとしている。正気の沙汰ではない。これほどの恐怖が国民に植え付けられれば、幕末同様、歴史を乱すに足る「何らかの深層心理」が国民間に生じるやも知れぬ。悪い予感がする。
ALL REVIEWSをフォローする