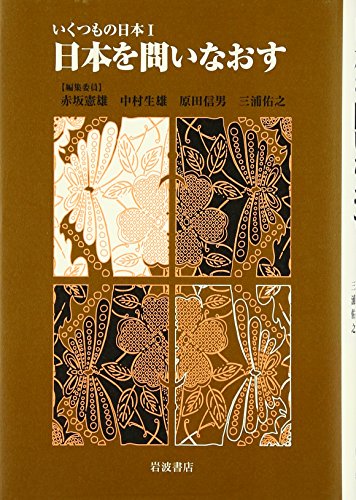書評
『里の国の中世』(平凡社)
列島のうねりの中の茨城の歩み
今年二月に急逝した網野善彦の近刊である。といってもこれは、『茨城県史』に書かれた中世の執筆部分であって、それを「里の国の中世」という題で出版したものである。網野の若い頃からの主要なフィールドは若狭と常陸であり、そのうち若狭を網野自身が「海の国」と命名したことから、本書を「里の国」と命名して書名としたという。
ただ常陸・北下総のような、海あり、里あり、山あり、の地を形容するのに「里の国」と集約するのは、本書の内容からしてもふさわしくない。
地域の歴史を描くのは簡単なようで、実はたやすいことではない。まず、歴史の全体の流れを簡潔にわかりやすく叙述すること、ついで身近な地域に即して詳しく描くことが強く求められる。読者は主にその地域に住む住民であれば、これは当然のことであろう。
しかしそれがいかに難しいことか。というのも、他方で、新しい研究の成果も盛り込まねばならないからである。地道なフィールドワークを行い、地域に即した歴史を掘り起こさないと、それらは達成できない。
また地域には、古くからの郷土の研究が行われてきており、分厚い蓄積があるのが普通で、それを視野に入れないと、生きた地域の歴史を描くことはできない。しかも土地には何らかの歴史上の人物などとの関係者もいるので、そことの折り合いも必要になってくる。
したがってこれらを調和させて上手に叙述するのは至難の業となる。ところが、網野は古代末期から中世前期にかけての茨城県下(常陸・北下総)の海・山・里の激動のうねりを描ききっている。
平将門の乱が起きる前後の動きから、荘園公領制の展開、鎌倉幕府の成立を経て、幕府が滅亡するに至るまでをダイナミックに描くのは網野ならではのことだが、なかでも東北地方と関東地方との交流の動きからこの地域の特性を描いた点や、荘園・公領の詳しい動きを丹念に追った点は圧巻である。
そのうえ、信太荘の現地調査に基づいて新しい知見を提供したり、系図を発掘して、これまで知られていなかった多くの事実を提供したことは、研究上の大きな成果である。
断片的な史料を使って読み応えのある歴史を描くのは、並大抵の作業ではなしとげられない。系図の片隅に記されている字句をとりあげ、各地に残る地名に注目し、発掘の成果を生かしてゆく。あらゆる情報をどん欲に拾い上げて、その情報の背後にある歴史の流れをつかんでゆく。
かと思うと、何故この件に関しては、幕府の歴史を描いた『吾妻鏡』に載せられていないのかという考察をもめぐらし、歴史を再構築してゆく。
こうして「網野史学」と称されるように、列島の歴史の大きなうねりのなかで、茨城県地方がどのような歴史を歩んできたのかを描いているのである。
堤禎子の解説は、そうした網野がいかに地域史の叙述にあたっていたのかを、幾つかの挿話を交えて語っていてまことに興味深い。そこからは網野の歴史に取り組む姿がよく伝わってくる。
ところで、こう苦労して書いても、県史や市町村史などは一部の人間しか見ることもなく、図書館や自治体の長・議員の書庫に眠っているのが現実である。
その点で、網野の叙述がこのように本書で広く見ることができるようになったのは貴重である。が、さらに網野の業績の総体を明らかにする必要がある。
ALL REVIEWSをフォローする