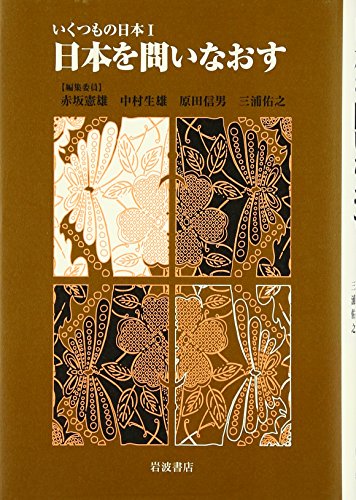書評
『雪舟: 旅逸の画家』(青史出版)
時代に柔軟に対応した姿を描く
近代以前の画家のなかで最も知られた存在といえば、雪舟をおいて他はなかろう。山水画、水墨画の大成者としてのそれであり、逸話も多い。しかしその実像となると、著作がないだけにほとんど明らかでない。手掛かりは、雪舟の描いた絵と絵に書かれた賛、周辺の人々の証言である。
それらを丹念に調べ、読み解くこと、その背景をきちんと把握することが何よりも必要とされるが、本書はそうした試みである。
最初に、雪舟の友人の万里集九の証言から入る。澄んだ水を汲んだ後、絵筆をとって描き始めるのかと思うと、そうではなく、やおら尺八を取り出して吹き、さらに歌や詩を謡い、吟じた末に、意気揚々と画面に臨んだという。
ここから著者は琵琶を抱える雪舟の自画像に注目し、音楽・芸能と画家との関係、さらには芸能と禅僧との関係などに触れて、雪舟の存在を一休や一路居士などの風狂の僧のなかにおいて捉える。
ここに著者の雪舟への接近の方法がよくうかがえよう。雪舟の存在を窮屈な禅僧の画家という枠に閉じ込めないで、振幅の多様性においてとらえようとするものである。このことは雪舟を画業一筋の人と見るのではないことからもよくうかがえる。
雪舟は当代随一の画僧であった周文を慕って相国寺に入ったとこれまでされてきたが、そうではなく相国寺に入って初めて水墨画に目覚めたとする。
さらに「拙宗等揚」という画家を、「雪舟等楊」との画風の違いから別人とされていたのを同一人物であるとして、画風の変化こそが雪舟の面目を伝えるものと見る。
こうして著者は雪舟の旅に即しつつ、その画業を探ってゆく。どのような旅でいかなる絵を描いたのか。絵が描かれたのはいつかを考え、その旅の時期や絵の背景と社会を考える。
まずは京を離れて、周防の山口に下り、そこからさらに大陸への渡航を目指した行動の意味を探る。近代の画家がヨーロッパに出かけて西洋絵画に触れたのと比較しつつ。
齢五十に達しての外国渡航、異文化との接触は何をもたらしたのか。多くは彼我の差に圧倒され、若くして渡航すべきだったと痛感する。ことに水墨画を学ぶとなれば、大和絵とは違った景色を描いているので、自分を見失うことになろう。
しかし雪舟は違った。明での滞在を契機にして雪舟は大きく成長した。画師を求めたが、「揮染清抜の者は稀なり」という認識に達し、そこで新たな境地を開いた。
雪舟がわずか二年間ほどの滞在で、中国画を完璧にマスターしたのは、その天分とともに、その天分を支える思想の故であり、宋学の素養が重要な意味をもっていたと説く。雪舟は乏しい資金のなかから朱子の版本を求めて帰国している。
こうして帰国してから三十年にわたり、各地を旅しながら、風景を描き、求めに応じて様々な絵を描いていった。九州を遍歴し、東国を遊覧するなど、その足は全国に及ぶ。時は応仁の乱後の戦乱の時代であったが、傑作が次々と描かれた。
こうした雪舟の生涯を見てゆくと、時代と社会に柔軟に対応している姿が認められ、バックボーンにしっかりした思想のあることが読み取れる。
私には、あまり好きになれなかった水墨画であるが、そんなことを考えつつ、雪舟の絵画を改めて見てみたくなった。そのためにも、雪舟の画業と足取りを示す年譜を入れて欲しかった。
ALL REVIEWSをフォローする