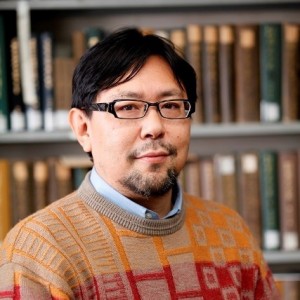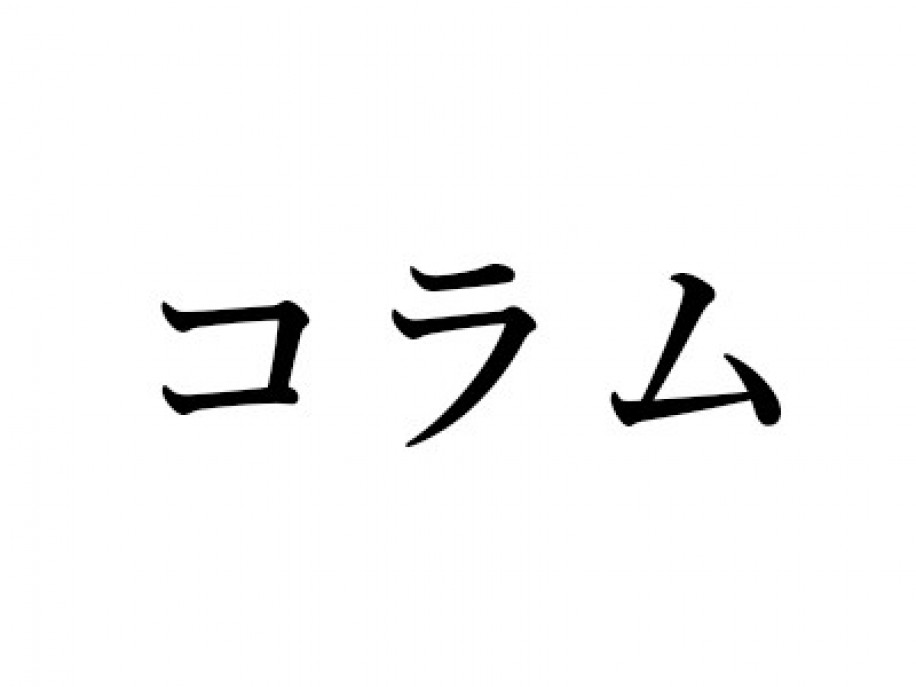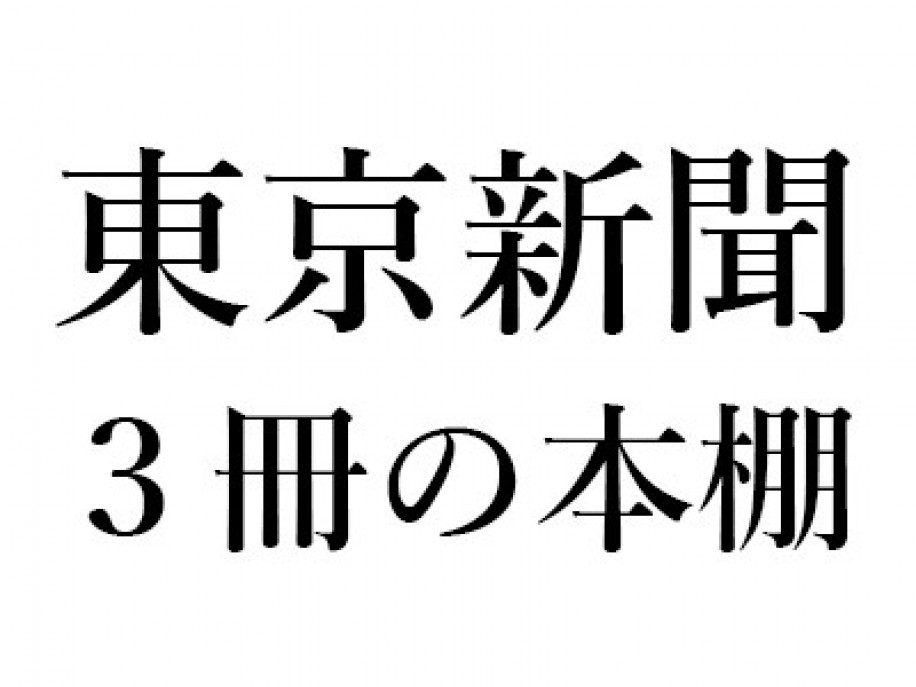書評
『桜狂の譜 —江戸の桜画世界』(青幻舎)
儚く咲く美しさに取り憑かれた絵師たち
高校の古文で習った。平安時代以来、「山」といえば比叡山延暦寺、「寺」は三井寺(みいでら)。同様に「花」というのは桜のことで、日本人は古来、桜をこよなく愛してきたのだと。ぼくは最近、この常識に疑問を抱いている。というのは町の名前。近世、各地の大名は新しい城下町を形成し、それが現在の県庁所在地や県内有力都市へと繋(つな)がる。大名は開発した町に名を付けるが、このときに松山・高松・松江・浜松・松本・松代・松阪・若松など、「松」の字が多く用いられるのに対し、「桜」は使われていないのだ。
徳川家康の旧姓である「松平」の一字を、という意図もあるだろうが、お城の屏風(びょうぶ)に好んで描かれる松(赤穂浪士事件の「江戸城・松の廊下」はこれに由来する)も考慮すると、武士は松が好きだったのではないか。はらりと潔く散る桜より、常に緑を絶やさぬ松。お家の安泰と永続を願う武士は、貴族の価値観とは別に、積極的に松を選んでいるように思うのだ。
このことを念頭に置いて本書を繙(ひもと)くと、また違う「桜」を見ることができる。「桜が咲くのは日本だけ」と信じ、取り憑(つ)かれたように桜を描き続けた画家がいた。“畸人(きじん)”三熊思孝(みくましこう)(1730~94)。著者は彼の事績を掘り起こし、博物学的な視点も取り入れて桜を描き続けた彼とその周囲の人々を「三熊派」と名付けた。本書は彼らの画業を丹念に紹介しながら、その意義を的確に教えてくれる。とても美しく仕上がっていて、本書を肴(さかな)に杯を傾ければ、いつでも花見が楽しめる。
三熊派は残念ながら絶えてしまうが、彼らの業績があったからこそ、文化人発の桜への愛情は武士や庶民にも浸透し、本当の意味での桜好きな日本人が出現してくるのではないか。
ALL REVIEWSをフォローする