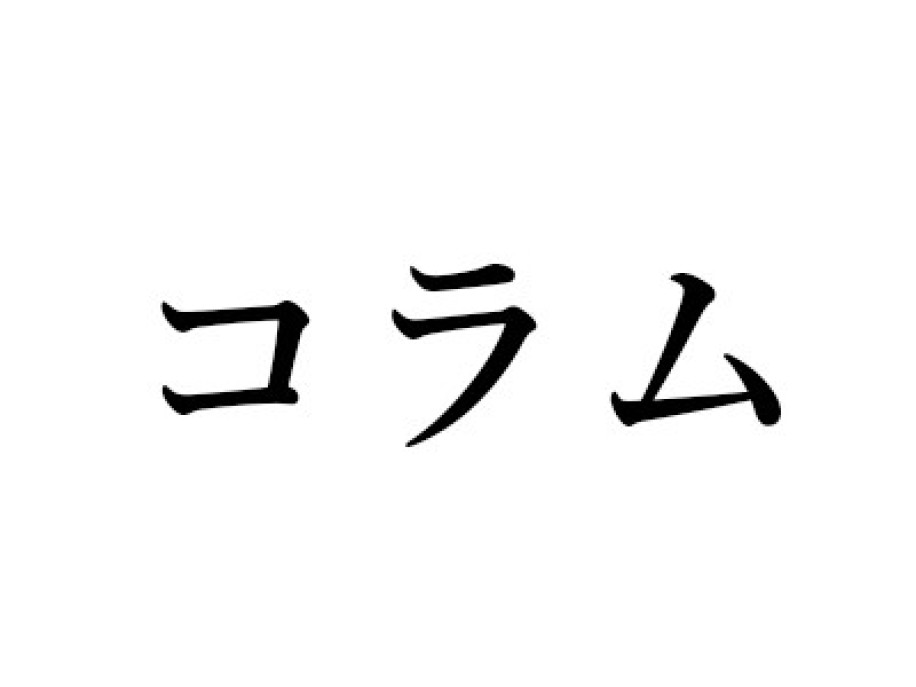書評
『謎ときエドガー・アラン・ポー:知られざる未解決殺人事件』(新潮社)
読者も騙す巧緻に仕組んだ挑戦
著者三冊目の謎とき本だ。小説には、読者から見ると作者が書いたと思ったことが書かれておらず、作者が書いたはずのないことが書かれている――そういうことがあるのだと実感させられたのが『謎ときサリンジャー』だった。著者が今回挑むのは、ポーの五編の推理小説のなかでも最も奇妙とも言える「犯人はお前だ」の謎である。本職の探偵が出てこない本作は筆致がコミカルで、シャトー・マルゴーの木箱から死体が飛びだすなどのこけおどし的トリックもあり、ミステリのパロディと捉えられることさえある。
あるとき町の金持ちが行方不明になり、乗っていた馬だけが手負いで帰ってくる。金持ちには放蕩(ほうとう)者の甥(おい)ペニフェザーがおり、状況と物的証拠から伯父殺害の犯人とされる。探偵役となったのは被害者の親友の人格者グッドフェローである。
ところが事件解決と思いきや、今度は語り手が探偵役になり、このグッドフェローこそが真犯人だと暴くのである。「犯人はお前だ!」と死体に指示(さししめ)された彼は真相を吐露し、その場で絶命。甥は財産を相続して幸せに暮らしましたとさ――。
しかし竹内いわく、これはポーが巧緻に仕組んだ「未解決殺人事件」であり、ポーからの挑戦なのだと。真犯人は他にいる。ポーはこの完全犯罪によって作中の村人だけでなく、読者をも騙(だま)したのだ(この先ネタばらしあり)。
なんと、真犯人は語り手とペニフェザーだと言う。この推理の手がかりとなったのは、二箇所に出てくるinとoutという小さな対句だ。ここから竹内は語り手とオイディプス王の平行性を看破していく。オイディプス王もまた「犯人はお前だ」と名指された人なのである。
「マリー・ロジェの謎」「盗まれた手紙」「モルグ街の殺人」などの分析も取り入れながら、この名のない語り手とグッドフェローが鏡像関係にあることや、「アンフェアな語り」の意図が鮮やかに解きほぐされる。さらにはポーの「のこぎり山奇談」「ウィリアム・ウィルソン」や「アッシャー家の崩壊」といった他作品の死の“真相”までが明らかになる。なんというスリルと快感だろう。
小説の語りの歴史に鑑みると、「犯人はお前だ」の超越的な文体トリックが見えてきそうだ。近代的リアリズムの発達過程のなかで、物語内容と関係を持たない語り手は隠され、擬装され、消されてきた。近代的語り手は実体のない客観的視点になるか(非劇化型)、物語内のキャラクターになるか(劇化型)である。
「お前が犯人だ」のナラティヴは十九世紀半ばだからこそ成立したのではないか。この語り手は何の立場表明もなく語り続けることができ、なぜか重要人物たちの会話を耳にしながら、そこに居合わせた理由は説明せず、そのうち三人称客観文体のように「私」の存在感を消したかと思うと、一人の登場人物として謎ときをしたりする。なんと融通無碍(むげ)な! ポーの高度な文体的目眩(めくらま)しが自然に受け入れられたのは、ナラティヴが過渡期にあったからではないか。
自在に前景化と後景化を繰り返す、稀代(きたい)の“信用できない語り手”。竹内の書を読めば、本作が戦略家ポーの最高傑作であることに気づかされるのだ!
ALL REVIEWSをフォローする