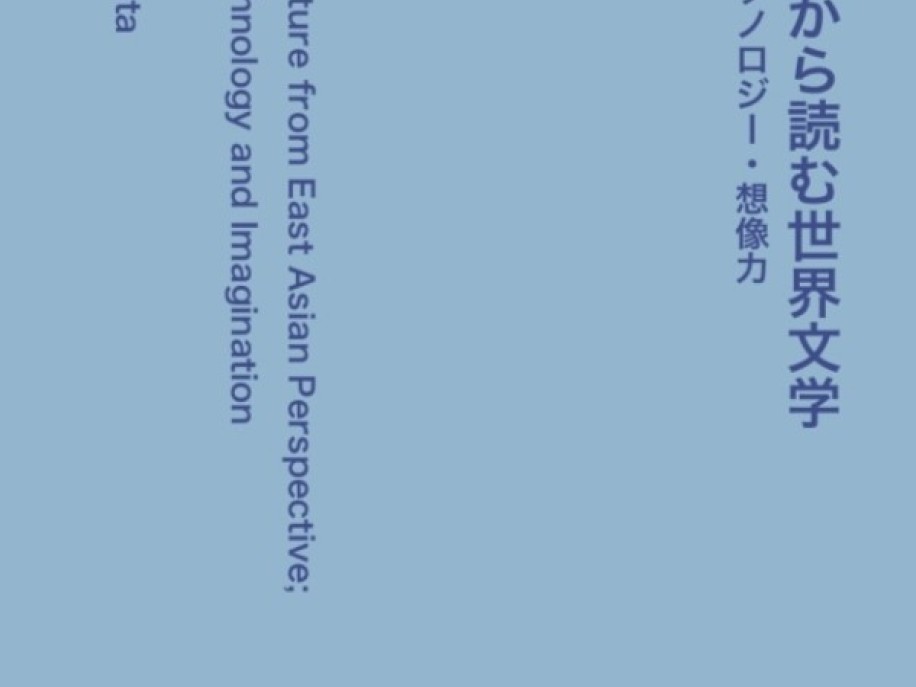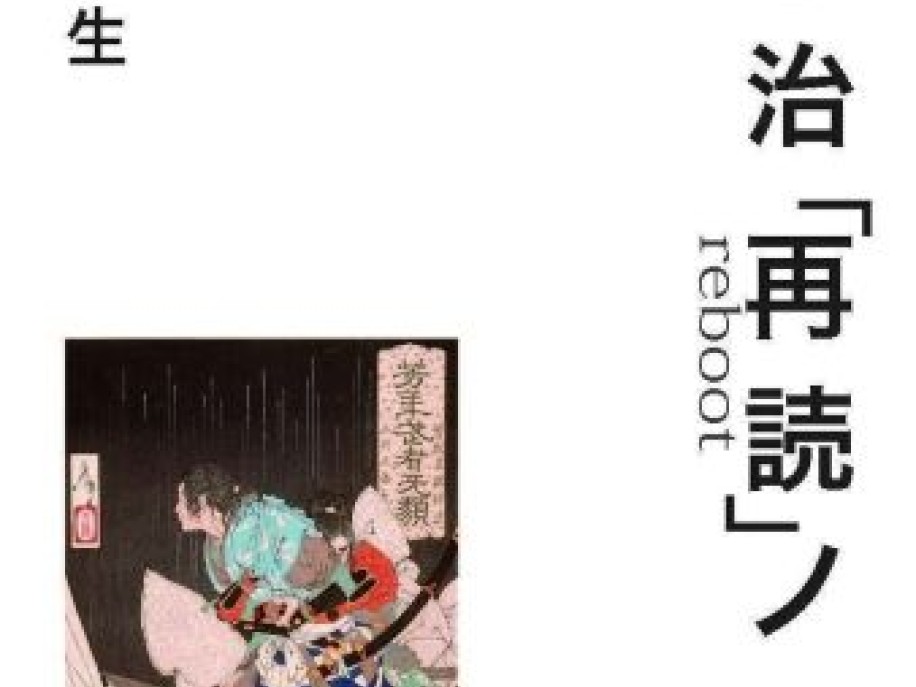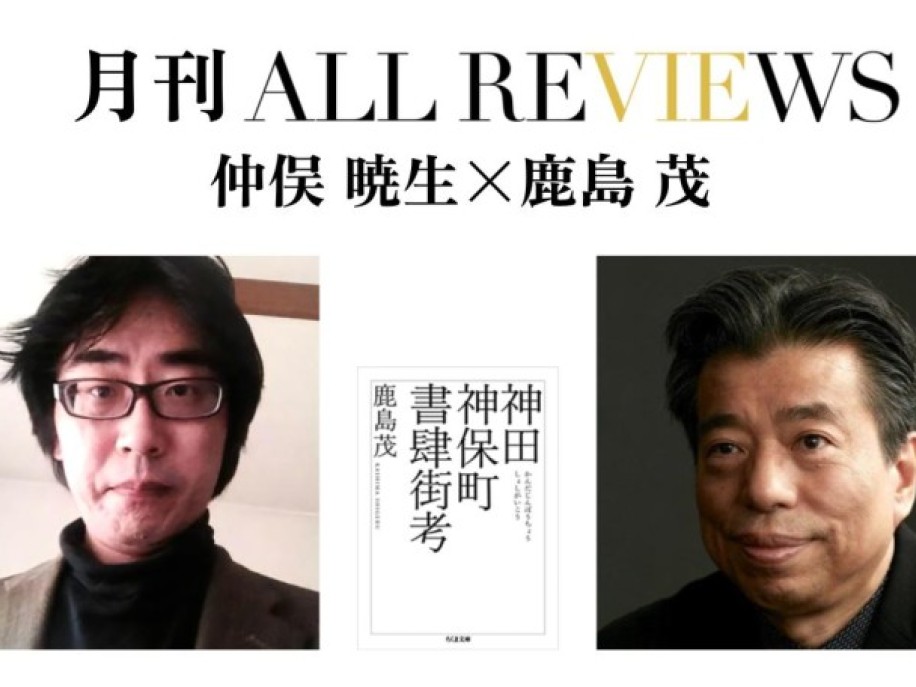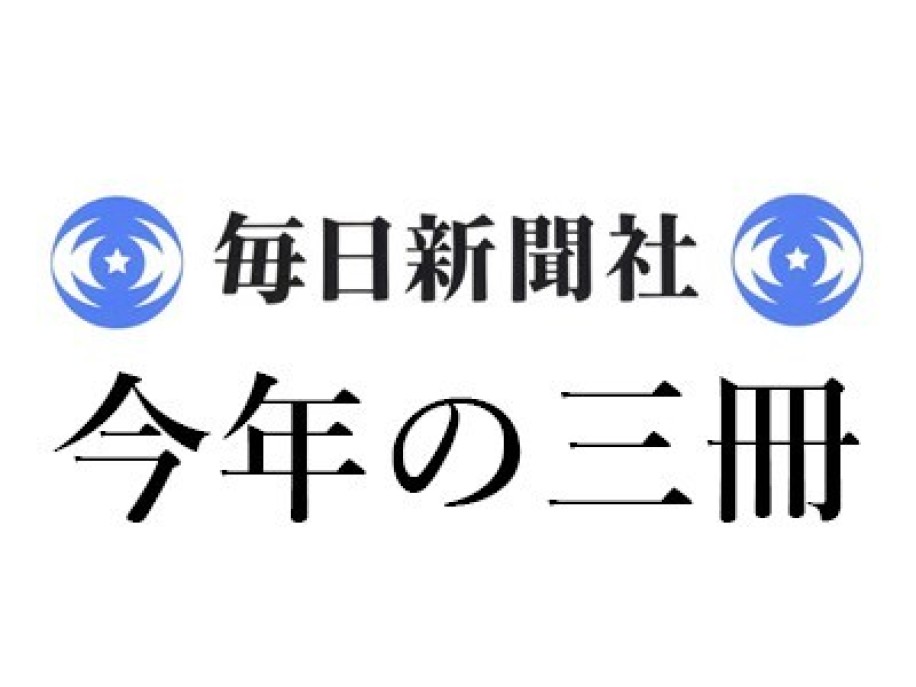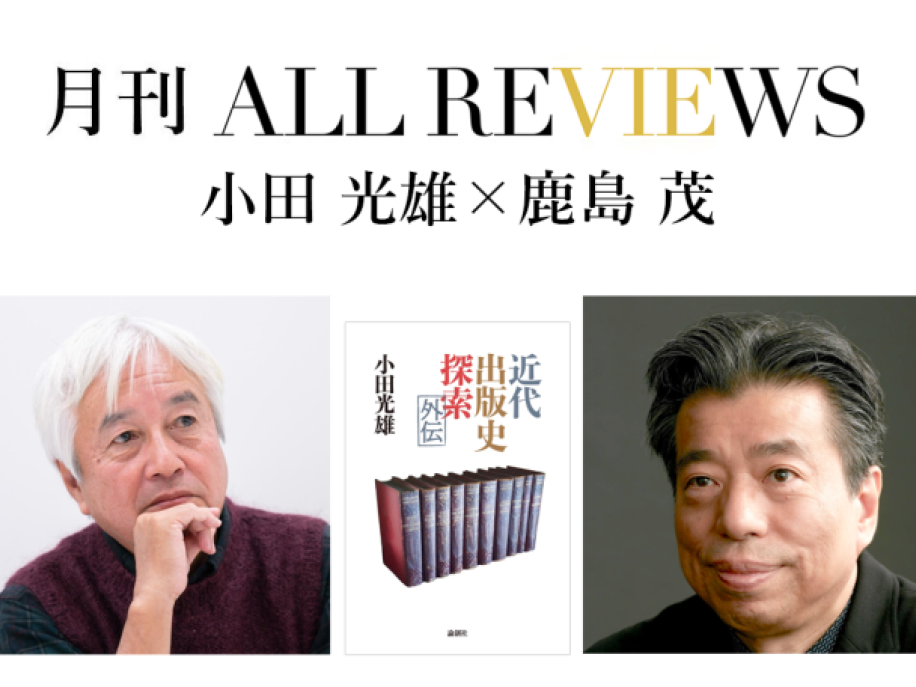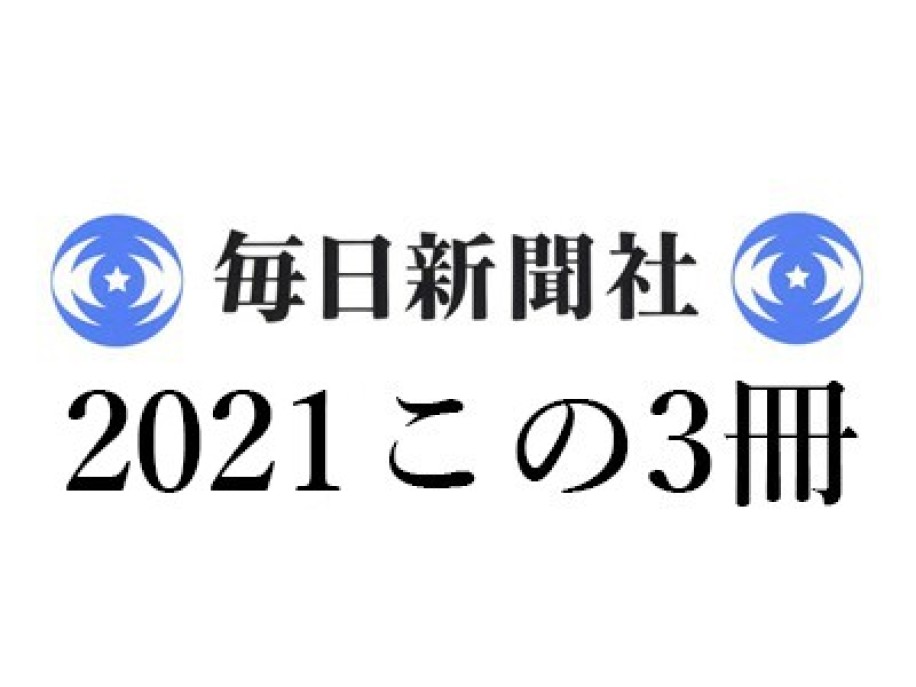読書日記
小田 光雄『出版状況クロニクルⅦ』(論創社)、仲俣 暁生『橋本治「再読」ノート』(破船房)
出版流通崩壊の前に
×月×日年末から春にかけて、必要もないのに大出版社の文学賞受賞パーティーに出るように努めていた。いよいよ現実味を帯びてきた出版流通の大崩壊に対して、みながどのような危機感を抱いているかを知りたかったからだ。
で、結果はというと、これが驚くほどの危機感のなさ。まさに他人事で、大出版社の社員は恒久的に身分が保証されると信じているようだ。
だが、出版流通の崩壊は悪ければ今年中、遅くても二、三年後には確実に起こる。『裸足の伯爵夫人』で、ロッサノ・ブラッツィ演じる伯爵が述懐するように「起こるべきことはかならず起こる」のだ。
というわけで、出版にかかわるすべての人に読んでもらいたいのが小田光雄『出版状況クロニクルⅦ』(論創社 三〇〇〇円+税)である。
この本を一読してわかったのは、日本の出版流通が置かれた状況を太平洋戦争のそれにたとえれば、インパール作戦とレイテ沖海戦に負けた昭和十九年末の段階どころではなく、沖縄戦に敗北し、あとはヒロシマ・ナガサキとソ連の満州侵略を待つだけの昭和二十年七月の段階まで来ているということである。
とりわけ衝撃的なのは二〇二三年十二月の「出版状況クロニクル36」の〔5〕の業界専門誌「新文化」の記事の要約である。
すなわち、二大大手取次の一つである日販が二五年二月をもってコンビニ二社の流通をやめるという決定を行い、コンビニ二社に伝えたが、一方のトーハンでも肩代わりできる態勢が整っておらず、二五年中には空白の期間が生じる恐れがあると書かれている。
一番心配したのはコンビニ2社が雑誌販売を止めることで、もしそれらの雑誌棚が撤去されれば、『共用配送』の仕組みが壊れてしまい、雑誌出版社と雑誌文化の危機ともなってしまう。
書店1万店の輸送網は6万店のコンビニルートによって成立しているし、コンビニ流通を守ることは書店配達を維持することと直結する。日販の決定は多くの企業に巨額の費用を発生させ、不安定化リスクをもたらすといわざるをえない。
他産業では流通コストを流通側、小売側が販売価格に転嫁するが、再販制度下にあるこの業界では出版社にしか価格決定権がない。本の原価には書店マージン、流通コストなども含まれているはずなのに賄いきれておらず、原価率を変えるか、改革販売を見直すしかない。
これらの分析を踏まえて著者はこうコメントしている。
ここで再販委託制の実質的な崩壊が出版流通の只中にも及んでいることを確認したことになるが、2で見たように、コンビニ売上もまだ下げ止まりではない。トーハンが代行したとしても、問題が解決されたわけではないのだ。
経産省が書店振興プロジェクトチームを立ち上げたと聞いた。それならば、状況の深刻さを正しく捉えるために、本書およびこれに先立つ『出版状況クロニクル』を読むことを強くお勧めしたい。まだ連合艦隊があるじゃないかなどとトンマなことを言い出さないために。
×月×日
では、物書きはどうかというと、こちらも同じくらいに危機感がない。未来永劫に本を出し続けることができると信じているようだが、流通網が崩壊したら、少なくとも紙の本を出すことは非常に困難になる。そこのところをまったくわかっていない。
そんな危機感のない物書き共同体の中でも、流通網崩壊後を見据えて、新しい出版流通形態を模索しようとする動きが出ている。
先駆的な雑誌だった『本とコンピュータ』の元編集者で、出版流通にも詳しく、文芸評論の著作もある仲俣暁生である。彼の最新刊『橋本治「再読」ノート』(破船房 一四〇〇円+税)はこの意味でとても画期的な一冊だ。というのも、これは流通網崩壊後にも唯一可能と思われる自費出版・自費流通・自費販売のシステムを構築するための実験的な試みであるからだ。自分の本は自分で流通させて自分で売る。これだけが唯一のサバイバルの道なのだ。
しかし、こういうと、いまではコミケや文フリもあるし、ネット通販もある。さらに、自費出版本を自費流通させて自費販売するいわゆるZineもかなり一般的になっているではないかという反論が予想されるが、これは違う。すでに著作が何冊かある作家が「あえて」自費出版・自費流通・自費販売のシステムの構築に挑み、その試行錯誤を介して、新旧のシステムの接合という第三の道を「あらかじめ」切り開いておくという、その点が新しいのである。だから、その方法はZineと似ているようで、かなり違っている。巻末に添えられた出版元の破船房についての次のような言葉はその違いをはっきりと示している。
破船房は(中略)自身による文芸評論をはじめ、思い立ったときにすぐ本を出せる『軽出版』を行うための仕組みとして、2023年春の文学フリマ東京を機会に活動を始めました。
こうした意味合いにおいて、対象として選ばれたのが橋本治なのはいかにも象徴的である。というのも、橋本治こそは、吉本隆明とは別の道をたどって「自立」にたどりついた思想家であるからだ。
事実、橋本はこの講演の後半でこうも述べている。初期の評論、『秘本・世界生玉子』や『花咲く少女たちのキンピラゴボウ』を書き始めた頃の動機は『自分の思想があれば自分の思想によっかかれるから楽だもん!』だった。なぜならば『橋本治という思想家が存在しなかった時代の橋本治が一番つらいんだよね』。一九七九年のデビューから、昭和という時代が終わろうとする一九八〇年代いっぱいをかけて、橋本治は『橋本治という思想』を成立させていったのである。
では、なにゆえに橋本治は「橋本治という思想」を自前で用意しなければならなかったのか? どうやら、その遠因を辿ると、橋本治が同時代に身を置きながら、どうしてもなじむことのできなかった全共闘の文体、すなわち六法全書の言葉をつぎはぎしたような「漢文」に対する居心地の悪さにあったようだ。
そして、それは構想されながらついに書かれることのなかった橋本治による全共闘小説の語り手=主人公が女だったことと深く関係しているのだ。
当時のさまざまな「理論」なるものは「漢文で書かれていた」と橋本は言う。おそらくそこからの連想で、橋本の話は当時とりかかっていた『枕草子』の現代語訳の話題に移る。(中略)全共闘世代の女の話と『枕草子』の現代語訳はどうつながるかというと、橋本がそこで問題にしたいことが「語られる中身」ではなく「語ってる言葉」、言い換えるなら態度(アティテュード)にあるからだ。
現代哲学では、「態度(アティテュード)」は身体性と呼ばれるものに近いだろう。この身体性という概念を導入すれば、著者が挙げている『秘本・世界生玉子』の中の「普遍」というものが何なのかがわかってくるはずだ。橋本治は語っている。
でも、僕達はもう知っている。僕達自身の中に普遍が存在しているということを。僕達自身という個の中にある普遍というのは、僕達自身だ。それが普遍である以上、それはすべてに共通するものだけれども、それが又僕達自身という個である以上、僕達が存在するその数だけ普遍というものは存在するのだ。
橋本治再評価の動きがこの一冊の「軽出版」から始まるかもしれない。オンラインではなく、活字と紙という身体性をもった「普遍」としての「本」。その普遍は「すべてに共通するもの」であると同時に、その数だけ存在する「個」でもあるからだ。
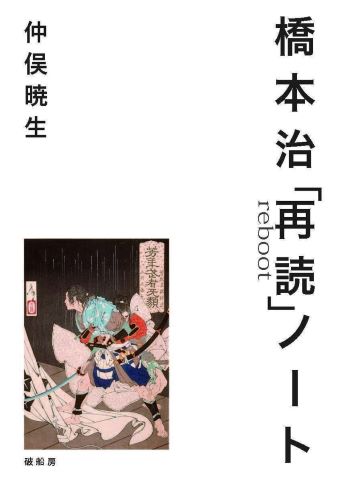
破船房/Shipwreck
破船房/Shipwreck(SOLIDA)
ALL REVIEWSをフォローする