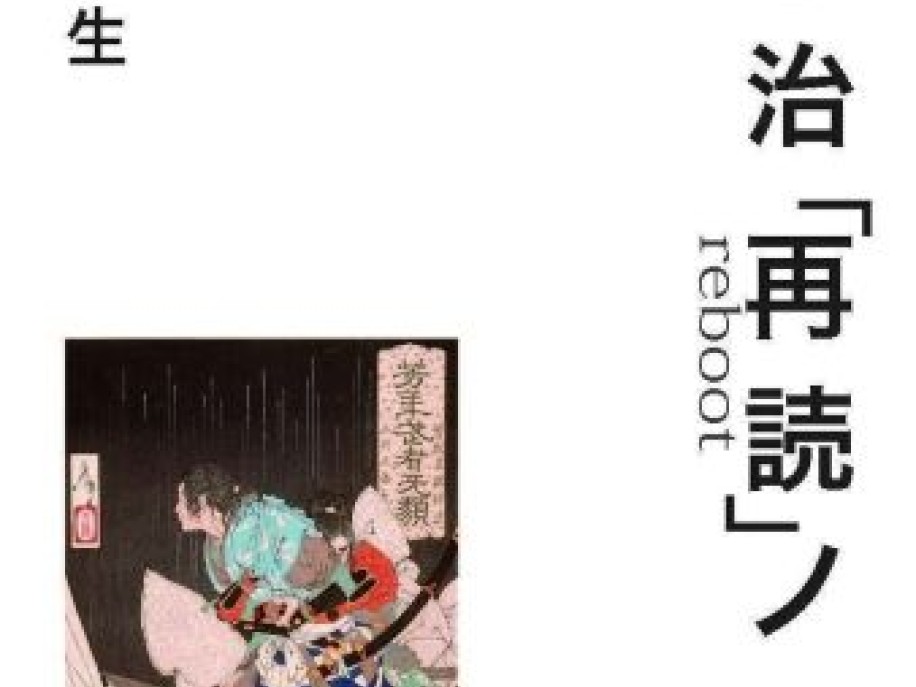前書き
仲俣 暁生『東アジアから読む世界文学──記憶・テクノロジー・想像力』(破船房)

はじめに──東アジアから世界文学を読む
二〇二四年のノーベル文学賞は韓国の作家、ハン・ガン(韓江)に与えられた。本書はそのことの驚きとよろこびの中で編まれた、いわば一種の緊急出版物である。私がこれまでに書いてきた書評のなかに、ハン・ガンを含む東アジアの重要な作家・作品を対象にしたものが十数本あることを思い出し、それらを一つの脈絡の中に置いてみたくなったのである。二〇一〇年代に入って、日本でも東アジア地域で書かれた文学作品が翻訳・紹介される機会が増えた。韓国のフェミニズム小説、中華人民共和国のサイエンスフィクション(科幻小説)、台湾のファンタジックな味わいの現代小説などである。
本書ではそれぞれを象徴する作家としてハン・ガン、劉慈欣と郝景芳、呉明益を置いた。作家と作品選択の根拠は私自身が愛読しているという、その一点にある。
もちろん各地域で展開している現代小説の姿は多種多様であり、彼ら彼女らのほかにもすぐれた作家が幾人もいることは間違いない。各地域の専門的な研究者や紹介者の尽力により、韓・中・台の現代小説が潤沢に紹介され、日本語で読める状況はよろこばしい。
でも私は、自分の愛読する数人の作家に対象を絞ってでも、この本で東アジアの現代小説に大きな輪郭線を描いてみたいと考えた。なぜならそのことは、日本の現代文学の姿を私たちが新たな視点でとらえ返す契機にもなるからだ。そのような意味で、この本をつくることは日本の現代文学を軸に文芸評論をつづけてきた私にとって、ひとつの里程標でもある。
日本の文芸メディアのなかで「世界文学」という言葉を目にすることが増えたのは二〇〇〇年代以後といっていい。それまでの文学全集的なニュアンスではなく「世界文学」という言葉がもちいられるようになった契機の一つとして、村上春樹を筆頭とする日本の現代文学が世界市場に受け入れられた事実を指摘するのはごく穏当な見方だろう。
とりわけ村上春樹がなぜ、これほどまで世界で広く読まれたのか──その「謎」を解くことは、日本の近現代文学史にこの作家をどのように位置づけるかとあわせて文学を語る者にとって大きな試金石でありつづけている。ひとまず言えるのは、二一世紀に入って経済・文化の両面で格段に進んだグローバリゼーションと村上春樹の世界的な受容とは切り離せないということだ。
日本でも一九八〇年代には新鮮であった「都会的なライフスタイル」や「高度資本主義」は、この四半世紀のあいだに西欧・北米以外の広範な地域でも一般化した。日本が「失われた三〇年」にわたり停滞し続けたのとは対照的に、世界規模で新しいミドルクラスの読者が誕生したのである。
文学作品がすぐれたグローバル商品でありうることは、村上春樹に限らず、ファンタジーやミステリー、サイエンスフィクションの世界で証明されてきた。しかし同時に、文学はローカルな言語や文化、歴史のうちに湛えられてきたものを記録する営みでもある。
このために「世界文学」をめぐる議論はつねに「翻訳」の問題と接続され、文学の翻訳可能性が議論されてきた。その視点からみれば、「グローバル文学」とは翻訳によって損なわれるものが少ない文学のことだといえるだろう。しかし世界文学は現代において「グローバル文学」としてしか存在しえないのだろうか。本書ではその問いに、もう一つの光をあてる試みでもある。
この本のタイトルにもちいた「東アジア」という言葉も、じつは取り扱いを慎重にすべき用語である。ほとんど「極東」と同義で用いられるこの言葉は、かつて日本が帝国主義的に支配した領域を、第二次世界大戦後のあらたな国際政治秩序のもとで呼び替えたものであり、必ずしもこの地域から内発的に生まれた「自称」ではない。つまり「世界文学」も「東アジア」も、本来は括弧にくくって考えるべき概念である。
それでもあえてこれらの言葉を本書の題名にもちいたのには理由がある。私がこれまでに著してきた現代小説論(『ポスト・ムラカミの日本文学』『極西文学論──Westway to the World』)はいずれも、日本が「極東」という名で呼ばれてきた第二次世界大戦後の政治的・経済的・文化的(当然、潜在的に軍事的な意味も含まれる)な文脈──加藤典洋が江藤淳から受け継いだ「アメリカの影」という問題意識──を前提としたものだった。
しかし、その視点からだけでは日本の現代文学をうまくとらえることができない、という不満と疑問が、この十数年のあいだに私自身のなかで生まれてきた。その意味で本書は、二〇年前の自著に対する現在からの返答ということもできるかもしれない。
本書の構成について、最後に記しておこう。第一章には、既発表の『失われた「文学」を求めて【文芸時評編】』と『その後の仁義なき失われた「文学」を求めて』と同様、『出版人・広告人』というリトル・マガジンでいまも継続している連載書評から、東アジアの現代文学にかかわるものを一〇本集めた(うち四本は前掲書に収められているものを再録した)。
第二章は季刊誌『kotoba』で二〇一九年から二〇二一年まで連載した「21世紀に書かれた「百年の名著」を読む」をすべて収録した。この章で取り上げた作品には原著が英語やイタリア語で記されたものもあれば、日本の作家のものも含まれるが、全体を通して読むと第一章で紹介した「東アジア」の現代小説をひろい文脈で捉え返す際の補助線になっていると思う。この連載を続けているときから、「世界文学」の配置をマッピングしなおしたいという気持ちがあったことを思い出した。
最後に、副題に「記憶・テクノロジー・想像力」という言葉をくわえたのは、文学作品は過去の「記憶」にとらわれるだけでなく、技術と想像力によって未来を切り開くものでもあると信じるからだ。そのための小さなブックガイドとして本書が役に立つことを祈っている。
目次
はじめに──東アジアから世界文学を読む
第一章
ハン・ガン『別れを告げない』──雪の白さの中で燃えさかる炎ハン・ガン『すべての、白いものたちの』──複雑に折りたたまれた過去を示す色
ケン・リュウ編『折りたたみ北京』──現代中国の多様性を析出する分光器
劉慈欣『三体』──中国大河SFは人類滅亡と革命を夢見る
郝景芳『1984年に生まれて』──二一世紀からのオーウェルへの返答
郝景芳『流浪蒼穹』──古典的宇宙SFに込められた祈り
呉明益『雨の島』──ネイチャーライティングが物語と出会うとき
四方田犬彦『戒厳』──もう一つの「一九八〇年代」へ
斎藤真理子『韓国文学の中心にあるもの』──日本文学の「中心」には何があるか
黒川創『世界を文学でどう描けるか』──サハリンとメアリ・シェリーの間に
第二章
イアン・マキューアン『贖罪』──「小説」と「小説家」についての小説ウンベルト・エーコ『プラハの墓地』──偽書と小説のあいだに
ジュンパ・ラヒリ『その名にちなんで』──名乗りとアイデンティティ
阿部和重『シンセミア』──戦後日本のミニチュア的寓話
リチャード・パワーズ『われらが歌う時』──色彩と音をめぐる家族小説
オルハン・パムク『雪』──詩と演劇を小説が包み込む
ハン・ガン『少年が来る』──過去と現在の往還
絲山秋子『離陸』──移動と鎮魂
リチャード・フラナガン『奥のほそ道』──線と円環のドラマ
呉明益『複眼人』──神話とリアリズムを超えて

お取り扱い店舗(通販有)
◆PASSAGE ラブレー通り4番地 (神保町・すずらん通り)破船房/Shipwreck
◆PASSAGE SOLIDA 1Fアルフォンス・アレー広場 4番地(神保町・靖国通り)
破船房/Shipwreck(SOLIDA)
ALL REVIEWSをフォローする