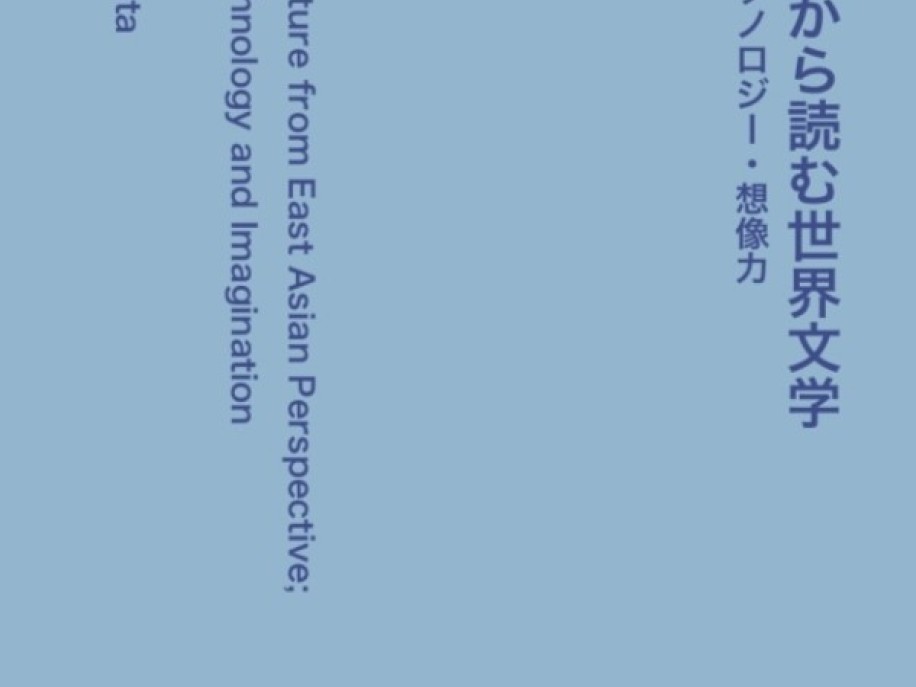書評
『房思琪の初恋の楽園』(白水社)
性被害を告発した人に対して、「なぜ今ごろになって」「逃げられたのでは」との疑念や仮定をぶつけ、告発を潰そうと試みる人がいる。冷静な指摘だと加担する外野もいる。複数の証言や裁判結果が出ても、「いやでも実は」が残る。いや、残そうとする。「どっちもどっち」を発生させ、うやむやにする。告発した人は、とりわけネット空間で永続的に言葉の暴力を受ける。
『房思琪(ファン・スーチー)の初恋の楽園』(林奕含(リン・イーハン)著、泉京鹿訳・白水Uブックス・1980円)は、著者唯一の小説。「実話をもとにした」と位置づけた作品を2017年2月に刊行、その2ケ月後に自ら命を絶った。
台湾・高雄の高級マンションに住む房思琪が、階下に住む50代の国語教師に作文を教わりに行き、強姦されてしまう。幼馴染みの劉怡婷(リュウ・イーティン)は彼女が残した日記を見つけ、おぞましい経緯を知る。
「文章を書きたいと思う子はみんな、歪んだ恋をすべきかもしれない」、国語教師は自身の一方的な快楽のために、自分の立場を振りかざす。「彼の話から聞き取れるのはいつも言い切りのピリオドであり、ひたすら肯定するだけなのだということに彼女は気づいた」。自分の弱さを打ち明けながら、その弱さに巻き込み、溺れさせるような関係を作り上げようとする。溺れてしまう私が悪い、その道を自ら選んだと思い込ませる強制力が言動を狂わせる。
起きてしまったことへの悔恨が憎悪に変わり、憎悪が相手ではなく自分に向かってしまう。傷つけられた、ではなく、自分の中にすでに刻まれてしまった傷が許せなくなる。抱えきれないものが体の中に蠢(うごめ)いてしまった時、それを言葉にするのは難しい。どうしたって吐き出しきれない葛藤が溜まっていく。
「もし読み終わって、かすかな希望を感じられたら、それはあなたの読み違いだと思うので、もう一度読み直したほうがいいでしょう」
著者が刊行に際してプレスリリースに記した言葉だ。簡単に希望を口にして落ち着かせるのもまた暴力なのだ。
『房思琪(ファン・スーチー)の初恋の楽園』(林奕含(リン・イーハン)著、泉京鹿訳・白水Uブックス・1980円)は、著者唯一の小説。「実話をもとにした」と位置づけた作品を2017年2月に刊行、その2ケ月後に自ら命を絶った。
台湾・高雄の高級マンションに住む房思琪が、階下に住む50代の国語教師に作文を教わりに行き、強姦されてしまう。幼馴染みの劉怡婷(リュウ・イーティン)は彼女が残した日記を見つけ、おぞましい経緯を知る。
「文章を書きたいと思う子はみんな、歪んだ恋をすべきかもしれない」、国語教師は自身の一方的な快楽のために、自分の立場を振りかざす。「彼の話から聞き取れるのはいつも言い切りのピリオドであり、ひたすら肯定するだけなのだということに彼女は気づいた」。自分の弱さを打ち明けながら、その弱さに巻き込み、溺れさせるような関係を作り上げようとする。溺れてしまう私が悪い、その道を自ら選んだと思い込ませる強制力が言動を狂わせる。
起きてしまったことへの悔恨が憎悪に変わり、憎悪が相手ではなく自分に向かってしまう。傷つけられた、ではなく、自分の中にすでに刻まれてしまった傷が許せなくなる。抱えきれないものが体の中に蠢(うごめ)いてしまった時、それを言葉にするのは難しい。どうしたって吐き出しきれない葛藤が溜まっていく。
「もし読み終わって、かすかな希望を感じられたら、それはあなたの読み違いだと思うので、もう一度読み直したほうがいいでしょう」
著者が刊行に際してプレスリリースに記した言葉だ。簡単に希望を口にして落ち着かせるのもまた暴力なのだ。
ALL REVIEWSをフォローする