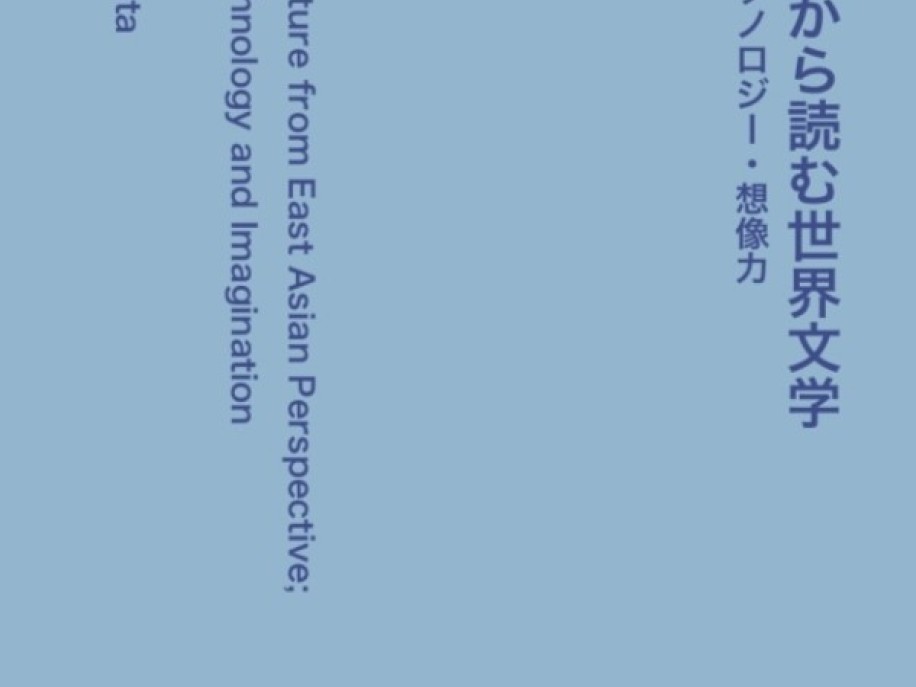書評
『至福のとき: 莫言中短編集』(平凡社)
莫言。「○○のガルシア=マルケス」なんて言い方、飽き飽きなさっておられましょう? しかし、莫言に関しては嘘偽りなし、と申しますか、紹介が英米に偏っている翻訳文学の中にあって埋没しがちな中国の、この偉大な才能を広く知らしめたい、そんな熱意がガルシア=マルケスというポピュラリティの高い名を挙げさせたと、お考えいただきたいのである。
たとえば、九十六年に翻訳された人肉食をめぐる驚異のミステリー『酒国』を読んでほしい。ヒーローがヒーローたる活躍を見せない、人肉食の謎が明らかにされないという点で、これは推理小説の形式を借りたアンチ探偵小説。また、美食と酩酊に支配される超現実世界を提示することで、独自の文化を培ってきた中国の波瀾万丈の歴史に内包される真実と虚構の構造を暴いたアンチ・ユートピア小説でもあり、かつ、遊戯としての文学に取り組んだゲーム小説の貌(かお)も持ち合わせているのだ。まさにアジアン・マジックリアリズムの傑作!
中短篇集『至福のとき』では、その莫言の多彩な“語り口”が味わえる。定年まであとひと月というところでリストラされた老人が、放置されていたバスをカップル向けの簡易モーテルにしてみたところ――というユーモラスな幽霊譚の表題作は落語。自転車と車でごった返している大通りにロバに乗った美女と古代の甲冑に身を固めた騎士が突然現れる「長安街のロバに乗った美女」は、頭がくらっとするほどナンセンスなオチが効いた幻想コント。長年逢わなかった小学校時代の同級生にばったり出くわし、金がないから帰りの旅費代を出せだの飯を食わせろだの要求される、何やら太宰治の「親友交歓」のような不穏な空気で始まる「宝の地図」はパワフルなホラ話。ある恋愛の情景をスケッチ風に描いた「沈園」は心理小説。イナゴの襲来を背景に〈青草を食べ、臭わないクソを垂れる〉奇妙な草食一族の愛憎の歴史を描いた「飛蝗」はマジックリアリズム。一冊で五通りもの語り口が楽しめる非常にお得な作品集なのだ。
とりわけ一読をおすすめしたいのが「宝の地図」と「飛蝗」だ。図々しい同級生が吹きまくるホラ話に、騙(かた)りの魅力たっぷりの中国の話芸を仕込んだ前者。五十年前と今、二度にわたるイナゴの大量発生事件を軸に、草食一族の現代と過去が呼応しあう後者。掟を破った男女を火炙りの刑に処したり、同じ女をめぐって兄弟が血みどろの争いを繰り広げたり、イナゴの神様と約束して廟を建てたり、騒動にこと欠かない草食一族のバカバカしくも壮大な物語には、圧倒されるばかりだ。〈われわれのクソは商標を貼ったバナナみたいに美しいのに〉だの、〈クソをしたあと、生活は花の盛りのように素晴らしく感じられ〉だの、この一族のクソに対する思い入れの深さがまた可笑しくて。ガルシア=マルケスがなんぼのもんじゃい! 中国四千年のパワーを体現する、この偉大な作家の魅力の一端を、ぜひ垣間見ていただきたいっ。
たとえば、九十六年に翻訳された人肉食をめぐる驚異のミステリー『酒国』を読んでほしい。ヒーローがヒーローたる活躍を見せない、人肉食の謎が明らかにされないという点で、これは推理小説の形式を借りたアンチ探偵小説。また、美食と酩酊に支配される超現実世界を提示することで、独自の文化を培ってきた中国の波瀾万丈の歴史に内包される真実と虚構の構造を暴いたアンチ・ユートピア小説でもあり、かつ、遊戯としての文学に取り組んだゲーム小説の貌(かお)も持ち合わせているのだ。まさにアジアン・マジックリアリズムの傑作!
中短篇集『至福のとき』では、その莫言の多彩な“語り口”が味わえる。定年まであとひと月というところでリストラされた老人が、放置されていたバスをカップル向けの簡易モーテルにしてみたところ――というユーモラスな幽霊譚の表題作は落語。自転車と車でごった返している大通りにロバに乗った美女と古代の甲冑に身を固めた騎士が突然現れる「長安街のロバに乗った美女」は、頭がくらっとするほどナンセンスなオチが効いた幻想コント。長年逢わなかった小学校時代の同級生にばったり出くわし、金がないから帰りの旅費代を出せだの飯を食わせろだの要求される、何やら太宰治の「親友交歓」のような不穏な空気で始まる「宝の地図」はパワフルなホラ話。ある恋愛の情景をスケッチ風に描いた「沈園」は心理小説。イナゴの襲来を背景に〈青草を食べ、臭わないクソを垂れる〉奇妙な草食一族の愛憎の歴史を描いた「飛蝗」はマジックリアリズム。一冊で五通りもの語り口が楽しめる非常にお得な作品集なのだ。
とりわけ一読をおすすめしたいのが「宝の地図」と「飛蝗」だ。図々しい同級生が吹きまくるホラ話に、騙(かた)りの魅力たっぷりの中国の話芸を仕込んだ前者。五十年前と今、二度にわたるイナゴの大量発生事件を軸に、草食一族の現代と過去が呼応しあう後者。掟を破った男女を火炙りの刑に処したり、同じ女をめぐって兄弟が血みどろの争いを繰り広げたり、イナゴの神様と約束して廟を建てたり、騒動にこと欠かない草食一族のバカバカしくも壮大な物語には、圧倒されるばかりだ。〈われわれのクソは商標を貼ったバナナみたいに美しいのに〉だの、〈クソをしたあと、生活は花の盛りのように素晴らしく感じられ〉だの、この一族のクソに対する思い入れの深さがまた可笑しくて。ガルシア=マルケスがなんぼのもんじゃい! 中国四千年のパワーを体現する、この偉大な作家の魅力の一端を、ぜひ垣間見ていただきたいっ。
初出メディア
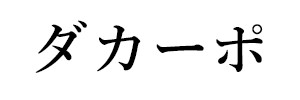
ダカーポ(終刊) 2002年12月18日号
ALL REVIEWSをフォローする