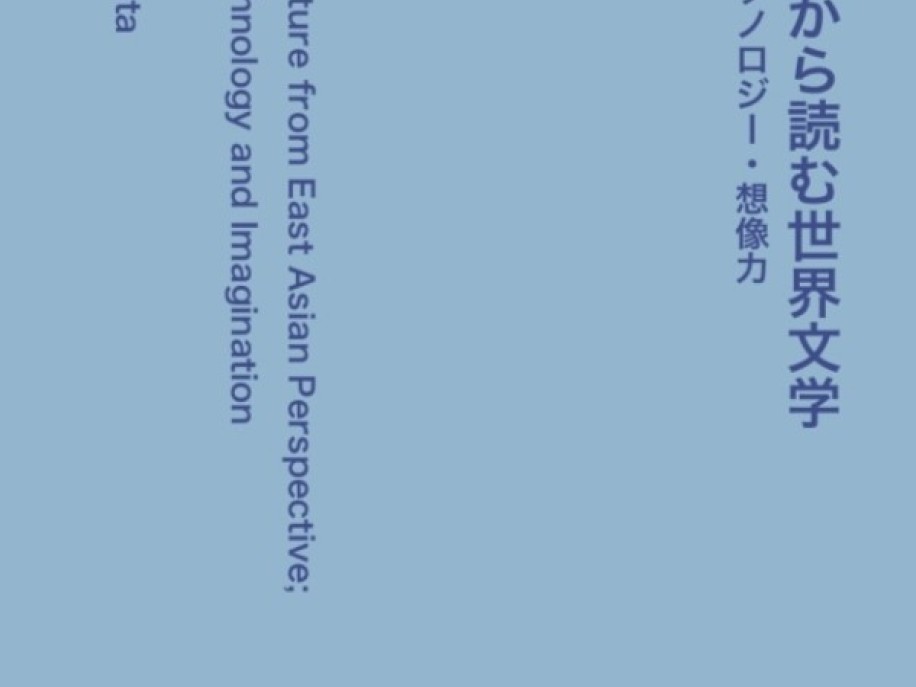書評
『冬将軍が来た夏』(白水社)
物語を運び去っていく言葉の霊力
この作家の言語を駆使する能力には脱帽した。語りの輝きは一つ一つの細部描写から放射され、漂流する言語の鉱脈にまだこれほどの宝物が埋もれているのかと、驚嘆するばかりである。主人公の「私」は幼稚園の先生をしている若い女性。ある日、勤務先の食事会で酔っ払い、園長の放蕩(ほうとう)息子は自宅に送り帰す隙(すき)をついて、彼女に性的暴行を加えた。園長先生は金に物を言わせ、示談に持ち込もうとする。そんな中、暴行事件が起きた三日前に、亡くなったはずの「私」の祖母が戻ってきた。憤慨した祖母は孫娘を連れ出し、法廷での徹底抗戦を誓う。
祖母は五人の老女たちと一匹の老犬と集団生活をしている。その仲間たちにいきなり飛び込んだ現代っ子の「私」はとんでもない世界を目撃するはめになる。祖母も含め、六人とも個性の強烈な女性で、現代社会からはじき出された者たちばかりである。共通しているのはみな苦難の過去を背負い、波静かな港のはずの家庭からも追われている。否、妻や主婦や母といった社会から押し付けられた役目から逃げ出したというべきかもしれない。目もあてられない暮らしをしているように見えるが、彼女らは決して自分たちのことを惨めとは思っていない。物質的には多少不自由でも、生きる希望は失われていない。むしろ、持ち前の楽天主義で、その日その日を楽しんでいる。自身も傷付けられた弱者ながら、みな心が海のように広い。自分よりも弱い者をかばい、命を張ってでも助けようとする。
彼女らの精神生活を支えているのは、アマチュアの演劇活動である。日常は行き当たりばったりで、生きるための日銭を稼ぐためには、法すれすれのこともあえてする。それだけで十分に演劇的だが、彼女らがやくざの商売に接近したとたん、物語は一転してドタバタ騒ぎになる。舞台の時間が進むにつれ、徐々に大人の童話の相貌を見せてくる。
この小説から「ふつう」の物語展開を期待するならば、肩透かしを喰(く)わされるであろう。暴行事件の裁判の行方や老女たちのさすらいの結末などはどうでもよい。意図的な省略は翻弄(ほんろう)される宿命を暗示し、あるいは世界の無意味を象徴させるための布置ではない。問われるのは現代文明の外側から何が見えるか、責任のある死のためにはどう生きるべきかである。
物語の展開は奇想天外というより、むしろ荒唐無稽(むけい)といえる。だが、小説的誇張は文体の虚飾ではない。この作品には「マジック・リアリズム」という用語は陳腐であろう。というより、あらゆる観念的な批評用語は軽すぎて、みな朝露のようにたちまち蒸発してしまう。
血縁や家族、女と男、意志と情念などが重層的に絡み合う様相は独特の言語運動を通して示されている。この長編のオリジナリティーは、小説という様式しか表現できない世界を言語芸術の名に相応(ふさわ)しい位相を通して示したところにある。そこには、土俗的な信仰があり、客家(はっか)の呪術的な伝承があり、少女的な空想の世界がある。そして、その説話的な空間をやさしく包み込んだのは、湧いて出るような豊かな言語の想像力であり、たくみに挿入された台湾閩南語(びんなん)語に秘められている霊力である。
物語はあてどもなく旅をしている。言葉が先導して、物語を運び去っていく。いとも軽く、まるでひとしきり吹いてきた風のように。十九世紀小説はついにできなかったことをこの作家は簡単にやってのけた。あたかも無邪気な少年が凧(たこ)揚げでもしたかのように。果たして次作はどう展開するのか。その手並みは楽しみである。
ALL REVIEWSをフォローする