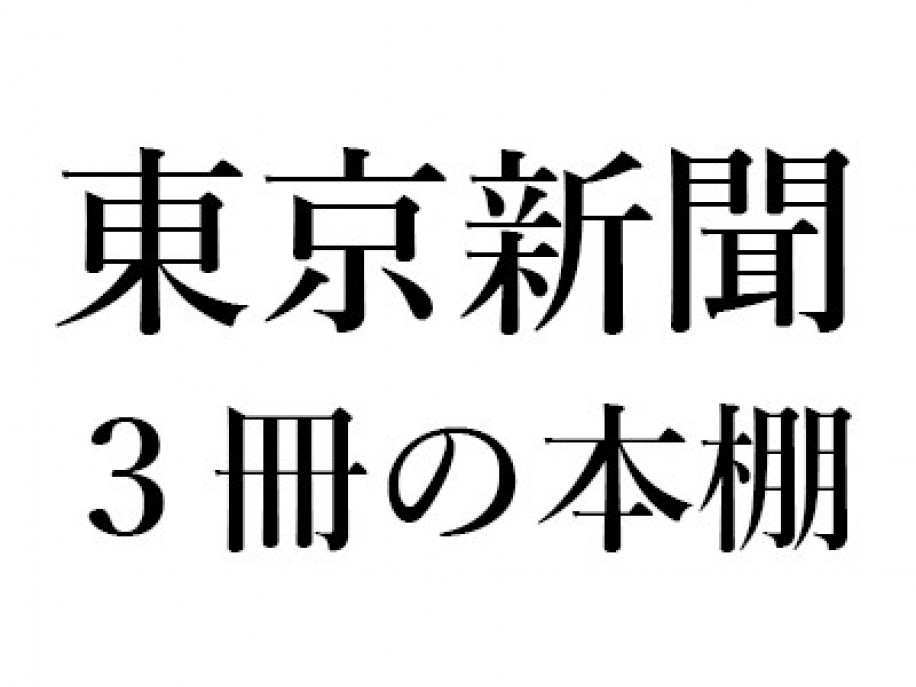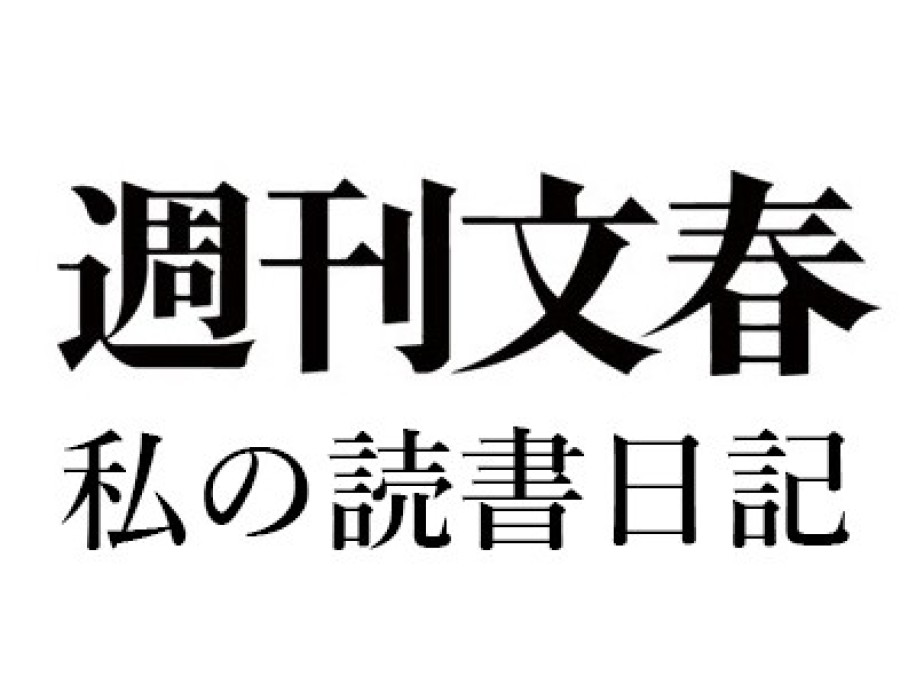書評
『カヨと私』(本の雑誌社)
近づこうとすると離れ離れると近づいてくる
どんなに長いこと一緒にいる人でも、その所作を見て、「えっ、そうか、そういうことだったのか」と嬉しくなったり腹立たしくなったりする。発見がある、と言うと何だか優等生っぽい表現でイヤなのだが、こちらもあちらも変化しているから、いつだって慣れはしない。では、ヤギの場合はどうか。小豆島でヤギと暮らす様子を綴(つづ)った本作では、嬉しくなったり腹立たしくなったりする感情が、とにかく気持ち良く弾けている。ヤギの名前はカヨ。カヨと私だけだった時は、「カヨの中には人間が入っているんじゃないだろうか」と言いたくなるほど。「私のことを見透かすような表情を浮かべること」さえあった。
「私は私で、どんどんヤギの成分が身体の中に入って」くるような状態に至るが、カヨが妊娠・出産し、ヤギが増えていくと、そうもいかなくなる。カヨは「交配を境にどんどんヤギの世界に戻っていき、むしろ私がヤギの世界に引きずりこまれていった」のだった。
動物の所作って、どうしてそういうことをするのか、そんなにはわからない。そんな気がすると予測し、そうではないと拒否されると、ならばこれはどうかと次の手を打つ。意思疎通できるようになったと思ったら、そんなものは勘違いだと切り離してくる。近づこうとすると離れ、離れると近づいてくる。
ヤギに向けられる視線が常に温かい。ずっと温かいけれど、その温度には波がある。どうしてこうなってしまったのかと悩んでいると、あたかも人間のように空気を読んだヤギが、できるかぎり迷惑のかからないヤギであろうとする。
著者とヤギが互いに惹(ひ)かれ合っている。でも、惹かれ方が微妙に異なる。結ばれてくれよと、真剣に見守ってしまった。
ALL REVIEWSをフォローする