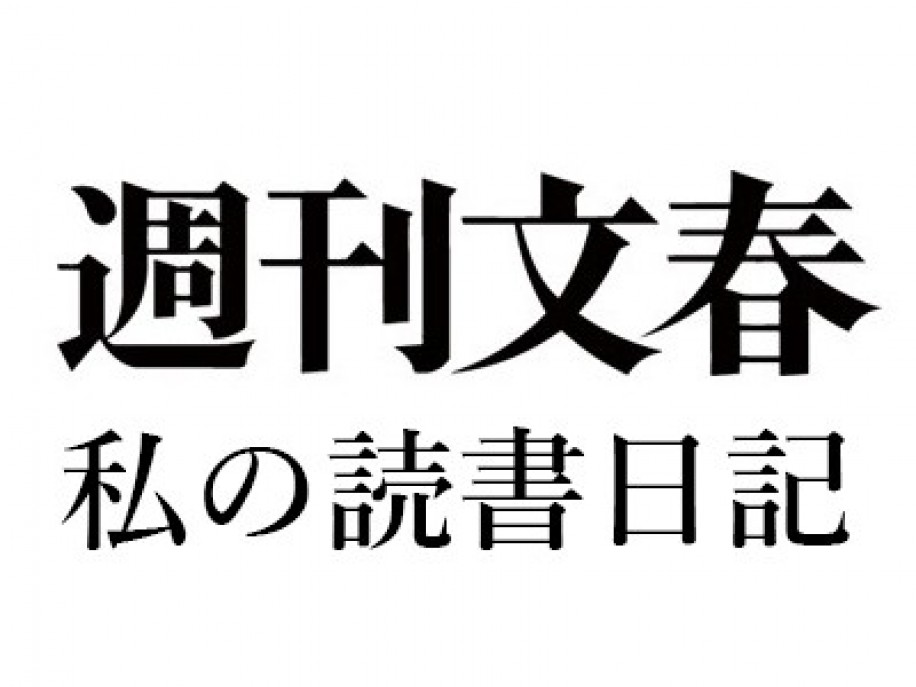読書日記
鹿島茂「私の読書日記」2016年12月1日号『あらゆる文士は娼婦である 19世紀フランスの出版人と作家たち』『パリはわが町』『全裸監督 村西とおる伝』
週刊文春「私の読書日記」
×月×日
来年開催予定の「十九世紀パリ時間旅行展」(仮)と「フランス絵本展」(仮)の不足資料収集のためにパリへ。バスチーユ広場で開催中の「古書・紙物市」が狙いである。機中、石橋正孝・倉方健作『あらゆる文士は娼婦である 19世紀フランスの出版人と作家たち』(白水社 2400円+税)を読む。出版人と作家の関係を探りつつ出版の本質に至るというのが共通するテーマだが、語り口が巧みなので一般読者が読んでも十分おもしろい。まず、前半を担当した石橋正孝が取り上げるのがラクロワ・ヴェルブックホーヴェン書店。聞き馴れない名前だが、ユゴーが『レ・ミゼラブル』の原稿に吹っかけた三十万フラン(約三億円)という契約金にもひるむことなく独占出版権を獲得したベルギーの出版社である。じつは、独占出版権獲得競争、大変な逆転劇で、下馬評では亡命中のユゴーの出版エージェントだったエッツェルが独占出版権を得るものと(当人を含めて)全員が信じていたのだが、エッツェルが資金調達に手間取っている間に、出版社を立ち上げたばかりのベルギー人・ラクロワが「胆力」で契約を締結、独占販売権を掻っ攫ったのである。
公私両面でユゴーに尽くしてきた(ただし、利益も得ていた)エッツェルにとって大打撃だったが、しかし、著者はここに、作家中心型から編集者主導型へと転換してゆく出版人エッツェルの変容を見る。それには亡命者の巣窟であると同時に海賊版出版の拠点だったベルギーがフランスに対してもっていた独特のポジションが影響していたのである。
「六一年十月に『レ・ミゼラブル』を取り逃がしたこと、そのほぼ一年後にジュール・ヴェルヌを発見したことがこの転換を後押しした。この二つの出来事それぞれの重みは、それらが起きた時点では、第二の成功より第一の失敗の方が圧倒的に大きかったはずだ。(中略)だが結局のところ、『危険人物』ユゴーとパリの大出版社の間を取り持つという出版方式は、エッツェルが亡命先のベルギーにいればこそ可能となっていたにすぎない。当人は自覚していなかったのだろうが、彼が帰国したことでベルギーにおける彼のポジションが実は空いていたのであり、ラクロワはそこにうまく嵌まったのである」
ところで『レ・ミゼラブル』の初版売り出しについては、「?」で問い合わせたユゴーに対し、出版者が「!」という返事で答えたという「世界一短い手紙」の逸話が有名だが、著者はあらゆる可能性を吟味したあげく、逸話の流布は英語圏に止まっていた事実を突き止め、「真の意味で小咄となるには、もとの文脈を離脱する必要があった」と結論づける。しかし、それにしてもよくできた逸話である。
では、十九世紀後半の出版界で覇者となった作家は誰かといえば「ルーゴン=マッカール叢書」のゾラをおいてほかにない。アシェット書店で広告主任をつとめていたゾラは「名のある作家でなければ本を出してもらえないが、名を得るには本を出さなければならない」というダブルバインドを抜け出す方法を考え出す。すなわち、最初の本をとにかく出してしまえば、宣伝でどうにでもなるのだから、印刷費相当額の宣伝広告費を自己負担すればいいのだと考え、この条件で処女作『ニノンへのコント』を「エッツェル・ラクロワ叢書」から出版することに成功する。次いで、マスコミの非難をあらかじめ織り込んだ「炎上商法」によって『テレーズ・ラカン』を売り出し、シャルパンティエ書店やマルポン・フラマリオン書店といった大量印刷・大量販売の出版社から「ルーゴン=マッカール叢書」を刊行するまでになる。出版の近代化路線の元祖が広告代理店的発想を身につけたゾラだったというのが秀逸。
こうした近代的な行き方に対し、十九世紀後半に作家性の擁護を謳ったのがルメール書店とヴァニエ書店。いずれも文学史に残る代表的な詩の「良心的出版社」である。著者の倉方健作によると、詩人に経費を全額負担させる自費出版でリスク回避に努めたという点で両社は軌を一にするが、大きな違いもあった。一つは自費出版経費の違い。ルメール書店が瀟洒で高級な造本で詩人の自負心を満たしたのに対し、ヴァニエ書店は費用が安く済んだため、ジュール・ラフォルグ、ランボー、コルビエールといった「夭折の詩人」によって版元に選ばれるという光栄に浴する。言い換えると、出版経費の安さがヴァニエ書店の名を文学史に刻んだのである。また、どちらの出版社も詩人たちの溜まり場となり、かたや高踏派の、かたや象徴派の拠点となったという点では似ているが、ルメール書店がアカデミー会員となる詩人を輩出したのに対し、ヴァニエ書店はヴェルレーヌとマラルメという大物を除くと、結局、後世に残るような詩人を生み出さなかった。
「ヴァニエ書店に集った若い世代は、マラルメとヴェルレーヌを尊敬し、その謦咳に接しながら、誰ひとりとして『師』に匹敵する作品を残すことがなかった」
さらに、ルメール書店が搾取にもかかわらず寄稿した詩人たちから感謝されたのに対し、ヴァニエ書店は最後までヴェルレーヌの面倒を見たのに、結局「ヴェルレーヌを殺した男」という悪評をこうむっただけに終わる。集合写真などで「一人おいて〇〇」と「一人おかれる」ことが多い編集者の出版人としての苦悩と逞しいサバイバル精神を描き出した好著である。
×月×日
パリのホテルで読み始めたのはロジェ・グルニエ『パリはわが町』(宮下志朗訳 みすず書房 3700円+税)。今年九十七歳のグルニエが最新作として世に送り出したのはパリの通りと番地にまつわる記憶を辿りながら、作家や詩人たちの思い出を綴ってゆく「地理感覚」の試み。記憶に残るパリの通りが時系列で喚起されてゆく。中心となるのはレジスタンスに加わり、ナチと戦った思い出だが、有名作家の名前も多く登場する。「ムフタール通り わたしはムフタール通りの空き地であった小規模なノミの市で、地面にころがっていた『異邦人』を、すでに見つけていた。ドサンティに聞いてみた。『このカミュとはだれなんですか?』と。『フランスの解放後に備えて、新聞発刊の準備をしている男なんだ』と彼は答えた」。後にグルニエは、レオミュール通りの建物で《リベルテ》誌の記者として働いたとき、《コンバ》紙の編集主幹となっていたカミュと知り合い、彼の部下となる。「フェート広場 パリに住んでいれば、自分が知って、好きになり、そして失われてしまったものを探して、人生を過ごすことができる」。×月×日
もしバルザックがタイムマシンで二十世紀末の日本に現れたとしたら、案外、アダルトビデオの監督になっていたかもしれない。あるいは、主人公をこの職業に設定していたかもしれない。本橋信宏『全裸監督 村西とおる伝』(太田出版 2400円+税)を読むとこの仮想がリアリティをもって感じられてくる。極貧家庭に育ち、グロリア版『エンサイクロペディア』のセールスマンになることで応酬話法の技術を身につけた野心満々の青年・草野博美は英会話学校、テレビゲーム販売会社などの経営者を経て「ビニ本」「裏本」の流通販売網「北大神田書店」を一人で立ち上げて巨万の富を築くが、逮捕されて挫折。その後AV監督に転ずるや、村西とおるという名で黒木香を売り出し一躍時の人となるがバブル崩壊で五十億円の借金を抱え込む。ここまでは同じ著者の『裏本時代』『AV時代』でお馴染みだが、本書では村西とおるという人物の「器の大きさ」が一段とクローズアップされて、とてつもなく面白い伝記に仕上がっている。取材をやりなおして関係者に徹底インタビューしているので、AV内幕史の決定版としても読むことができる。傑作である。ALL REVIEWSをフォローする