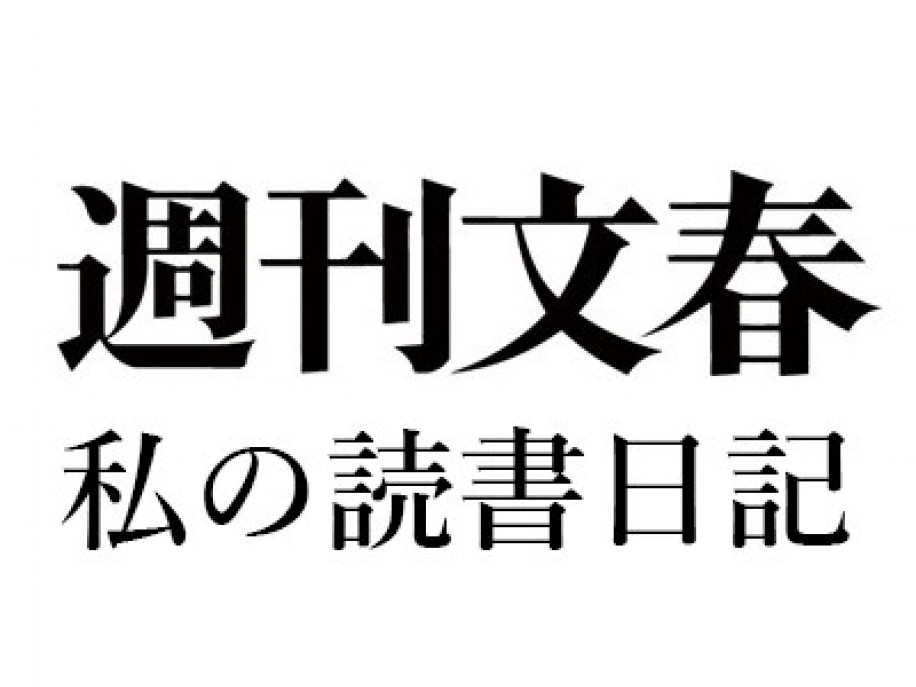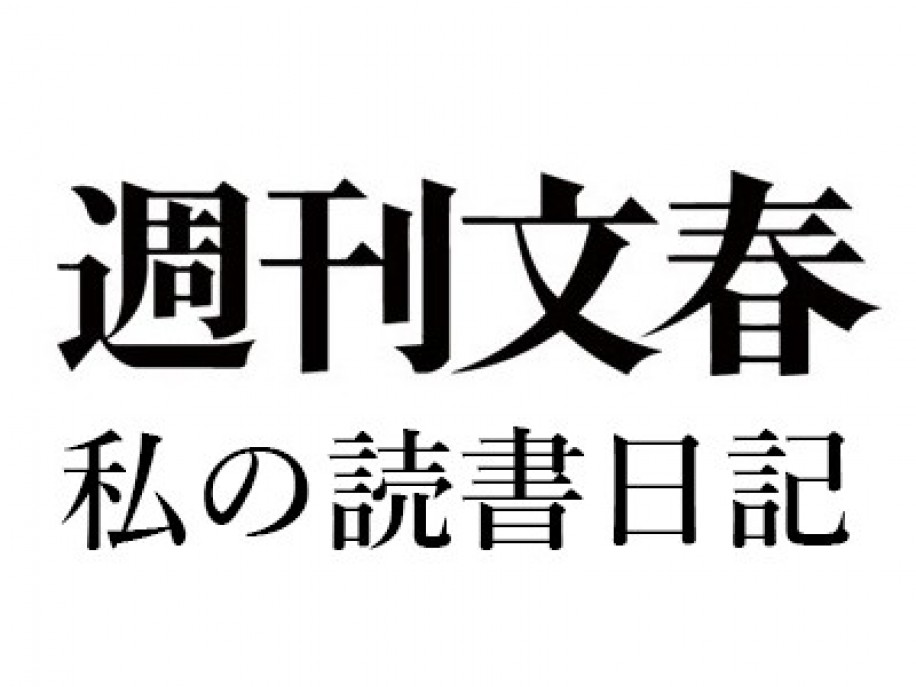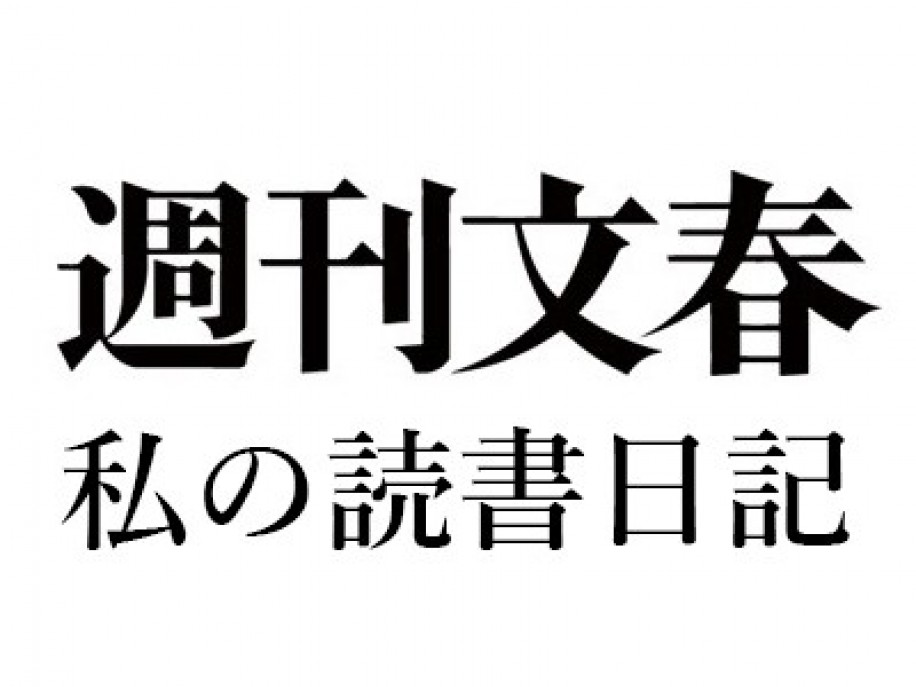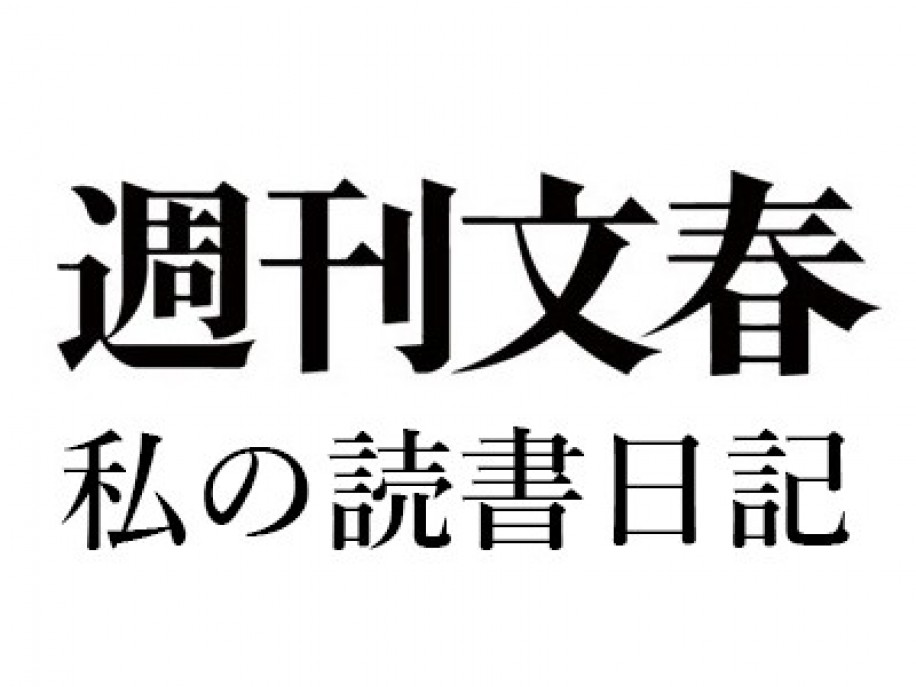読書日記
鹿島茂「私の読書日記」- 週刊文春2018年3月29日号 - 村西とおる『禁断の説得術 応酬話法』(祥伝社)、玉村豊男『からだの履歴書』(世界文化社)、小栗左多里&トニー・ラズロ『ダーリンの東京散歩』(小学館)
週刊文春「私の読書日記」
×月×日
学者や文学者には具体から観念に行く人と、観念から具体に行く人の二種類がある。私はどうやら前者のようで、この年になってようやく哲学や思想の面白さがわかってきた。最近ではどんなに難解な哲学書でも怖くない。では哲学者の中で一番凄いことを言ったのはだれかというと、それはパスカルだと思う。人間の営為(生きがいのある労働や創造行為も含めて)はすべて気晴らしにすぎないが、その気晴らしも人から承認してもらわない限り生きる理由にならないと断定したのだから。
この意味で、村西とおる『禁断の説得術 応酬話法 ――「ノー」と言わせないテクニック』(祥伝社新書 800円+税)はそのノーハウ本的なタイトルにもかかわらず意外に哲学的な本だ。著者は周知のとおり、英語百科事典のトップセールスマンを皮切りに、英会話学校経営、テレビゲーム・リース業、ビニ本・裏本の制作販売、アダルト・ビデオの制作・監督・主演というように、成功と失敗のジェット・コースター人生の末に巨万の富を築いたが、衛星放送の投資に失敗、五〇億円の借金を抱え込んで自殺(他殺?)の寸前まで行ったが、持ち前の情熱で借金を全額返済、いまや、七転び八起き的な人生の語り部として全国で引っ張りだこになっている。本書はそんな著者が百科事典セールスマン時代に叩き込まれたアメリカ式応酬話法を惜し気なく披露したもので、AV出演への説得ばかりか、五〇〇〇万円の借金返済を迫って投身自殺を強要した不動産業者を応酬話法で説得して生還する話や、北海道の原野で行き倒れ寸前にたどりついた食堂の老女に英会話教材を売り付けるなど凄いエピソードが繰り出されていて、これはこれで読み所満載だが、しかし本書の勘所は次のような間接否定話法についての考察である。
性欲や食欲や睡眠欲には、限界があります。ある程度満たされれば満足し、それ以上求めることがありません。しかし、自己承認欲求には限りがありません。限界を超えて『もっと、もっと』と、とどまるところを知りません。営業マンは、このような人間の心の底に横たわる強い自己承認欲求を理解し、お客さまと接することが求められます。(中略)お客さまの断わり文句を聞いたら、最初に発する言葉は『おっしゃる通りです』『なるほど、そうなんですか』『ご意見はよくわかります』と、お客さまの言葉を肯定することから話を組み立てることを徹底してください。お客さまの自己承認欲求を、〝言葉のマッサージ〟で心地よく刺激するのです。俗に、貧乏人とは多くを持たざる者ではなく多くを欲する者である、と言いますが、その意味では、誰もが常に自己承認欲求に飢えているのです
人間、突き抜けると哲学者になる、の典型だろう。
×月×日
人間のすべての営為は気晴らしにすぎないが、やるんだったら徹底的にやらないとその気晴らしさえ快楽にならない人がいる。フーリエはこれを「熱狂情念」と呼んだが、フーリエは三大情念の一つとして「移り気情念」というのも挙げている。熱狂しだすと集中力はもの凄いが、ある瞬間に憑き物が落ちたように熱狂が冷め、新しい熱中対象を求め始めるという人である。玉村豊男『からだの履歴書 病気自慢』(世界文化社 1300円+税)は、熱狂情念の人であると同時に移り気情念の人でもある著者が、病気さえも熱中の対象にしてしまう様を描いた病気・健康エッセイ。
著者は数え年四二歳の厄年に大吐血する。「交通事故は別にして、吐血するまでは病気とはほぼ無縁の生活を送ってきた私にとって、思えばこれが『病気自慢』人生のはじまりでした」。吐血に加えて下血もひどくなり、輸血を繰り返すうちに輸血後肝炎に感染、慢性化する。動くと疲れるので気晴らしを求めた結果、油絵とワインつくりに熱中、農作業に打ち込んだおかげで肝機能も回復する。しかし、パリでの取材中に食べたマンゴーと酒でアレルギーを発症し、帰国後に受けた診断で血糖値が五七七に急上昇。糖尿病を発症し、インシュリンが欠かせなくなる。入院中に痛風発作にも見舞われる。以後、肝炎と糖尿病を抱えながら、ワイン農園ヴィラデストを経営するかたわら、サプリメント、ダイエット、筋トレ、ジョギングに熱中するという生活を続けるが、やり始めると猛烈に勉強するという態度はどんな場合も同じである。
立ち眩みがするのは、かならず食事を済ませてから少し時間が経った頃でした。(中略)私は看護師に頼んで医師からその[ヘモグロビンの]データをもらい、自分のノートに書き写していました。(中略)食事の数時間後に採血したときのヘモグロビン量が、食事前に採血したときより明らかに減っているのです(吐血で最初に入院したとき)
それ[定時の血糖値測定]以外にも、食後三十分、一時間、一時間半……と三十分刻みで測定して、一日の血糖値の変化と食事内容の関係などを記録したのです。(中略)私は退院後も、即効性インシュリンを毎食前に打ちながら、数値の変化を克明に追い、そのデータにもとづいて、毎回打つインシュリンの量を調整していきました(糖尿病で入院したとき)
ダイエット、筋トレ、ジョギングなどでも勉強癖は遺憾なく発揮されて、専門書まで読みこなす。
新しい病気にかかったときは、少し難しそうな医学書まで買って読んでみます。書いてあることの半分以上がちんぷんかんぷんでも、よく探せば一般の患者に役立ちそうな情報も隅のほうに隠れているものです
ところが、肝炎発症二十九年目にして新薬のお陰で肝炎は完治。大喜びしたのもつかの間、完治からほぼ一年後に肝臓ガンが発見される。新薬で免疫系に異変が生じたのだ。こうして入院手術となったが、やがて入退院を繰り返すうちに、入院鞄に入れるべき必需品のリストを熱中して考えたり、遺言の書き方や葬式の段取りから散骨の場所までさまざまに思案する。
病気でも健康維持でも、徹底的に調べ、考え、研究する。この究極の「気晴らし」さえあれば、どんな病気でもケガでも怖くないのである。熱狂情念、移り気情念に乾杯!
×月×日
以前、青山骨董通りのスターバックスのテラスでコーヒーを飲んでいるとき、突然、髭面の外国人に「昨日、テレビに出てましたよね」と日本語で話しかけられた。見ると、どこかで見覚えのある顔。「あっ、ダーリンさん!」。そう小栗左多里&トニー・ラズロ『ダーリンは外国人』のトニー・ラズロさんだったのである。初対面にもかかわらずおおいに話が盛り上がり、私は青山・赤坂・麻布という高級地域が「陸軍→GHQ→テレビ局」という変遷によって今のような土地柄になったことなど蘊蓄を傾けた。そのご夫妻の最新刊が『ダーリンの東京散歩 歩く世界』(小学館 1000円+税)だから、これは読まずにはいられない。タイトル通りの浅草から都庁までの漫画(小栗)と文章(ラズロ)によるブラタモリ風東京体験散歩だが、私のような何でも屋にとっては言語学者であるラズロさんの多文化共生的な語源講釈が楽しい。たとえば浅草雷門では「龍=ドラゴンって言われてるけどもともとは違うものだね。むしろ逆」とネームがあり、聖なる龍に対峙する悪なるドラゴンの絵が掲げられている。あるいは銀座「千疋屋」でのフルーツポンチを巡る会話。「『ポンチ』はサンスクリット語で『5』って意味だよ。お酒やスパイスなど5種類のものを混ぜて作ったのが始まりとされる」。オランダ語ではこれが「ポンス」となり、日本語のポン酢の語源となる。ことほどさように、日本語というのは多文化共生の言語なのであり、東京もまた然りなのである。
ALL REVIEWSをフォローする