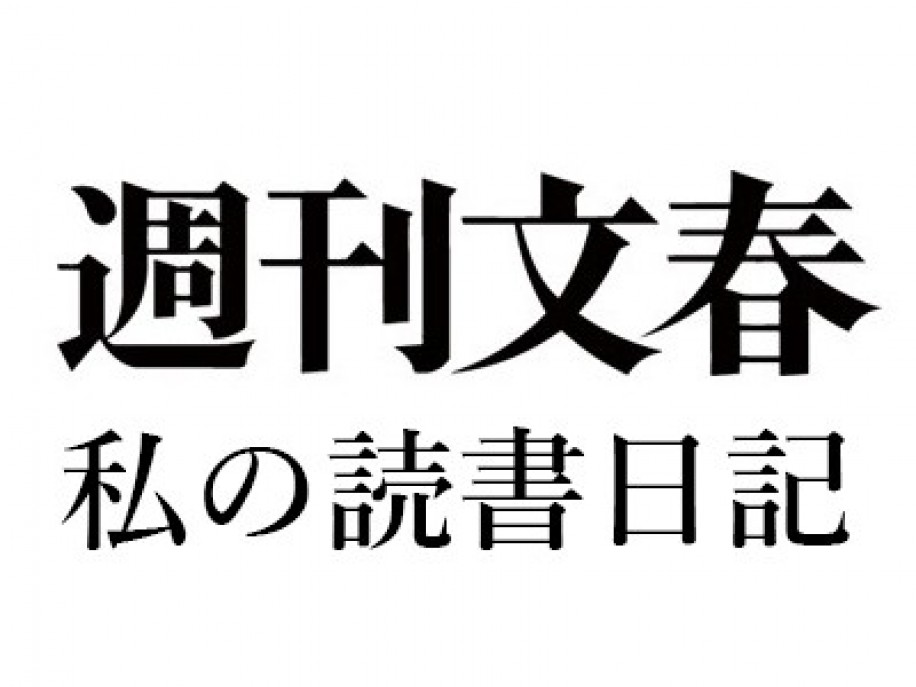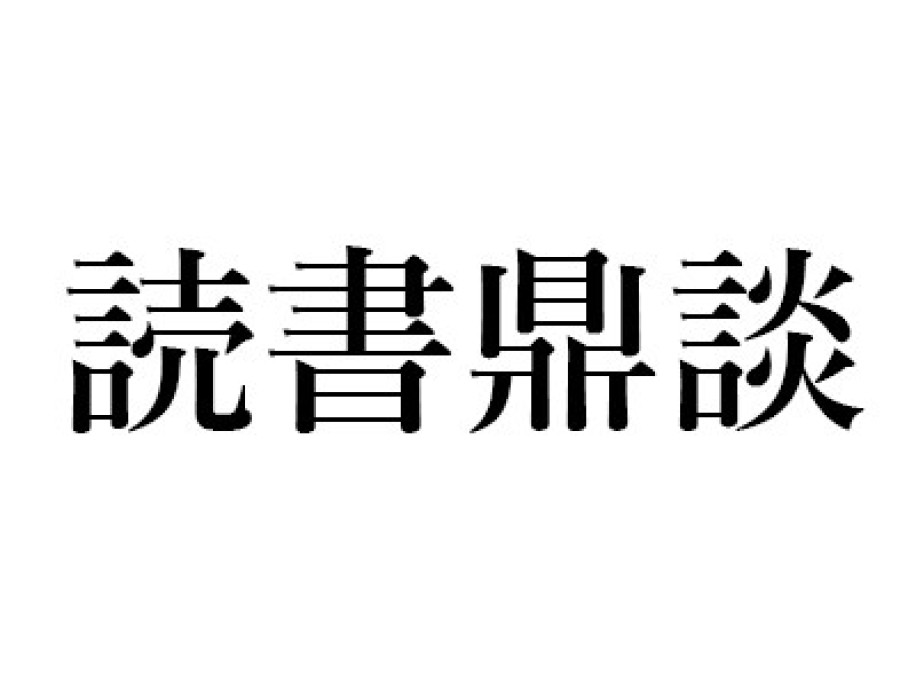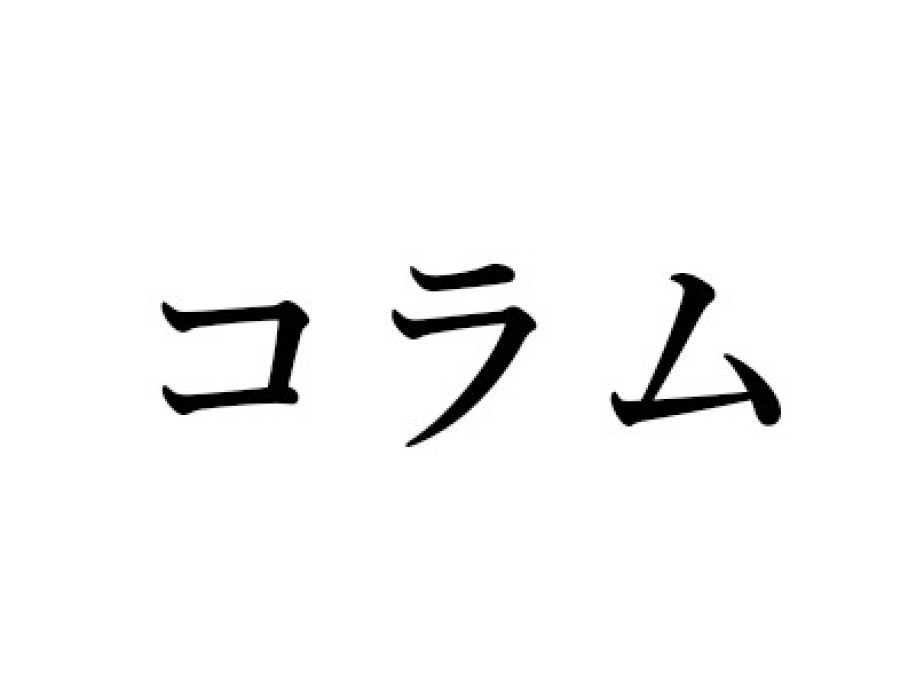書評
『回転スシ世界一周』(光文社)
スシ、寿司、SUSHI
旅の出発点はひらめきだ。この本を読むと実感する。海外で回転スシの店が続々オープン。新聞の面白ネタとして読み過ごしそうな記事に、著者の中の何かがピンと反応した。日本の食文化が広く世界に受容される、歴史的転換点にあるのでは。そうだ、こうしちゃいられない!
玉村豊男著『回転スシ世界一周』(世界文化社)は、パリにはじまり、ロンドン、アムステルダム、ニューヨーク、ロサンゼルスと、めまぐるしく回った報告だ。十六日間の旅と帯にある。
「ふつうなら、ちょっとおおげさでも、何か月、いや何年がかりの取材、とうたいたいところでは」
と首を傾げたが、読んでわかった。そんなのんびりしたことを許さないほど、世界のスシ・シーンは急速に変わっている。
日本人による日本人相手の店を想像すれば、さにあらず。客の多くは、現地のちょっとおしゃれな層だ。オーナー、シェフも、日本人でないケースがほとんど。若き起業家たちである。
アムステルダムで「ステレオ・スシ」をはじめたのは、コンピューター技術者と広告会社の元同僚。握り方は、インターネットで(!)学んだとか。
カリフォルニアロール発祥の地ロスでは、パフォーマンス・スシが大人気。ハッピ姿の職人(こちらは日本人)が握って踊って、ショータイムには客も全員参加する。アメリカ人の「スシをとことん楽しむそのエネルギーに圧倒された」と著者。旅が進むにつれ、常識は次々くつがえされていく。
われわれは、よその食べ物を何でも取り入れる、めずらしい民族と、自分たちのことを考えてきた。料理や食文化はふつう、戦争や植民地化といった関係を通さぬ限り、簡単には伝播しないものと。が、どうやらそれは違うらしい。
外国旅行や情報交換が、自由にできるようになると、どの国の人も、似たような好奇心を持つのである。地球のあちこちでスシが愛されている光景は、平和と技術革新の象徴だ。
スシが受け入れられるには、魚を食べる習慣のあるなしは、関係ない。新しい文化情報にアンテナを張る人たちが多いところで、流行る。著者いわく、スシは「頭」で食うものなのだ。
思えば、ファーストフードとしての握りズシを生んだ、十八世紀後半の江戸は、百万都市だった。外食の需要は大きく、一定の知的レベルにある市民が、均質な情報を共有できる社会でもあった。この特徴、現代の世界の大都市に通じている。
なるほど、江戸ってそういう町だったか。スシとはそういう食べ物なのか。四か国五都市に江戸を加えて、すべてがひとつの輪につながった。スシを再発見した世界一周なのだった。
【単行本】
【この書評が収録されている書籍】
週刊文春 2000年8月10日号
昭和34年(1959年)創刊の総合週刊誌「週刊文春」の紹介サイトです。最新号やバックナンバーから、いくつか記事を掲載していきます。各号の目次や定期購読のご案内も掲載しています。
ALL REVIEWSをフォローする