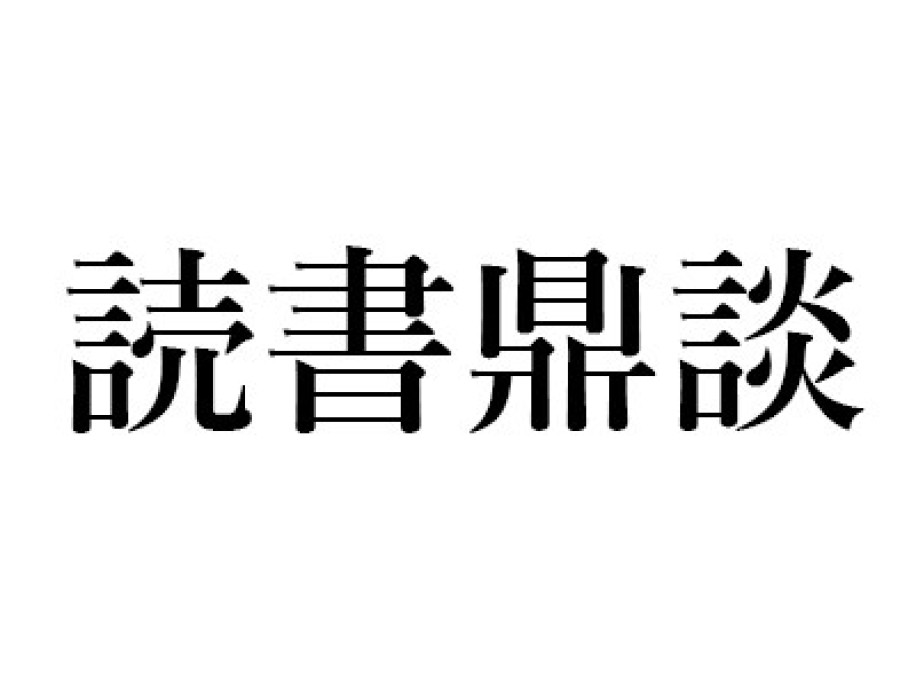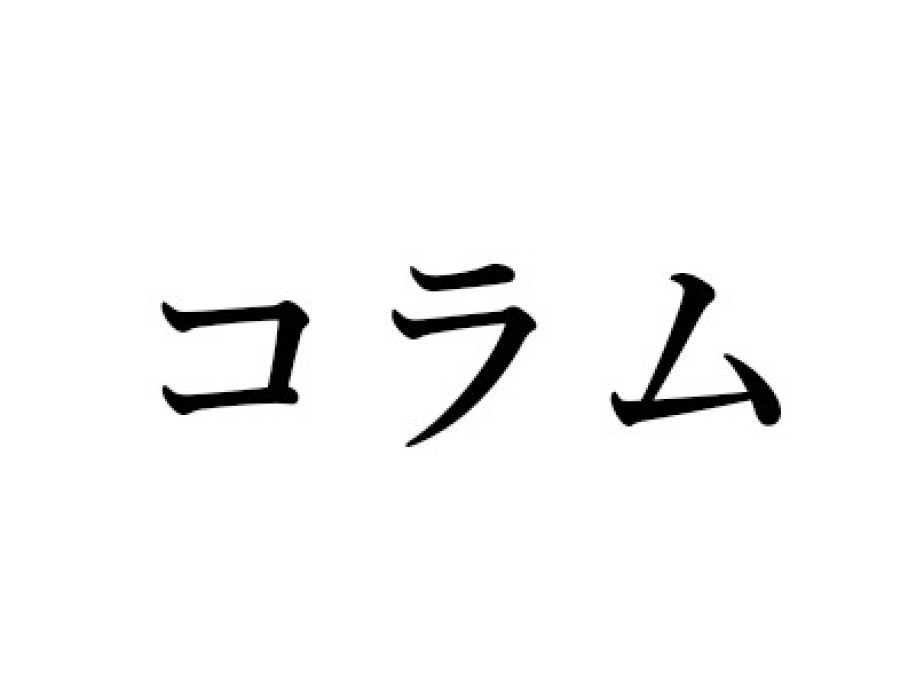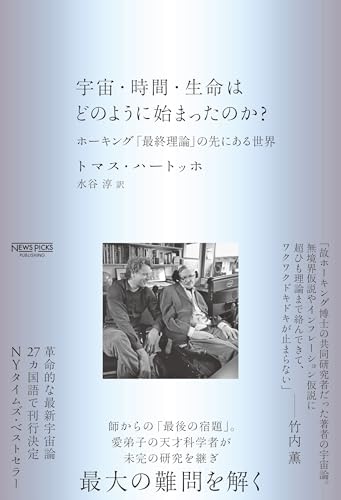書評
『日本人の愛したお菓子たち 明治から現代へ』(講談社)
「洋菓子」が本格的に入ってきた幕末・明治から現在まで、その時代を象徴するお菓子とそれにまつわるエピソードが並ぶ。生菓子・焼き菓子を扱おうとしていたのにスナック菓子、駄菓子、キャラメル、アイスクリーム、パンにまで手が出てしまったとあるが、それが本書を楽しくしている。
最初に登場するのはシュークリーム、プディング、あんぱん、スイートポテトなど。日本人得意のアレンジを加え、今も愛されている品々だ。大正に入るとキャラメル、社会的インパクトとしては特大ホームランだとある。「おせんにキャラメル」という劇場の売り子の声が聞こえる。
昭和に入り戦争の時代は甘いものが消えていく。戦後復活の始まりもキャラメルで、昭和21年に紅梅製菓とカバヤ食品が創業と知ると、巨人軍選手のブロマイドの入った紅梅キャラメルの人気が思い出される。
その後登場するお菓子の写真が次々現れ、クリスマスやバレンタインデーを思い出し、若い頃の友だちの顔、更に時が進むと子どもの友だちの顔が浮かんでくる。帯にある「お菓子は思い出の栞」は言い得て妙だ。
最初に登場するのはシュークリーム、プディング、あんぱん、スイートポテトなど。日本人得意のアレンジを加え、今も愛されている品々だ。大正に入るとキャラメル、社会的インパクトとしては特大ホームランだとある。「おせんにキャラメル」という劇場の売り子の声が聞こえる。
昭和に入り戦争の時代は甘いものが消えていく。戦後復活の始まりもキャラメルで、昭和21年に紅梅製菓とカバヤ食品が創業と知ると、巨人軍選手のブロマイドの入った紅梅キャラメルの人気が思い出される。
その後登場するお菓子の写真が次々現れ、クリスマスやバレンタインデーを思い出し、若い頃の友だちの顔、更に時が進むと子どもの友だちの顔が浮かんでくる。帯にある「お菓子は思い出の栞」は言い得て妙だ。
ALL REVIEWSをフォローする