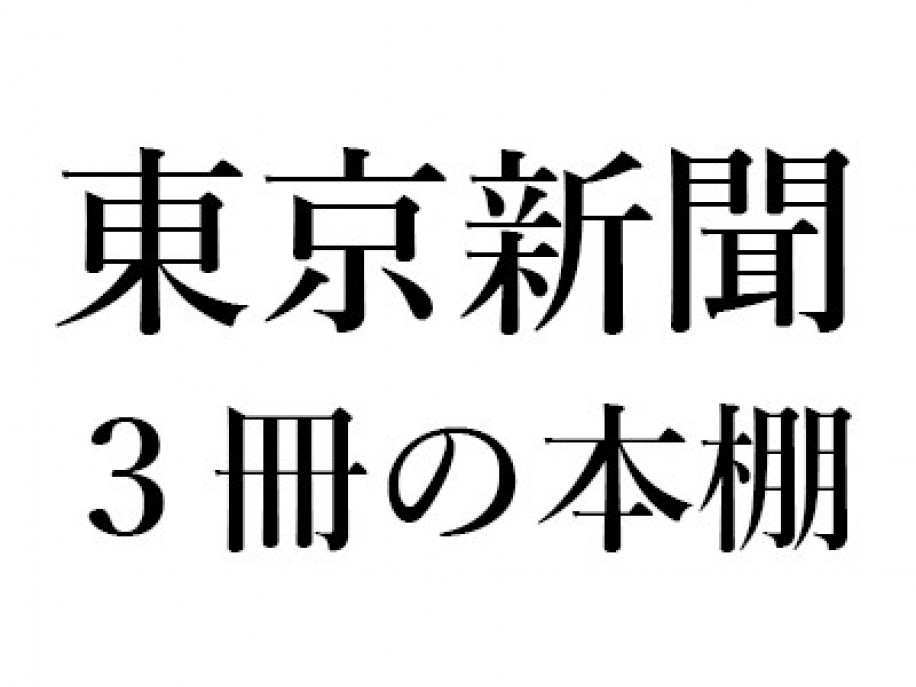書評
『ぼくの美術帖』(みすず書房)
出版不況と言われる中で、今年の春、うれしいことがあった。(事務局注:本書評執筆は2006年)
一九八二年(何ともう四半世紀近く前だ)にPARCO出版から出版された『ぼくの美術帖(ちょう)』が、みすず書房から新装で復活出版されたのだ。こんな時代でも、良書はちゃんと蘇(よみがえ)るものなのだった。
著者はイラストレーターの原田治さん。と言ったら、ある世代の女の人たちは「エッ、あのOSAMU GOODSの?」と驚くだろう。70年代末から80年代に少女だった人で、OSAMU GOODSを知らない人は、まずめったにいない。今の「かわいい」文化だって、ほんとうは原田さん抜きには語れないのだ。
原田さんにはOSAMU GOODSタイプの絵ばかりではなく、いくつかの異なった画風があり、サラリと洒脱(しゃだつ)な人物画やモダンアート的な抽象画なども私は好きだった。
そんな大人気イラストレーターとして活躍するいっぽう、自分の美意識のみなもとをじっくりと探って行く『ぼくの美術帖』を書きあげていたのだ。
当時読んで、私はビックリ。こんなにわくわくさせる美術評論の本は珍しいんじゃないかと思った。タイトル通り「ぼく」の「美術帖」なのがいい。徹底して原田治個人の好みに偏執して語られているのがいい。
ティツィアーノや俵屋宗達が出て来るかと思えば、木村荘八や鏑木清方が、そして宮田重雄や鈴木信太郎が出て来る。北園克衛のグラフィック・デザインやアーニー・ブッシュミラー(アメリカのコミック『ナンシー』の作者)まで、同様の愛着で語られている。
ジャンル分けは関係ないのだ。私はこの本で小村雪岱(せったい)を、川端実を、戦国時代の兜(かぶと)の美を知った。
ごく個人的な好みに偏執した結果、逆に個人を超えて、もっと広く大きな世界にたどりついているという感触もあった。古今東西の美術を貫く、いくつかの美意識の流れがつかめたような気がした。特に「美意識の源流」と題された縄文文化論。新しいみすず書房版で再読して、また唸(うな)った。
(事務局注:続編にあたる『ぼくの美術ノート』(亜紀書房)も発売中)
【この書評が収録されている書籍】
一九八二年(何ともう四半世紀近く前だ)にPARCO出版から出版された『ぼくの美術帖(ちょう)』が、みすず書房から新装で復活出版されたのだ。こんな時代でも、良書はちゃんと蘇(よみがえ)るものなのだった。
著者はイラストレーターの原田治さん。と言ったら、ある世代の女の人たちは「エッ、あのOSAMU GOODSの?」と驚くだろう。70年代末から80年代に少女だった人で、OSAMU GOODSを知らない人は、まずめったにいない。今の「かわいい」文化だって、ほんとうは原田さん抜きには語れないのだ。
原田さんにはOSAMU GOODSタイプの絵ばかりではなく、いくつかの異なった画風があり、サラリと洒脱(しゃだつ)な人物画やモダンアート的な抽象画なども私は好きだった。
そんな大人気イラストレーターとして活躍するいっぽう、自分の美意識のみなもとをじっくりと探って行く『ぼくの美術帖』を書きあげていたのだ。
当時読んで、私はビックリ。こんなにわくわくさせる美術評論の本は珍しいんじゃないかと思った。タイトル通り「ぼく」の「美術帖」なのがいい。徹底して原田治個人の好みに偏執して語られているのがいい。
ティツィアーノや俵屋宗達が出て来るかと思えば、木村荘八や鏑木清方が、そして宮田重雄や鈴木信太郎が出て来る。北園克衛のグラフィック・デザインやアーニー・ブッシュミラー(アメリカのコミック『ナンシー』の作者)まで、同様の愛着で語られている。
ジャンル分けは関係ないのだ。私はこの本で小村雪岱(せったい)を、川端実を、戦国時代の兜(かぶと)の美を知った。
ごく個人的な好みに偏執した結果、逆に個人を超えて、もっと広く大きな世界にたどりついているという感触もあった。古今東西の美術を貫く、いくつかの美意識の流れがつかめたような気がした。特に「美意識の源流」と題された縄文文化論。新しいみすず書房版で再読して、また唸(うな)った。
(事務局注:続編にあたる『ぼくの美術ノート』(亜紀書房)も発売中)
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 2006年11月5日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする