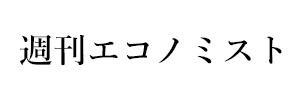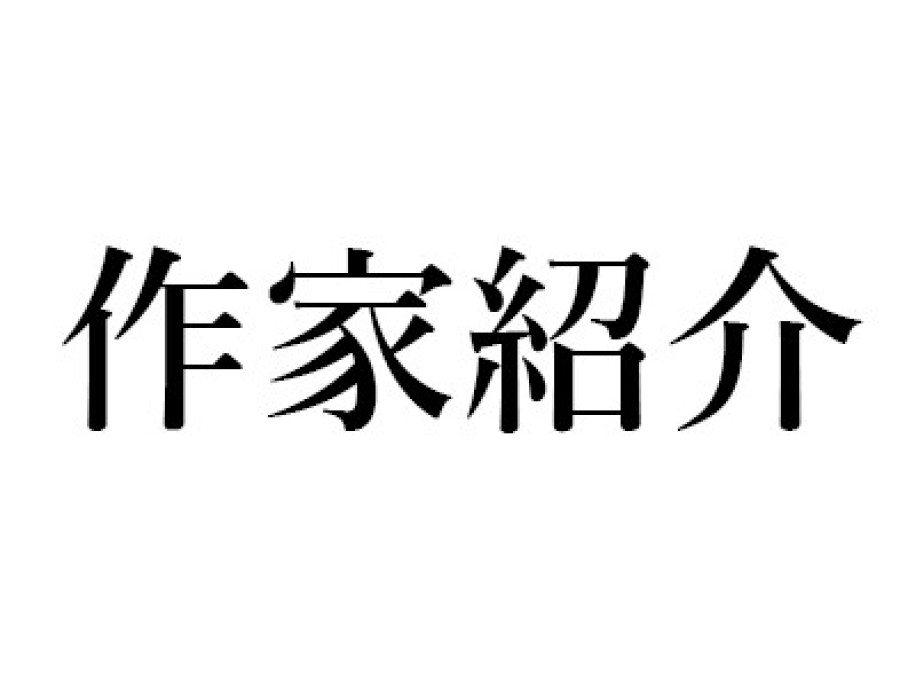書評
『試行錯誤に漂う』(みすず書房)
演奏家が試行錯誤しながら弾くように小説を書きたい
演歌というものはズクズクの情ばかりでおもしろみに欠け、またその独特の節も、泥臭くもっさりして、ファッショナブルでないから好きではない、と、ずっと感じていたが、よく聴くとそうでもないような気がしてきた。そこでさらに検証するため、覚束(おぼつか)ない技術で自らギターを弾き、森進一が1969年に飛ばしたヒット曲、「港町ブルース」を歌ってみたところ、実に楽しく心地よく、日に何度も、というのを具体的に言うと、日に40回くらい、これを歌っていたら周囲の者にまるでもの狂いのようだ、と言われた。そんなことでギターを弾いて歌ってばかりいたため読書があまりできなかったが、そんななか読む、保坂和志の随筆集『試行錯誤に漂う』(みすず書房、2700円)が極度におもしろい。この随筆集にはカフカのことが、そしてベケットがよく出てきて、書く、とはどういうことか、そして、作品に対してどういう立場で書くのか、ということが、頭の中で刻々と生まれ、明滅し、変化する考えをそのまま書き写すようにして書かれている。
それは自分のような小説家にとっては凡庸な表現で申し訳ない、目から鱗(うろこ)が落ちるような心持ちのする、衝撃的な考えであった。
どういうことかというと、小説家はどうやって小説を書いているのか、というとそれは人それぞれだろうが、ひとつだけ共通することがあるとすれば、それは小説の完成というか、達成というか、そういうものを目指して書いている、ということで、つまり、最初に、「まあ、大体こんな感じの小説にしたいな」というのがあって、それを目指して書き、うまくいくこともあれば、失敗することもあり、うまくいったときは達成感を感じるのであって、それがなになのかは本人にしかわからないが、その達成を目指して書いている。
ところが、本書によると、そりゃあ、そうかも知れぬが、そうした、予(あらかじ)め想定した達成に向けて、部分を組み立てて完成にいたるということは、元来、書く、という行為の本質から外れたこと、ということになる。
そしていま自分は、本質、と書いたが、その言い方には実はその書き方には自信がなくて、いや、自信がないというよりはここで本質と言えば保坂氏の言っていることとぜんぜん違うことになるような気がして、そこで、本質と言うよりは実質と書き変えるのだが云々(うんぬん)。
といった感じの文章は、ちょっと物真似(ものまね)をしてみたのだが、確かに達成を目指さず、いつまで経(た)っても続いて終わらないし、なによりも結論に向かっていかず、どんどん広がっていく。そうすると苛立(いらだ)って、「結局、どこに行きたいの」と言う人が出てくる。それに対しては、「どこにも行きたくねえよ。生きてぇだけだっつの」と答える。
演奏家の練習の意味
生きるというと、ライブという語を聯想(れんそう)するが、保坂氏は本書の中で音楽について何度も触れていて、例えばピアニストについても書いているが、これも驚きの内容で、ピアニストはなんのためにピアノを弾いているか、なにに向けてピアノを弾いているか、ということについて書いてある。右(事務局注:上)の小説家と同じように考えれば、本番に向けて弾いている、という風に考えられる。本番というのは、コンサートやレコーディングだが、そこで最高の演奏ができるように練習をするために弾いている、と考えられるのである。
けれども実際に弾いているときの魂の状態はそうではなく、その都度、曲に向き合い、ここを強く弾いたらどうなるだろうか、とか、ここを少しゆっくり弾いたらどうだろうか、といったことを一瞬の休みもなく考え・感じながら弾いている。
それこそが、その試行錯誤に漂う、ことこそが演奏家が楽器を弾くということであり、人が文を綴(つづ)るということではないのか、と保坂氏は書くのである。
それにいたって私は、ここに書かれる演奏家とは月とすっぽんであるが私が日に40回も「港町ブルース」を歌う理由が理解でき、そして書く場合も、願わくばこのようにして書きたいものだ、と思ったのであった。思ったのであった(谺)。
ALL REVIEWSをフォローする