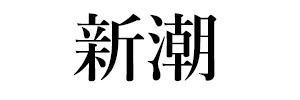書評
『死小説』(新潮社)
死によって途絶した意志の形
自分はいま生きているが、そのうえで、生きているということはどういうことだろうか、と考えてみたところ、あ、なるほど生きているということはこういうことだったのか、と、わかるためには、死んでみないとわからないのではないか、という考えにいたった。けれどもそのときはもう死んでいて、ということは当然、それをわかったりわからなかったりする脳も死んでいるので、死んだところで、やっぱりわからないのかもしれない。その途中で、生きているということは、一瞬たりともじっとしていないというか、なにかをしようとか、どこかへ向かおうとする意志が、その生きているものを動かすことかも知らん、とも考えた。
伊弉諾尊(いざなぎのみこと)は死んだ伊弉冉尊(いざなみのみこと)に会いたくて黄泉国(よもつくに)に行き、腐敗して蛆がたかったその姿を見てびびって逃げ、その際、伊弉諾尊は黄泉国とこの世の出入ロを大岩で塞いで。それ以来、黄泉国はこの世と隔てられるが、死が恐ろしいのは、そうして死んだら腐敗して蛆がたかる、その姿が恐ろしいからか、というと、マア、そうなのだろうけれども、別の言い方をすれば、死ぬと、その意志が向かおうとする方向とは逆の、または無関係の方向に、意に反して、というか、意がなくなって向かってしまうから、とも言えるのではないかと思う。
ということは、死にたくないと思うのは、どこへも向かえなくなる、または、どこかとんでもないところ、腐敗とかぢごくとか、へ向かってしまう、ということが恐ろしいからだと言えるが、けれども死んだということは、その意志がなくなるということで、したがって、どこかへ向かいたい、という気持ちは、その時点ではない訳だし、もっというといまの形での自分もなくなり、もしなにかが残ったとしても、それは別の形になっているだろうから、恐れることはなにもない、ということになる。
だったら別になんの問題もないはずなのにやはり気色の悪さが残るのはなぜだろうか。
やはり、伊弉諾尊が伊弉冉尊を見て恐れたような他人の死の死穢が気色が悪く、その気色の悪さを、あまりのことに頭がグラグラになって自分の死と混同して考えてしまうからだろうか。
しかし、そうならないために伊弉諾尊は黄泉国とこの世の出入ロを大岩で塞いで、その気色悪さを防止したのではなかったのか。
それは確かにそうなのだけれども、厳密に言うと、少し違っている部分があって、まず大岩で塞いだというと、この世のどこかに穴のようなものが開いていて、それを岩で塞いだようにフツー思うが、その穴はどれくらいの大きさだっただろうか。
私はそれは極度に大きかったのではないかと思う。どれくらい大きかったか。富士山の噴火ロくらい大きかったか。いや、もっと大きかった。琵琶湖くらい大きかったのか。いやもっと大きかった。大八洲、日本国にすっぽり被さるくらい大きかったのか。いやもっと大きかった。じゃあ、いったいどれくらい大きかったのか。それはこの世の中がすっぽりばまり込むくらいに大きかった、つまりこの現実の国は黄泉の国にすっぽりはまり込むような構造になっていたのである。なので大岩というと、全体的に球状のイメージがあるが、実際は石版のような平たいものであったと推測される。
ということは伊弉諾尊は考えられないくらい巨大な平たい岩を、ちょうど棺に蓋をするように、この世の全体に被せたということになり、まさに神業としか言えないが、しかし、それは岩であり、当時のことなので、ゴムパッキンなどもなく、表面の細かい凹凸による小さなすきまはかなりあったのではないか、と思われる。
そこから状態が変わってしまったものの意志がわずかだけれどもこの世に洩れ続け、それがこの世のあちこちで割とあからさまに展示されているから、私たちは気色の悪さを感じるのである。
というと、それがいわゆる霊魂ってやつですか。と問う人があるかも知れないが、私はそれは違うと思う。そうではなく、それは死によって途絶した意志の痕跡として、具体的な形をとって現れているように思う。
それは、物として現れ、人として現れている。植物として現れている。現象として現れている。物なれば、そのものを作った人の意志、例えば、可憐なれ、という意志が途絶して、可憐であることをやめて別の物と成り果てる形で現れる。大岩のすきまから洩れ出る意志としてそのように現れているのである。人なれば、大岩からその人を見る眼差しを感じて、ふと見上げる表情、本来の表情を刷毛でひと撫でしたような、他人のような表情として表れる。或いは、いっさいの表情を失し、そのために感情も失し、単なる光と影による、神話の登場人物として現れる。動植物も玩具も、そのように、突如として途絶した意志の形として現れる。
その様にしかし普通は気がつかないで、まさか気がつかないうちに、自分もまた途絶した意志の痕跡であるだなんて思いもしないで生きているのは、そんなことに気がついてしまうと普通に生きていけないからで、だから生きているということはどういうことかということがわからないようになっている。うまくできている。
ところが、『死小説』を読むときは、読んでいる間は別。大岩から、黄泉の国から、意志、気配がバスバス噴出してくる。匂い・手触りを伴って噴出してくる。気色悪さが気色よさに変じて、気がつくと念仏を唱えて号泣したり、少し笑ったりしている。全体的に気色よくなっている。生きている気色よさも死ぬ気色よさも力の有り様は同じようなものだな、とか思ってしまっている。吽。
ALL REVIEWSをフォローする