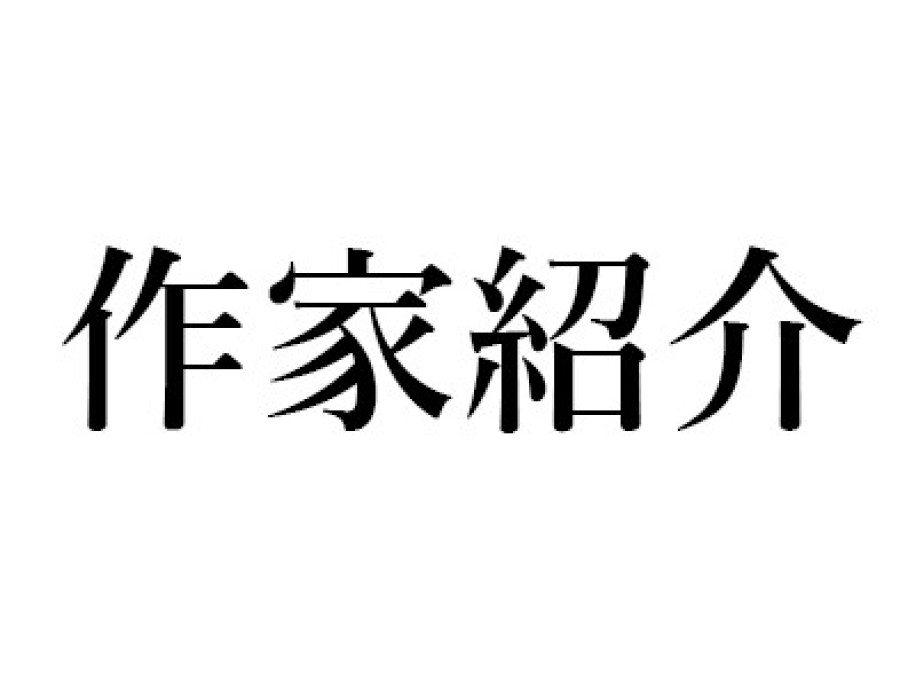書評
『小説、世界の奏でる音楽』(新潮社)
作家は小説を書き、編集者はそれを商品として企画し発売する。批評家は刊行された作品を論じ、読者は知的、あるいは商業的な情報に導かれて個々の作品に出会う。作家は直接読者に語りかけるのではなく、編集、出版、宣伝、批評などを介在させながら、読者と交信している。そのような関係性がいつ頃から成立したかは定かではないが、つい最近まで小説はほぼそのような循環のなかで流通してきた。
情報通信技術の発達は読書行為を大きく変えた。インターネット小説や携帯小説は活字出版媒体を必要としなくなり、読者が直接作品ないし作家を選別できるようになった。そのことの是非はともかくとして、作家と読者との関係が大きく変わったのはまちがいない。ただ、読書行為が進化したかというと、必ずしもそうではない。文学はむしろ以前にもまして大量消費の過程に巻き込まれるようになった。小説をどう読むべきか、読む行為がどうあるべきか、それらのことは以前と違った意味で重要になってきた。
小説に比べて、批評のほうはいまのところ、まだ大きな脅威に晒されていないようだ。無論、ブログでは従来のメディアに依存しない批評は多くあらわれている。だが、読者層が薄く、携帯小説のように商業的に成り立つまでには至っていない。
文芸批評に対する不満は以前からあった。言説の緻密さを求めるあまり、広範な読者を遠ざけたのみならず、作家とのあいだにもときには情動的な緊張をもたらした。旧来の批評が危機に直面しているかどうかは、人によって見方が分かれるところだが、批評のあり方に疑問を感じる人が増えたのは否めない。本書を読むとき、そのような時代の雰囲気を念頭に置くべきであろう。
この本は、もともと月刊の文芸誌に連載されたもので、三年まえに刊行された『小説の自由』(新潮社)とその翌年に出版された『小説の誕生』(新潮社)につづく三部作の最終巻。その内容を一言でまとめれば、小説とは何かについての探究である。だが、読者が結論めいたことを期待しようとすれば、肩透かしを食うであろう。そもそも著者はその問いかけに対し、明確な答えを与えようとしない。なぜなら、小説や芝居は安定した言葉で説明できるものではない、と著者は考えているからだ。小説とは何かの答えは誰かから与えられるものではない。読書行為のなかでしか得られないものだ。
取り上げられている作品を見てわかるように、著者の目と世間の基準とはだいぶ違う。この小説論を執筆する背景には、おそらく批評家に対する不満ないし不信があったのであろう。作品論は外から批評するのに対し、本書は内から作品を眺めることに徹している。小説がどのように書かれているか、その過程を作家の立場から解剖してみると、意外な点が多く見えてきた。
文芸批評の場合、しばしば作品の見映えを最大の優先事項とする。小説の構造が緻密にできているか、物語の展開に整合性があるか、言語表現が洗練されているか、それらのことはまず作品をはかる物差しとなる。だが、作家の立場から見ると、必ずしもそうではない。生を描けたかどうかが中心的な問題になる。既成の基準に一致しないことを著者は「緩さ」ということばで表現している。「緩さ」がどのようにオリジナリティを生み出したかが、具体例を挙げながら説かれている。
詩を書くことは雲にはしごをかけるようなものだ、という詩人がいる。小説も同じであろう。読者からみれば、小説家はまるで何でもできるマジシャンのようだ。何を書くかは事前にすべて心得ていて、創作はただ心のなかで練り上げた物語を手順どおりに言葉に置き換えるだけだ、だが、作品が出来上がる過程を見ると、作家は全知全能でもなければ、綿密な計画を持って書いているともかぎらない。むろんそのような作家もいるかもしれない。
だが、優れた作品はむしろ作家が迷走しながら書いている。著者のことばを借りれば、人間が芸術を作るのではなく、芸術によって人間が作らされるようにしむけられているのだ、自ら小説を書く者でないと、なかなか気付かないであろう。
小説の仕組みと自我意識とのあいだに共通点があるという指摘には、はっとさせられた。人間は一生のなかで多くの出来事を経験する。そのような経験は消えてなくなるのでなく、複雑な因果関係の堆積としていまの「私」がある。そのような仕組みは小説と似ていると著者はいう。第四章「涙を流さなかった使徒の第一信」は一見やや唐突に見えるが、自らの内面についての分析は、小説がどのように誕生するかを示唆して興味を惹く。
著者の見解にしたがえば、文学作品の善し悪しの見方はだいぶ変わる。小説はなにがしかの意味を読者に伝えるためのものではない。いい作品はむしろ「意味」を脱臼させ、読者を「意味」から離れた世界に連れ出す。逆に小説が何かを言うための表現形式だと思いこむと、作品の独創性には気付きにくい。
もっとも傾聴すべき点は、読書行為はどうあるべきか、ということである。作品を読むことは大変な努力が必要で、どのような優れた小説でも、よく吟味しないとほんとうの素晴らしさは見えてこない。必要なのは固定観念に囚われず、作品と正面から向き合うことだ。インターネット小説や携帯小説が流行っているいまだからこそ、そのような読みがますます大切になるのであろう。
【この書評が収録されている書籍】
情報通信技術の発達は読書行為を大きく変えた。インターネット小説や携帯小説は活字出版媒体を必要としなくなり、読者が直接作品ないし作家を選別できるようになった。そのことの是非はともかくとして、作家と読者との関係が大きく変わったのはまちがいない。ただ、読書行為が進化したかというと、必ずしもそうではない。文学はむしろ以前にもまして大量消費の過程に巻き込まれるようになった。小説をどう読むべきか、読む行為がどうあるべきか、それらのことは以前と違った意味で重要になってきた。
小説に比べて、批評のほうはいまのところ、まだ大きな脅威に晒されていないようだ。無論、ブログでは従来のメディアに依存しない批評は多くあらわれている。だが、読者層が薄く、携帯小説のように商業的に成り立つまでには至っていない。
文芸批評に対する不満は以前からあった。言説の緻密さを求めるあまり、広範な読者を遠ざけたのみならず、作家とのあいだにもときには情動的な緊張をもたらした。旧来の批評が危機に直面しているかどうかは、人によって見方が分かれるところだが、批評のあり方に疑問を感じる人が増えたのは否めない。本書を読むとき、そのような時代の雰囲気を念頭に置くべきであろう。
この本は、もともと月刊の文芸誌に連載されたもので、三年まえに刊行された『小説の自由』(新潮社)とその翌年に出版された『小説の誕生』(新潮社)につづく三部作の最終巻。その内容を一言でまとめれば、小説とは何かについての探究である。だが、読者が結論めいたことを期待しようとすれば、肩透かしを食うであろう。そもそも著者はその問いかけに対し、明確な答えを与えようとしない。なぜなら、小説や芝居は安定した言葉で説明できるものではない、と著者は考えているからだ。小説とは何かの答えは誰かから与えられるものではない。読書行為のなかでしか得られないものだ。
取り上げられている作品を見てわかるように、著者の目と世間の基準とはだいぶ違う。この小説論を執筆する背景には、おそらく批評家に対する不満ないし不信があったのであろう。作品論は外から批評するのに対し、本書は内から作品を眺めることに徹している。小説がどのように書かれているか、その過程を作家の立場から解剖してみると、意外な点が多く見えてきた。
文芸批評の場合、しばしば作品の見映えを最大の優先事項とする。小説の構造が緻密にできているか、物語の展開に整合性があるか、言語表現が洗練されているか、それらのことはまず作品をはかる物差しとなる。だが、作家の立場から見ると、必ずしもそうではない。生を描けたかどうかが中心的な問題になる。既成の基準に一致しないことを著者は「緩さ」ということばで表現している。「緩さ」がどのようにオリジナリティを生み出したかが、具体例を挙げながら説かれている。
詩を書くことは雲にはしごをかけるようなものだ、という詩人がいる。小説も同じであろう。読者からみれば、小説家はまるで何でもできるマジシャンのようだ。何を書くかは事前にすべて心得ていて、創作はただ心のなかで練り上げた物語を手順どおりに言葉に置き換えるだけだ、だが、作品が出来上がる過程を見ると、作家は全知全能でもなければ、綿密な計画を持って書いているともかぎらない。むろんそのような作家もいるかもしれない。
だが、優れた作品はむしろ作家が迷走しながら書いている。著者のことばを借りれば、人間が芸術を作るのではなく、芸術によって人間が作らされるようにしむけられているのだ、自ら小説を書く者でないと、なかなか気付かないであろう。
小説の仕組みと自我意識とのあいだに共通点があるという指摘には、はっとさせられた。人間は一生のなかで多くの出来事を経験する。そのような経験は消えてなくなるのでなく、複雑な因果関係の堆積としていまの「私」がある。そのような仕組みは小説と似ていると著者はいう。第四章「涙を流さなかった使徒の第一信」は一見やや唐突に見えるが、自らの内面についての分析は、小説がどのように誕生するかを示唆して興味を惹く。
著者の見解にしたがえば、文学作品の善し悪しの見方はだいぶ変わる。小説はなにがしかの意味を読者に伝えるためのものではない。いい作品はむしろ「意味」を脱臼させ、読者を「意味」から離れた世界に連れ出す。逆に小説が何かを言うための表現形式だと思いこむと、作品の独創性には気付きにくい。
もっとも傾聴すべき点は、読書行為はどうあるべきか、ということである。作品を読むことは大変な努力が必要で、どのような優れた小説でも、よく吟味しないとほんとうの素晴らしさは見えてこない。必要なのは固定観念に囚われず、作品と正面から向き合うことだ。インターネット小説や携帯小説が流行っているいまだからこそ、そのような読みがますます大切になるのであろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする