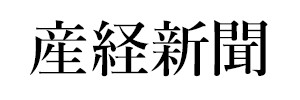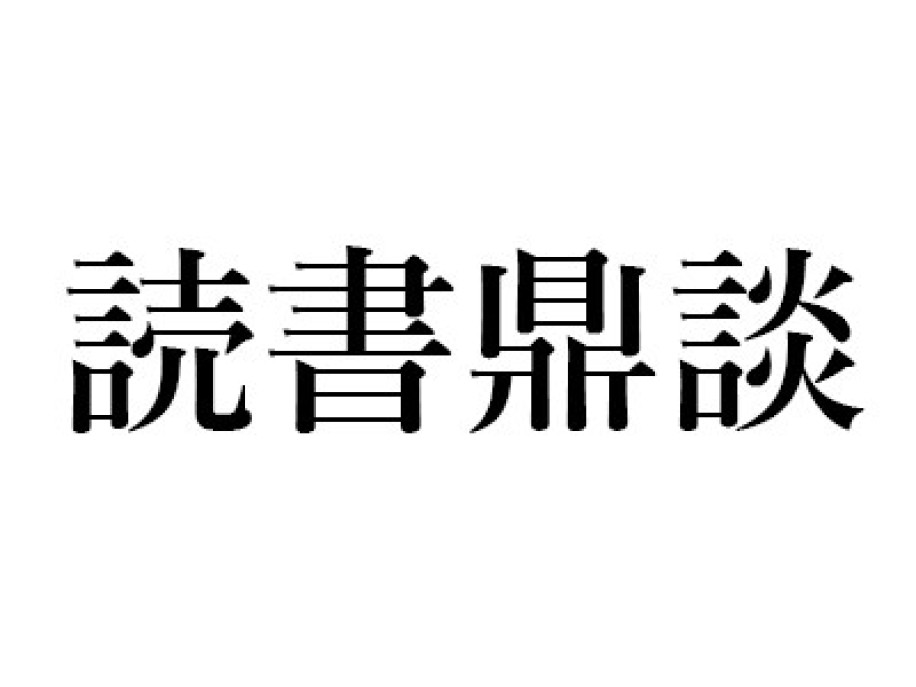書評
『琉球弧の喚起力と南島論』(河出書房新社)
吉本隆明氏の『南島論』(一九七〇年)は忘れえぬ論文だ。そこで私は、初めてレヴィ=ストロースの親族理論の概要を知ったわけだし、構造人類学が社会学への入り口になるという強い示唆も受けたのだ。
その吉本氏が、今また、南島論へ立ち返るという。
南島論は、都市論とペアになるものだ。
都市論は、現代の最も高度な都市が、国家の枠を否応なくはみ出していくことをのべる。いっぽう南島論は、天皇制や国家が生まれる以前の《基層》を掘り下げる。つまりどちらも、人類が国家なしに生きられることを論証する。
都市論のキー・ターム「アジア的」に加え、吉本氏は新たに「アフリカ的」を追加した。これは今の第三世界にもあたる。アフリカ的段階の都市は、アジア的、ついで西欧的な都市に変貌していくのが、自然史的な必然だという。《アフリカ的段階……を普遍的な概念として追加して南島論の基層を掘り下げ……天皇制を越える……人類の普遍的な……原型……とぶつかることができるんじゃないか》
こうのべる吉本氏に対して、一緒にシンポジウムに参加した赤坂憲雄氏は《吉本氏が……依拠するヘーゲル的な人類史の普遍性に対して……戸惑い》を隠さない。私も同様に感ずる。
大きな「歴史」を考え、そのなかで天皇制の、さらには国家の生成と死滅を見届けようというのが吉本氏の基本戦略である。だが、起源に遡れば、それを無化できるのか。国家の本質が共同幻想だとしても、それはわれわれの社会の強固な現実として、多様な機能を果たしているではないか。日本の天皇制にしても、高度資本主義のなかに再生しつづけている。《象徴天皇制の終焉と、日本の農耕社会の終りとが、対応関係にあるだろう》と言われても、にわかに信じられない。
国家がもちろん、問題なのである。ただそれは今、疎外論、幻想論で語るべき対象なのか? 権力はなにかの間違いでうまれただけのもので、歴史が進めば消滅するものなのか?
権力の制度ー政治権力のあり方が、時代とともに変化するのは当然だ。そこには「悪しき権力」や、社会の実態にそぐわぬ権力もあろう。国家がそうならそのつど問題にすればよい。
都市が国家をはみだすように見えるのは、経済や交通や情報の回路が、国家の範囲を越えてますます拡がっているためである。この傾向が続けば、やがて国家を解体しなければならなくなるのは目に見えている。だがそれは、国家をもっと普遍的な権力の制度に造りかえることのはずで、権力をきれいさっぱり地上からなくしてしまうことではないはずだ。
日本本土とまったく異なる歴史的経過をたどった南島は、興味のつきない場所である。しかし南島論が、吉本氏の戦略をまっとうするかたちで成立するかは、また別の話だ。赤坂氏の言う通りに、南島論の「第二章」は、もう吉本氏の手を離れ、万人の書き継ぐべきものになったのだろう。
【この書評が収録されている書籍】
その吉本氏が、今また、南島論へ立ち返るという。
南島論は、都市論とペアになるものだ。
都市論は、現代の最も高度な都市が、国家の枠を否応なくはみ出していくことをのべる。いっぽう南島論は、天皇制や国家が生まれる以前の《基層》を掘り下げる。つまりどちらも、人類が国家なしに生きられることを論証する。
都市論のキー・ターム「アジア的」に加え、吉本氏は新たに「アフリカ的」を追加した。これは今の第三世界にもあたる。アフリカ的段階の都市は、アジア的、ついで西欧的な都市に変貌していくのが、自然史的な必然だという。《アフリカ的段階……を普遍的な概念として追加して南島論の基層を掘り下げ……天皇制を越える……人類の普遍的な……原型……とぶつかることができるんじゃないか》
こうのべる吉本氏に対して、一緒にシンポジウムに参加した赤坂憲雄氏は《吉本氏が……依拠するヘーゲル的な人類史の普遍性に対して……戸惑い》を隠さない。私も同様に感ずる。
大きな「歴史」を考え、そのなかで天皇制の、さらには国家の生成と死滅を見届けようというのが吉本氏の基本戦略である。だが、起源に遡れば、それを無化できるのか。国家の本質が共同幻想だとしても、それはわれわれの社会の強固な現実として、多様な機能を果たしているではないか。日本の天皇制にしても、高度資本主義のなかに再生しつづけている。《象徴天皇制の終焉と、日本の農耕社会の終りとが、対応関係にあるだろう》と言われても、にわかに信じられない。
国家がもちろん、問題なのである。ただそれは今、疎外論、幻想論で語るべき対象なのか? 権力はなにかの間違いでうまれただけのもので、歴史が進めば消滅するものなのか?
権力の制度ー政治権力のあり方が、時代とともに変化するのは当然だ。そこには「悪しき権力」や、社会の実態にそぐわぬ権力もあろう。国家がそうならそのつど問題にすればよい。
都市が国家をはみだすように見えるのは、経済や交通や情報の回路が、国家の範囲を越えてますます拡がっているためである。この傾向が続けば、やがて国家を解体しなければならなくなるのは目に見えている。だがそれは、国家をもっと普遍的な権力の制度に造りかえることのはずで、権力をきれいさっぱり地上からなくしてしまうことではないはずだ。
日本本土とまったく異なる歴史的経過をたどった南島は、興味のつきない場所である。しかし南島論が、吉本氏の戦略をまっとうするかたちで成立するかは、また別の話だ。赤坂氏の言う通りに、南島論の「第二章」は、もう吉本氏の手を離れ、万人の書き継ぐべきものになったのだろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする