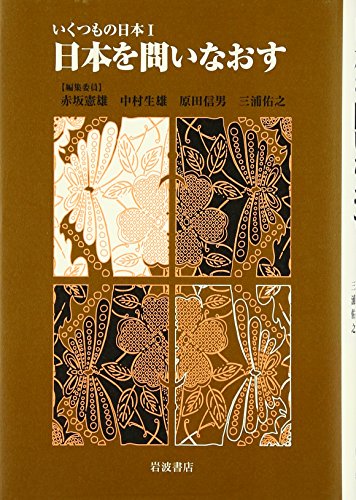書評
『信心の世界、遁世者の心 日本の中世〈2〉』(中央公論新社)
人々に仏の教えはどう説かれたのか
名古屋市東区に長母寺という寺がある。地方によくある、ごく普通の寺院であるが、成立は古い。鎌倉後期にその寺に四十年にもわたって住持となっていたのが、本書の水先案内人を務める無住である。四十年も住持でありながら無住と称するだけあって、その書物も『沙石集』(沙石は砂石と同じ)、『雑談集』とあって、ごく控え目であるが、著者の大隅が、日本の中世の信心の世界を明らかにするにあたって、この無住を選んだ理由は、その人物の性格と作品の性格とにあった。
これまで『沙石集』は説話集としてとらえられて研究がなされてきたが、大隅は、そこに書かれているのは、庶民に仏の教えをわかりやすく説いた説法をそのまま文章にしたような内容であり、我が身の信仰の遍歴である、と見て、このような作品からでないと、中世の人々の心を等身大に捉えることはできない、と考えたのである。
説法といっても、当時、名声を博していた安居院(あぐい)の流れのように、貴族や武家を相手にして経典や経論を引用して講演を行い、多額の布施を与えられるようなものではなく、文字の読み書きもできないような近隣の人々を相手にわずかな布施をえる説経師の行うようなそれである。
そうした人々を相手に仏の教えはどう説かれたのであろうか。このことを考えることで、中世の人々の信仰の世界をのぞいたのが本書である。
無住の生きた時代は、よく知られているように旧来の仏教信仰に対して、法然の浄土宗や大陸から伝えられた禅宗に代表される、新たな宗派が次々と生まれた時代である。それらは今日まで日本社会の仏教信仰の枠組みをつくってきたことから、これまでに多くの研究の蓄積がある。それだけにどれだけ新味が出せるのか、期待をもって手に取った。
そこでは、無住の生涯に始まり、生きること、貧しいこと、信心、神、僧と寺院、神社と神官、見えないもの、人の前世と後世など、十二章にわたって、『沙石集』に載る話を解説しつつ、その背景にある信仰の姿や、無住という遁世者の心を探ってゆく。
『沙石集』のわかりやすさにもよろうが、著者独特の淡々とした柔らかな語り口と、その読解とによって一気に読み終えてしまった。
その読後感から浮かんできたのは、著者の広い歴史的な視野からの観察であり、深い心の内面への洞察である。特に「私が出会った中世の人々は、中世でも現代でも人間として、同じ課題を背負って生きていることを、改めて考えさせられた」という一文は、何気ない文章ではあるが、まことに印象的である。
もちろん、中世の人々は見ることのできない神仏の存在と力を信じ、夢を回路にして神仏のことばを聞いていたということの指摘、また、神仏のお告げで霊魂の生まれ変わりを知って人間の運命を考えるかたわらで、極めて現実的な考え方をするという二重の基準をもっていたことの指摘など、中世の人々の独自性についての的確な把握も印象的ではあったが。
さらに、本書を読んで思い浮かべたのが、同じシリーズの最初の巻である石井進著『中世のかたち』との比較である。
石井は残念ながら、昨年十月、急逝したが、その書のなかで中世のかたちを捉えるために、列島の周縁部分にこそ目を注いだ。北海道の上ノ国や、津軽の十三湊、南は九州の鬼界ケ島など、鎌倉でもその周縁部分にこそ注目しており、さらには商人などの周縁身分の人々の活動をも考察した。
つまり社会活動の広がりの突端、あるいは基礎部分から、日本の中世社会のかたちを考えたのである。
そのために列島各地の発掘遺跡を訪れ、また民俗事象を採取することで、考古学や民俗学などの成果をも巧みに取り入れ、まさに幅広い石井歴史学の醍醐味をそこに展開したわけであるが、本書の著者の大隅は、『沙石集』に徹底的にこだわることで、宗教史への関心から中世の人々の心に肉薄しようと試みた。
それだけを見ると、大きな違いがあろう。
一方は足偏の歴史学と称されるように各地を訪ね歩き、そこから探ってゆく姿勢であり、他方は書斎にあって思索し目を凝らし探ってゆく姿勢である。むろん、大隅が現地に赴かなかったわけではないが、その現地の調査の成果は本書にはストレートには反映していない。
そうした意味からも、二つの書を読み比べてみると、歴史学の対照的なおもしろさが伝わってこよう。また共通して、現代人とはひと味違うとともに、現代人と共通する悩みも背負った中世の人々の姿と心が見えてくるに違いない。
ALL REVIEWSをフォローする