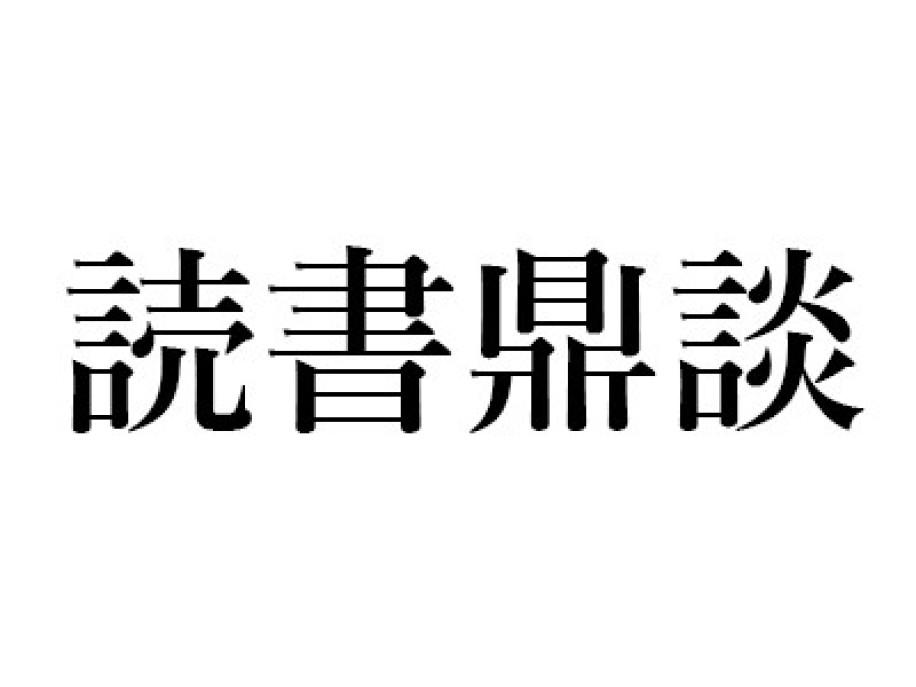書評
『動物園巡礼』(東京大学出版会)
不自然で無理のある施設
はじめに動物園の動物に対するまちがった見方が正してある。たいていの日本人がいだいている見方であって、動物園の動物は現地で捕獲され、運ばれてきて、狭いケージで飼育されているというのだ。現代の動物園で目にする動物の多くは、実は動物園生まれなのである。
動物園で生まれ育ち、ほかの世界をまったく知らず、動物園で死んでいく。そのため野生動物と区別して、「動物園動物」とも呼ばれている。
美術史家木下直之は、江戸の奇想の画家たちを「発見」した辻惟雄とともに、美術のワクを大きくひろげた人だ。おかげで美術の世界が、いや、世の中そのものが、うんとおもしろくなった。
両者とも、べつに新しい何かを見つけたというのではない。とうの昔からそこにあったもの、誰もが目にしながら、見ようとしなかったものを見た。ひとたびその人が見たからには、以後は誰もがそれを見ないではいられない。
木下直之にも「奇想」の再評価というところはあるが、氏素性正しき画家たちとちがって、こちらは名をとどめず、素性あやしく、まがいものとされてきた。そんな銅像や怪しい人形や、へんな肖像やハリボテの城。これまで学者たちが「キッチュ(きわもの)」として一顧だにしなかったもの。それがこの美術史家の手にかかると、みるみるきわものがホンモノになり、意味深い美的遺産として、日本人の精神史をいろどるまたとない証拠物件になる。
このたびは動物園を巡っていく。小田原城内にある小さな動物園が「巡礼」の皮きりだった。つづいて木下大サーカス、浅草花屋敷、もっぱらゾウをめぐっているのは「ゾウのいない動物園は動物園ではない」からだ。江戸時代からつづく見世物の花形であって、あの巨大な体躯(たいく)の、鼻の長い、忍耐づよい生き物の受難物語でもある。その最たる出来事は、「戦時猛獣処分」にまつわるエピソードだろう。せめてもの罪滅ぼしに「時局捨身動物慰霊祭」が催されたが、すぐ隣のゾウ舎の中では、「まだ二頭のアジアゾウが生きていた。殺されつつある最中であったといってもよいだろう」。
人間の勝手なご都合主義のもとに、動物にとって、どれほど理不尽なことがまかり通ってきたか。木下直之は「巡礼前夜」に、先立って書かずにいられなかった。「つまり、動物園とはほとほと不自然で厄介で無理がある施設である。それでも必要だと主張するのなら、その存在意義を反動物園論者に示さなければならない」
それだけに旭川市の旭山動物園にたどりついたときはホッとした。「すべて動物の意思」の原理でつくられており、さていま何をするかはペンギンがきめること。オランウータンの領分である。元園長いわく、「動物をずっと見ていてください。人間のほうがおかしいと思うようになりますよ」。
私はかねがね上野動物園のサル山に首をひねっていた。大きな白いコンクリートのかたまりで、無数の不定形なデコボコがつけてある。長年にわたるサル学の成果が、このような造形をもたらしたと考えていた。
単にサルの行動が見やすいのと、掃除しやすいためだった。たしかにボスをいただくサルの集団行動がよくわかる。ついては自分のモットーを一つまとめた。つまり、この世のすべての動物のなかでサルはもっともヒトに近いというが、これはまちがい。正しくは、この世のすべての動物のなかで、ヒトはもっともサルに近い。
ALL REVIEWSをフォローする