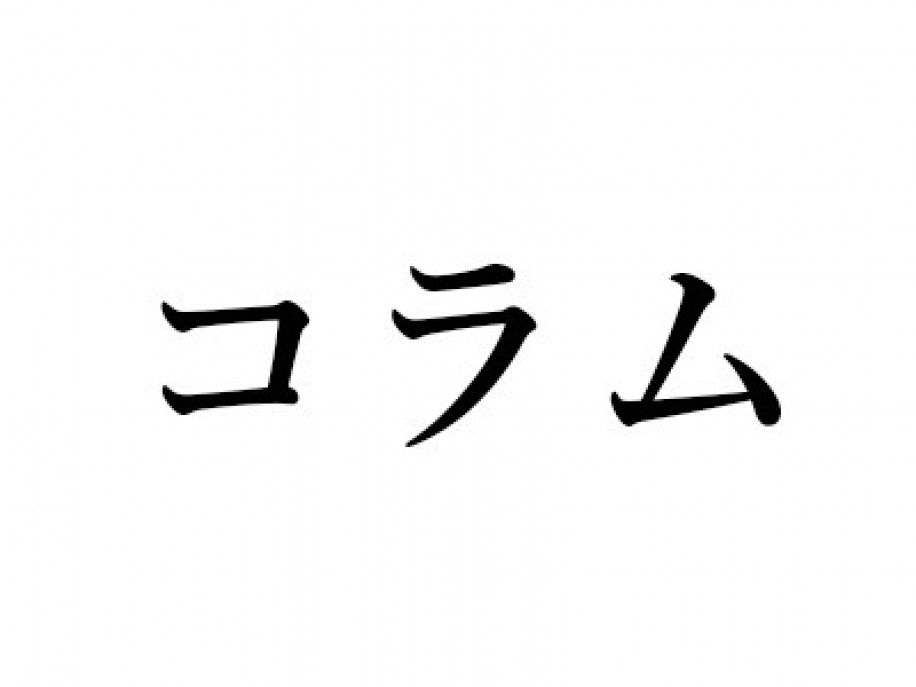書評
『火環: 八幡炎炎記 完結編』(平凡社)
鉄の町の繁栄と衰退を背景に激動の戦後を生きる少女の物語
いまは北九州市などと味けない名前だが、その前は若松、八幡、戸畑、小倉、門司の五市が関門海峡から洞海湾にかけて、覇を争っていた。いずれも石炭と鉄を背景に勃興した。かつて洞海湾を川ひらたと呼ばれる「黒ダイヤ」運搬の平底船がひしめいていた。製鉄所の煙突が戦艦の砲門のように屹立して、それは戦争のたびごとに数を倍増させ、連日連夜、火と煙を噴き、地鳴りのようにどよめいた。長編小説『火環(ひのわ)』は「八幡炎炎記 完結編」と銘打たれている。先に出た『八幡炎炎記』は鉄の町八幡を舞台に、敗戦まもなくのころだった。親方の妻と、手に手を取って広島から駆け落ちしてきた仕立て職人の夫婦。その妻の姉は建具職人の女房で、ひょんなことから孫娘ヒナ子を養育するはめになる。
敗戦とともに八幡製鐵の高炉の火は消えていたが、朝鮮戦争の勃発とともに息をふき返した。鉄都が甦る。
「ヒナ子。じいちゃんの焼酎ば買うてきちょくれ」
完結編では、ヒナ子は小学三年で、カラの三合瓶をもって酒屋へ向かう道すじ、電信柱のポスターや広告やチラシを眺めていく。多感な少女には、ポスターの男女の唇が日ごとに接近して見える。朝鮮戦争は三年目に入り、軍需基地ニッポンは朝鮮特需でうるおっていた。とりわけ、出征兵と帰休兵がごった返す北九州一帯は、天下の八幡製鐵所と性産業で笑いがとまらない。わずか七年前、この兵士たちの国と、まなじり決して一億国民が戦争していたなどと誰が覚えているだろう。
年が明けてヒナ子は小学四年に進級。クラスの男の子と、近くの山へ登りにいった。「あたし、おしっこ、まりたい(したい)」、藪の中途で、しゃがみこんだ。「透き通ったおしっこがにょろにょろと熊笹の間を流れ下り、葉陰にいた一匹の蟻が押し流されていくのが見えた。/蟻の災難じゃ……。ヒナ子がつぶやく」
『火環』は『八幡炎炎記』とつどって、「著者初の本格自伝的小説」となっている。ヒナ子はキヨ子の雛というわけだろう。自分が育った時代と、自分が生きた環境と、自分がしたしんだ人々のエピソードを綴れ織りにして、あざやかな人間絵巻をつくりあげた。文芸誌のカラ騒ぎを黙殺して、地味な雑誌に連載していたのを思い出す。今は亡き堀越千秋が、腕のいい仕立て屋のようなイキのいい挿絵をつけていた。うれしいことに、その一つが表紙カバーに使われている。
そこには四人の若い女が一心不乱にミシンを踏んでいるが、まさに洋裁学校とミシンの時代だった。男どもが特需景気に浮かれている間に、女たちはせっせと手職を身につけ、自立していった。ヒナ子は中学を出て、上の学校にすすまず、映画館の雑用係にもぐりこんだ。客であふれ返り、子供は最前列の台に顎をのせてスクリーンを見上げていたころであって、シナリオライター志望のヒナ子には、打ってつけの職場だった。
昭和三十年代、おりしも石炭が石油にとってかわられ、筑豊一帯はみるみるさびれていった。鉄の町にも落日が迫ってくる。それでも黒い巨大な軍艦都市はゴーゴーと火と煙を吐きつづけ、そのなかで一個の羅針盤に導かれるようにしてヒナはたくましく育っていく。その自信ある姿からして「完結編」とは、さてもピッタリの表現である。
ALL REVIEWSをフォローする