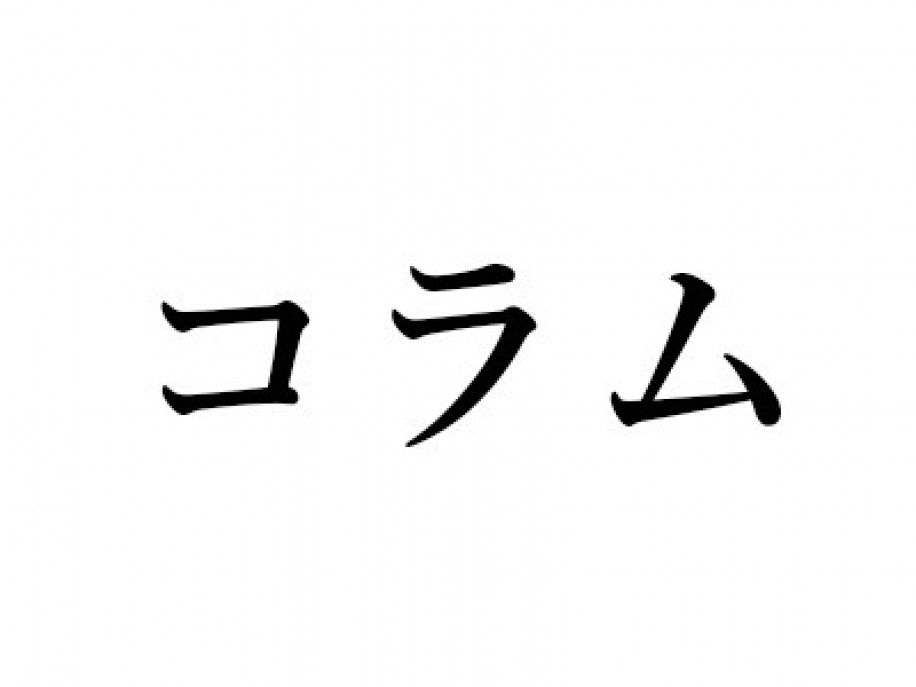書評
『台所半球より』(講談社)
主婦の日常とブンガクの関係
世によく「主婦作家」とか「台所で料理をしながら立って書く」といった紹介が横行するが、家庭をもった女がモノを書く、というのはそんなカンタンなことではないだろう。花嫁道具のタンスも鏡台もなく、本と本箱と原稿用紙を持って夫の所にきた時、「わたし、小説を書きます」とうちあけた。(村田喜代子『台所半球より』、講談社)
そのくらいの了解で成り立ったこの家の「夫」は「文芸書など読まず、その点で大多数のごく健全な中年男性の一人」だそうである。それはモノ書きの女にとって、かえってスバラシイことではなかろうか。夫婦喧嘩をすると、夫はすぐに「理屈をいうな!」と腹を立て、小説家の妻は頭の中で……と彼は言った、などとその場の様子をすぐ文章に並べたりする。何ともおかしい風景。
しかしそのくらいの了解の割には、この夫は妻の小説書きを邪魔立てする風もなく、アメリカ政府から妻が招かれれば、嫌がらずにパスポートを取りにいくのまでつき合ってくれる。このダンナサマの人柄のよい「普通さ」が、このエッセイ集をとても気持ちよく読ませてくれる。
それでも妻は家で小説を書いていると、「家族に奉仕すべき時間を多大にかすめとり、家族の世話にわずらわすべき頭を多大にこっちで消費しているので、気がとがめる」。
だから、家族が帰り、車庫のシャッターの音がすると、彼女はテーブルからサッと立ち、辞典、原稿用紙、万年筆、ぜんぶ戸棚の鍋につぎつぎと放り込んでしまうのだそうだ。
鍋、である。この作家は服は買わないのに鍋を二十も買い込んで、毎夜、台所でズラッと並べる。銀白色のアルミ鍋。「磨けばけっしてくすむことがないので、それらの鍋は床から光が湧くように眩しかった」。さながら鍋の星座である。
昔からモノを集めることが好きだった。小さな家の中に閉じ込められているからこそ、目は拡大鏡のようにモノに凝らされていく。
コーヒーをたてるとき、粉の山には小さな噴火口のように穴があく。高い所から火山を見下ろすとこんなかな、と一杯のコーヒーをたてる。塩辛を箸でつまんで、ビンの中から立ち上がれば怖い。梅雨あけの頃、ラッキョウを甘酢に漬けると、ガラス瓶の中で水面めざして「じりじりと尻尾からひしめいて」ラッキョウが登る。まるでムンクの「叫び」みたいなシュールな眺め。
村田さんは東京でブンダンに生きてはいない。九州の主婦である。だけど主婦の日常とブンガクは、非常に近いところにあるのだそうだ。ある友人はいう。
「ものをみる視力さえ過激にはたらかせれば、遠くへ旅行に出なくとも、おもしろい所へ行けるわね」
子どもがいる、夫の転勤がある、年寄りがいる、そんなエクスキューズを吹きとばすような励ましの痛棒ではないかしら。別に作家にならなくても、とりあえず日常に目を凝らすこと。
作中、一人と一匹が印象深い。
一人は村田さんを育ててくれたスギという天然木みたいなおばあさん。小学生の著者が習ったことを教えると、文字のよめない祖母は「しぇっち!」と舌打ちした。
この「しぇっち!」の意味は今だに不明だが、なにか慣りと軽蔑が入り混っていた気がする。そして「紙の上に書いとるようなことが、アテになるもんか!」とうそぶいた。
すごいおばあさんだ。
もう一匹。シベリアン・ハスキーの飼犬ルビ。この犬が初潮と発情期を迎えた描写。
その夜、風呂に入っていると、吹きさらしのコンクリートの上に散っていた昼間のしみが、眼に浮かんできた。まるで人間の女の出すものとおなじしみである。それと同時に風の中に立ちあがった時の犬の姿や、しぐさや顔の表情がよみがえる。すると一歳にも満たない犬の背負ったものがまざまざと見え、涙がポタポタと落ちた。
とてもとても読み捨てにしかねるエッセイである。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
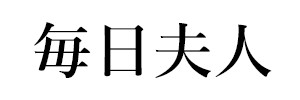
毎日夫人(終刊) 1993~1996年
ALL REVIEWSをフォローする