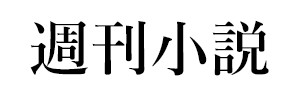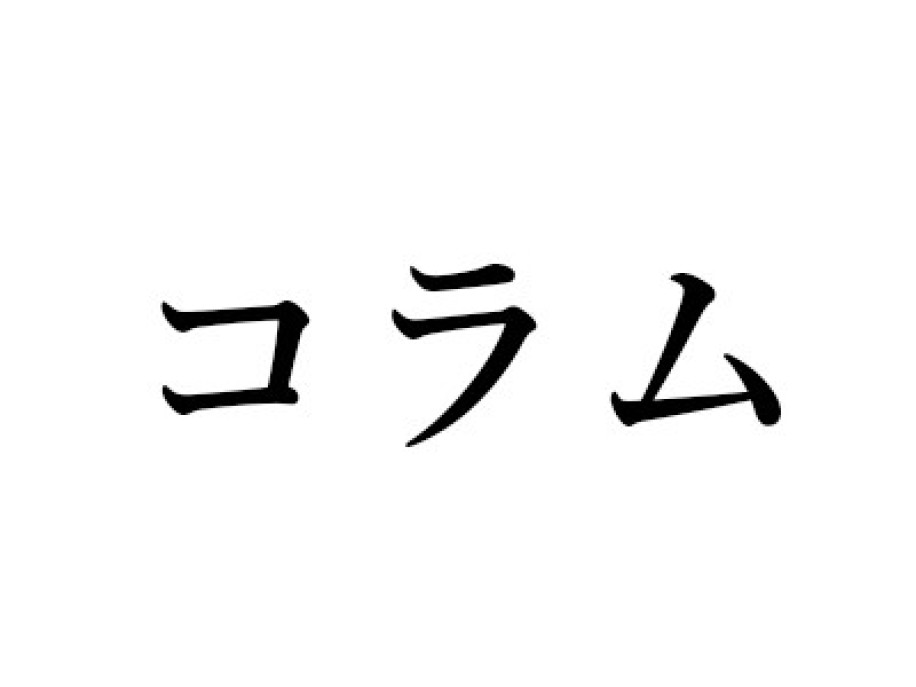コラム
山口 文憲『読ませる技術』(筑摩書房)、村田 喜代子『名文を書かない文章講座』(朝日新聞出版)、岸本 葉子『炊飯器とキーボード』(講談社)
カルチャーセンターって、どんなとこ?
ひょんなきっかけからカルチャーセンターで、エッセイの書き方を教えている。前に、エディター、ライター志望の人のための講座には出たことがあり、その話をもらったときは、
(エッセイに『書き方』なんてあるのか。あったら、私が習いたいくらいだ)
と思ったが、もの書きをして十年、日々の仕事の中で、習慣的に注意を払っていることや、バランスをとっていることが、ある気もした。それを、言語化し、人に伝える講座といえようか。
エディター、ライター志望のための講座は、若い人オンリーだったが、一般向けのカルチャーセンターとなると、年齢層は広い。女性は二十代からいるが、多いのは中高年。男性はリタイヤドが主。平日六時半からという時間設定のためもあろう。ひとクラス二十五名くらい。
受講の動機は、①書くことが好き、②できれば自分の本を出したい、③たまたま私の本を読んだことがあり「現物」ってどんなだろうとの興味から、の三つに大別できるようだ。課題の作文に付けてくる、メモ等からの類推である。
「岸本さんファンの若い女性ばかりだったらどうしようと思っていましたが、自分と同じオジサンもいて、ホッとしました」
と書いてきた男性もいた。
机の並べ方は、コの字やロの字にして講師を囲むという形式ではなく、全員が黒板を向いて座る。
そして私は、六時半から八時半まで、途中五分くらいのトイレ休憩のみはさんで、ほぼ二時間、ひたすらひとりで喋りまくる。黒板に書いては消し、書いては消し、何往復するかわからない。手はチョークでまっ白になる。さながら、予備校の授業のようである。
二時間のあいだ、受講者は一言も発することはない。その意味では、一方的である。
なごやかな座談の場にしないのは、私にとりまとめる能力がないためと、お金を払ってきている人の時間をムダにしては悪いと思うので。これは私の例であって、講師によっては、書いてきた作品を皆で合評する形式もあるらしい。
授業がすんだら、サッと帰る。どこかに寄って、お茶をすることはない。家まで一時間半と遠いせいもあるが、何よりも二時間で心身すり減らし、へとへとになるので。はじめの頃は特に、マイクを通しての音量がわからず、喉を使い過ぎ、終わったら声も出ず、倒れ込むように入ったラーメン屋のカウンターで、
「タンメン下さい」
のひとことが言えなかった。
もの書きは、と一般化していいのかわからないが、だいたいふだん家で机に向かっているので、まる一日声を出さないこともざらだし、そもそも人慣れしていない。労働効率からいっても、精神的にも、家で原稿を書いていた方が、よほど楽。などと書くのは、
「こんなにたいへんなんだぞ」
ともったいつけて、恩に着せようとしているのではない。カルチャーセンターというと、何やらあやしげな、あるいはバブリーなものと思っている人もいるかも知れないが、講師にすれば、割のいいバイト気分でこなせる種類のことではなく、それなりに真剣に臨んでおり、受講者には、その点だけは信じて、お金と時間とを割いてもらっていい、と言いたいがためだ。
インターバルは、私の場合、月一回。全三回のコースである。「旅のエッセイ」と「身辺エッセイ」の二つのコースを、三か月ずつ、年に六か月持っている。主たる業務に支障が出るので、後の半年は休講とさせていただく。
内容は、一回めは「旅」「身辺」とも共通で、エッセイの基本。
二回めからは分かれ、「旅」の方は、一回めで話した基本に加えて、旅エッセイに関する注意事項。旅先でのメモの取り方、写真の役割。ここで千二百字の作品を、課題として出す。十日くらいで書いてもらい、私が家で目を通し、ひとりひとりに評を記したメモをつける。
三回めは、課題のうちのいくつかと、本からとったコピーを、教材とする。
「身辺」は、今ちょうど内容を再考中なので、詳しくは書けないが、課題は八百字となる。
いずれも、三回を通じて、受講者の作品を含めて例文を十数から二十本ほど、教室で読むことになる。
受講者の作品を読んで気のつくことは、知り合いの男性編集者が、やはりカルチャーセンターでエッセイの講師をつとめた後、もらした言葉が言い得ている。
彼いわく、シロウトの人は、私のように月十五本とか二十本、
「あれ、この話、まだ書いてないよな」
とびくびくしながら原稿を送ってくる者と違って、「ここぞ」の大ネタを振ってくる。
だから、ネタとしては「岸本さんのより面白い」。
が、彼は仕事がら、内容の有無は別とし、「読みやすさ」という点では一定レベルをクリアした、職業的もの書きの文章にばかり、日々接している。それに比べて「なんて読みづらいんだろうと、思う」そうだ。
とすると、カルチャーセンターで教えられるのは、ネタの「出し方」と言えようか。
作品の中には、できごとが時系列で並んでいるが、書きたいことの中心がわからない、すなわち、何が出したいネタなのか、読みとれないものがある。そうなると、講師のできることは少ない。
カルチャーセンターで教えて十年以上の、山口文憲さんの『読ませる技術』(マガジンハウス)は、そのあたりを辛口に、でもていねいに説明し、書きたいとは何か、表現とは何かに分析を加えて、鋭い。自意識の次元にまで下りていっていて、どっきりさせられる。
村田喜代子さんがカルチャーセンターで教えた内容をまとめたのが『名文を書かない文章講座』(葦書房)。私が理屈でがんがん押していってしまうところを、
「あ、こんなふうに、わかりやすくも言えるんだ」
と参考になった。
冒頭に「ひょんな」と書いた、私が講座を持つことになったきっかけと、教室での悪戦苦闘ぶりは、拙著『炊飯器とキーボード』(講談社文庫)を、ご覧になられたし。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア