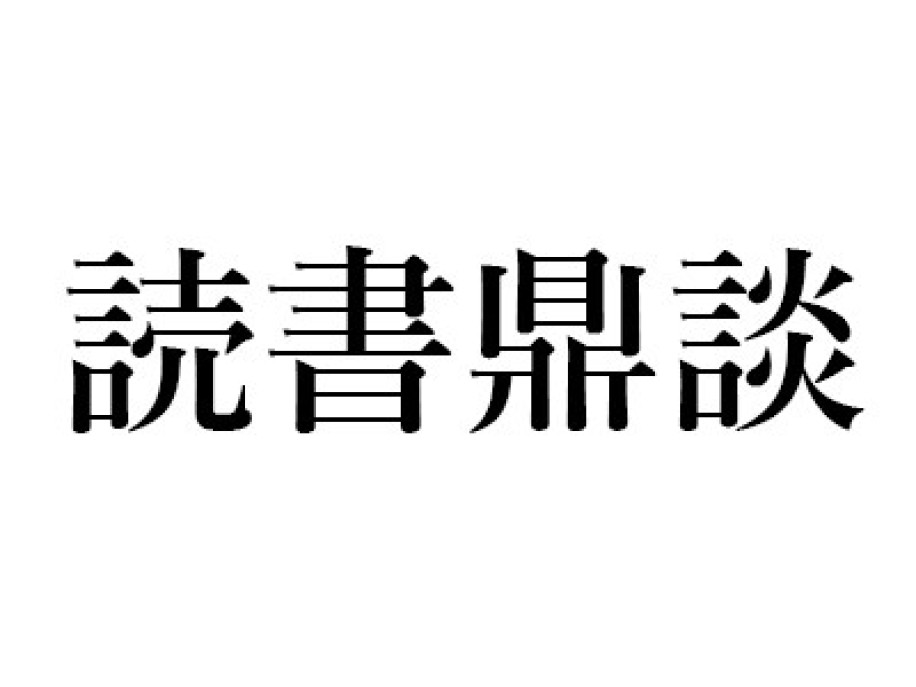書評
伊東 豊雄『この社会に、建築は、可能か』(青土社)、『誰のために 何のために 建築をつくるのか』(平凡社)
それが人の暮らす街なのだろうか
日本を代表する建築家の一人である著者が、自身の仕事を顧みながら現代社会のありようを問う。まず「渋谷から『場所』が消えていく」という文が目にとび込んでくる。渋谷がもっともひどいが、東京のあちこちで「場所」が消えている。暮らしの記憶がないのだ。「場所」は流動し、変化する自然との関係でつくられる時間的・空間的「淀(よど)み」であり、大地から離れた均質な空間にそれはない。それが人の暮らす街なのだろうかと思う。
そこで建築家は何をすべきか。著者の答えは、「美しい建築をつくること」、「失われつつあるコミュニティを回復すること」の二つである。具体的には、人と人とを結ぶ、人に居心地の良さを与える、人に生きる力を与えるという三つのテーマになる。
ここで最も興味深い「生きる力」は「動物的な生命力」であり、「現在話題を提供しているバーチャルな技術は妨げ以外の何物でもない」と言う。技術を否定するのではなく、生きる力を発揮させるための技術を求めているのだ。現代建築はグリッド(立体格子)を組み立てて均質な構造をつくっており、分断を生む。一方生物は多様、柔軟で外とつながり……と言っても都市にそのような建築がつくれるものだろうか。著者は「せんだいメディアテーク」で樹木の幹を思い描き、床を支える透明なチューブの太さや配置を一律でなくした。これが内にいても外にいる感覚になる空間を生み、あらゆる世代に利用される賑(にぎ)わいの場になっている。
伊東は独自性だけを強調しているのではない。多くの建築家との交流、そこからの学びが本書にもたくさん示される。そこから次々と新しい試みがなされ、「台中国家歌劇院」では二次元の平面はなく、全て三次元曲線という大胆な試みをした。11年をかけて完成した歌劇場は、まさに洞窟であり、古代の人々の棲家(すみか)と同時に未来を感じさせる。
とくに興味深いのは、東日本大震災後、仮設住宅暮らしの人々が集まる「みんなの家」だ。作品とは言えない建物だが、今も地域の人々にとって大事な場だ。著者は、多木浩二の「さまざまな記憶や物事で満たされた家は、建築家の考える家とはまったく異なる存在」という言葉、つまり「生きられた家」を思い起こす。そこにこそ「生きる力」があるのではないかと問いかけられていると感じたのだ。作品性のあるものを作りたい気持ちと、「みんなの家」で知った非作品性のもつ意味との間にある矛盾に悩んだ著者は、ある陶芸家の、でき上がった作品は土と火という自然の力が作ったものであり、作家は姿を消しているという言葉にハッとする。
これで暮らす場所の問題が解決したとは言いきれなくて当然という難しい課題だが、「生きる力」を求めることで、「場所」が消えない街が生まれることを期待している。
ALL REVIEWSをフォローする