書評
『数理モデルはなぜ現実世界を語れないのか:社会的な視点から科学的予測を考える』(白揚社)
意義と限界、暴走しないための5原則
誰もがその利益から排除されない「公共財」の例として、経済学のテキストでは多く国防や灯台が挙げられるが、近年では金融危機や気候変動、パンデミックに対する防止活動に、よりリアリティを感じる。興味深いのは、それらがともに「数理モデル」で解析されていることだ。記憶に新しいのが2020年に世界を脅かした新型コロナウイルス感染症で、ソーシャル・ディスタンス(社会的距離)の取り方により感染者数がどう変わるかを研究者がシミュレーションした。結果を可視化したグラフは鮮烈で、隔離につき国民の協力を促した。著者は「もっともシンプルな気候変動モデル」を提案した気候物理学者。数理モデルの専門家として金融危機やパンデミックにも通じており、本書はこれら三分野を例に数理モデルの意義と限界を論じている。難解な数理モデルの専門家は、仮説を過信してモデル内部に閉じこもり、リスクを過小に見積もりがちだが、予測がはずれれば現実世界に出て、金融や気候、疫病の危機に対して説明責任を負うべきと唱えている。
モデルは現実の「メタファー(隠喩)」で、「モデル化」とは、本質的とみなす事象間の因果関係を変数の関係式で浮き彫りにすることである。三次元の都会を平面の地図で描くような単純化をともなうが、買い物には役に立ってもビルの谷間でドローンを飛ばすには不十分だろう。モデルが予測に使えるかは、何を目的とし、現実とどこまで「類似」しているかで決まる。
「モデル生物」のマウスには、反応が人間に共通するという保証はないが、実験環境を均質にできるメリットがある。実験には「他のすべてが同じならば」という条件が必要で、「トラックがいつ時速100㎞に達するか」は、実験室では「力=質量×加速度」という物理法則通りになるとしても、公道で測定すると風速やトラックの形状、タイヤの使用年数といったその他の条件が関係してしまう。
モデルによる実験は均質な環境で反復されるのに対して現実の環境条件はそれぞれに異なり、一回限りの出来事かもしれない。毎日反復される短期の「天気」は過去から相当な精度で予測できても、長期にわたる「気候」は予測には不確実性が高い。それでも気象は自然現象だが、ウイルスの現実世界での蔓延(まんえん)は、人間の隔離行動によって条件が大きく変わる。
経済研究者は経済現象を観察者から独立していると考えがちだが、現実の金融取引で取引者が価格につきブラック・ショールズ・モデルで決まるとみなすとモデルが現実世界に「実装」され、モデルと現実世界の境界が明確でなくなり1987年の金融危機の一因となった。今後も当局の規制がどれほど効力を持つかは覚束(おぼつか)ない。
著者は数理モデルを予測ツールとしては否定的に見ており、それは書名の通りだが、他方で意義も強調している。定量化すれば意思決定にバイアスがかからないからで、課題は数理科学に過度に期待しないことだとしている。現場の最先端からの提言として本書はバランス感覚に溢れ、とくに終章にまとめられた「責任あるモデリングの5原則」には、数理モデルが暴走しないための英知が込められている。
ALL REVIEWSをフォローする






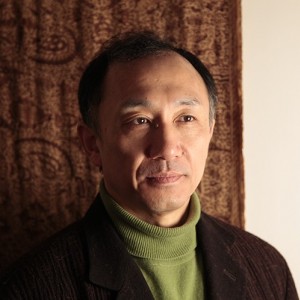





![中村桂子「2023年 この3冊」毎日新聞|<1>西田洋平『人間非機械論 サイバネティクスが開く未来』(講談社選書メチエ)、<2>中沢新一『カイエ・ソバージュ[完全版]』(講談社選書メチエ)、<3>ロビン・ダンバー『宗教の起源 私たちにはなぜ<神>が必要だったのか(白揚社)](/api/image/crop/916x687/images/upload/2025/03/e172f187e73582fd5102cba2655da740.jpg)

























