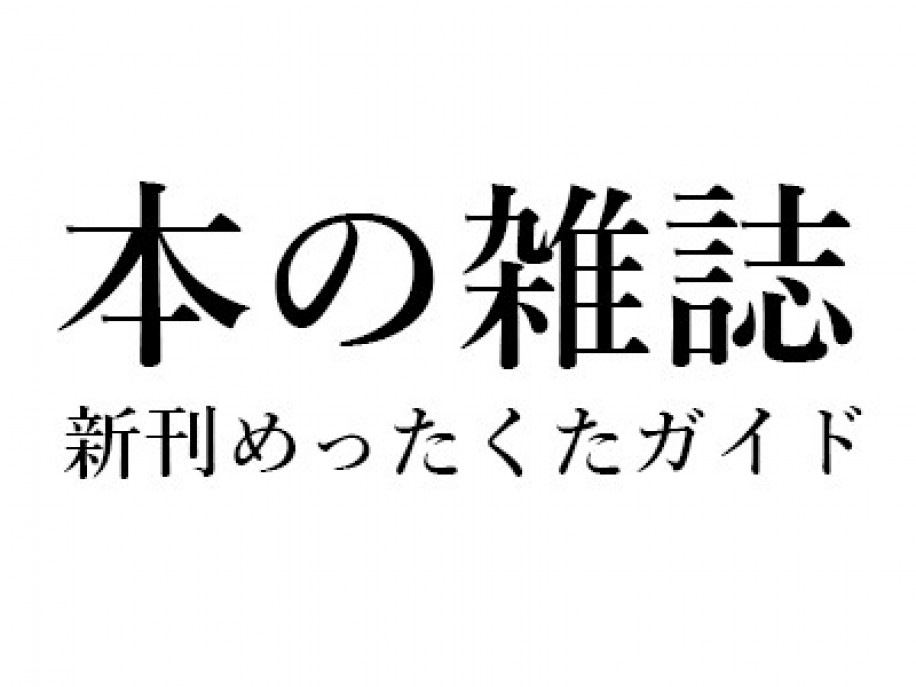書評
『法隆寺への精神史』(弘文堂)
建築史の神話
いやいや滅法おもしろい、井上章一『法隆寺への精神史』(弘文堂)は。法隆寺のエンタシスという円柱にみられるふくらみはギリシア神殿の建築がルーツ。中学の歴史の時間に誰でも頭にすりこまれる話ではなかろうか。
しかし井上さんは大学で建築史を学んで、この話が出てこないのをいぶかしく思う。その疑問がその仮説の淵源を探らせ、このような壮大な文化史になってしまったのである。
この説が国民的物語になったのはどうも大正八年の和辻哲郎『古寺巡礼』が大きいらしい。和辻は大和の古美術とギリシア古典の類似をうたいあげた。その和辻に影響を与えたのは伊東忠太。しかし、その前に石井敬吉という、のち構造設計に転向した建築家がいて、さらにまた影響を与えたのは……と従来の大河のように退屈な学説史と逆の方法で歴史をさかのぼりながら、さまざまな物や人の思いを法隆寺というランドマークの周りによび出す。著者は法隆寺そのものというより、法隆寺を通じて彼らが何を語ろうとしたか、その精神史に注目する。だから思いつきやハッタリや妄想の論まで検討している。
フェノロサは「欧米人に興味深い」見方をもち込み国粋を保存するといいながら、その国粋を欧米人向きに解釈しなおした。欧化への情熱にとらわれた人々はこれに追随して、ギリシアからインドへ、そして法隆寺へという文明の流れを見たがった。
反対に一九二〇年代から皇国史観が時流となると、法隆寺の非対称な伽藍配置にシンメトリーを好まない「日本の固有性」を見るのが大勢となる。あるいは一九三〇年代になると、堀口捨巳などによりモダン・デザインの実践的な立場から法隆寺を解釈しようとする。
キリストと聖徳太子の生誕伝説、インド美術の固有性の発見、法隆寺再建説など脇の固めも多彩、仮説が自信に変わる道のり、発見をめぐる先乗り争い、学者にはいえない素人説のオリジナリティなど、きわめて人間臭い建築史を、じつに冷静に実証的にやってみせた快著である。
これまでの何冊かに比べ文体がスッキリして、気持ちよく肉声が届く。願わくば著者はエラくならずに、これからも権威や定説にあざやかなウッチャリをかけつづけてほしい。いやすでに扱い残した梅原日本学への手袋があとがきで投げられている。次作「縄文幻想」待ってます。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする