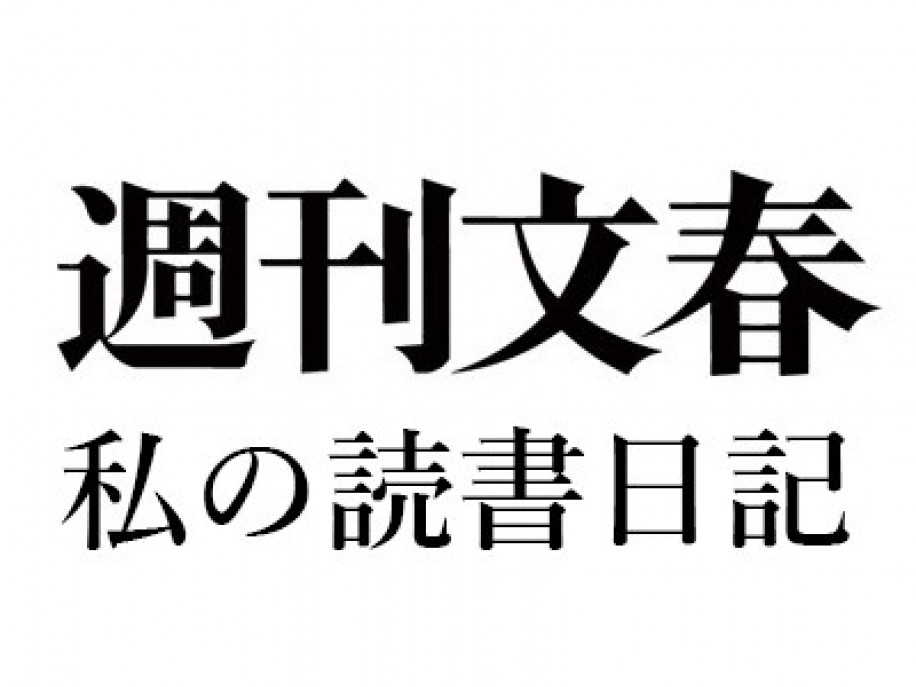書評
『建築MAP京都』(TOTO出版)
千二百年の京都建築にアクセス
どうしてこのような本がたくさん売れるんだろうか。売れるからには買ってる人がそれだけいるにちがいないが、誰がいったい“建築マップ”などという専門的な本を買うのか。このシリーズの第一弾の『建築MAP東京』(TOTO出版)が出た時にそう思ったし、このたびの京都でまたまた思っている。ヨーロッパと日本の観光ガイドブックの大きな差は建物の解説にある、とその筋ではしばしば言われてきた。パリでもローマでもロンドンでも、たとえばミシュランのガイドを見ると、まずその都市の歴史と概説があって、次あたりで一気に建築様式の図解がはじまる。ゴシックとかルネッサンスとかのヨーロッパ共通のスタイルの特徴と見所が語られる。各国各地に固有なものは、たとえばオランダなら“アムステルダム派”とか、ウィーンなら“セセッション”とかはコラムで出てくる。
もっと驚くのは観光客の寄りそうな建物の解説で、なんという建築家が手がけたもので、どこに特色があるか、スタイルは何か、までちゃんと書いてある。
ところが日本はちがう。東大寺の国宝の南大門のガイドに、仁王像の彫刻家の名は出てくるが、門そのものを設計した俊乗坊重源のことも、大仏様(よう)というスタイルであることも、その特異な軒の構成についても触れられはしない。
そういう状態が悲しくて、建築の面白さについて知ってもらおうと、これまであれこれやってきたが、どれだけ効果のあったものか。渦中の本人には分からないのかもしれないが、そうとう空しい感じのキョウコノゴロなのだった。
ところが、『建築MAP東京』は発売三年半で七万部以上も出たというのだ。京都や奈良ならいざ知らず、東京の建物の見るべきものはほとんどが明治以後現代までのもので、まず観光客は買わんだろう。建築の本はふつう二、三千部がいいとこで、出ても、二、三万。どこに七万人もの読者が隠れていたのか、分かるもんなら教えてほしい。
それで今度は京都。帯には「この一冊で一二〇〇年の京都建築へ確実にアクセスできます」とうたってある。
中を見ると、地図、写真は当然として、解説が詳しい。たとえばありきたりの銀閣寺を見ると、「一般に金閣に対して、銀閣と呼ばれて親しまれている二層の楼閣。足利義政が西芳寺の瑠璃殿を模して自らの山荘に建立した。……二階は花頭窓が並び、軒廻りに出三斗を配した禅宗様仏堂の形式をとる。盛砂や池が配された閑雅な庭園内に端然と佇むその姿は、拝観者を魅了してやまない」
建設の事情から見所まで短文のうちに過不足なくまとめ、ちゃんとスタイルや作り方の具体的な特徴にも触れている。それも、花頭窓とか出三斗(でみつと)とか情容赦なくテクニカルタームを駆使して、ハードボイルドに攻める。詳しい内容は分からなくても、花頭窓というからにはともあれ華やかな作りの窓だろうと予想がつくからつまずきはしない。出三斗はつまずくかもしれないが、こんなのは専門家のおまじないだと思って飛び越えても意味は通じる。
古建築から出来たての京都駅までこの感じで登場するのである。
こういう本が一般向けに出るんだから、いよいよ日本もヨーロッパ並みに、と思う反面、なんかの間違いじゃあるまいか、と疑ったりする。一般の人は私が思っているよりもっと先に行ってるのかもしれない。
【携帯版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする