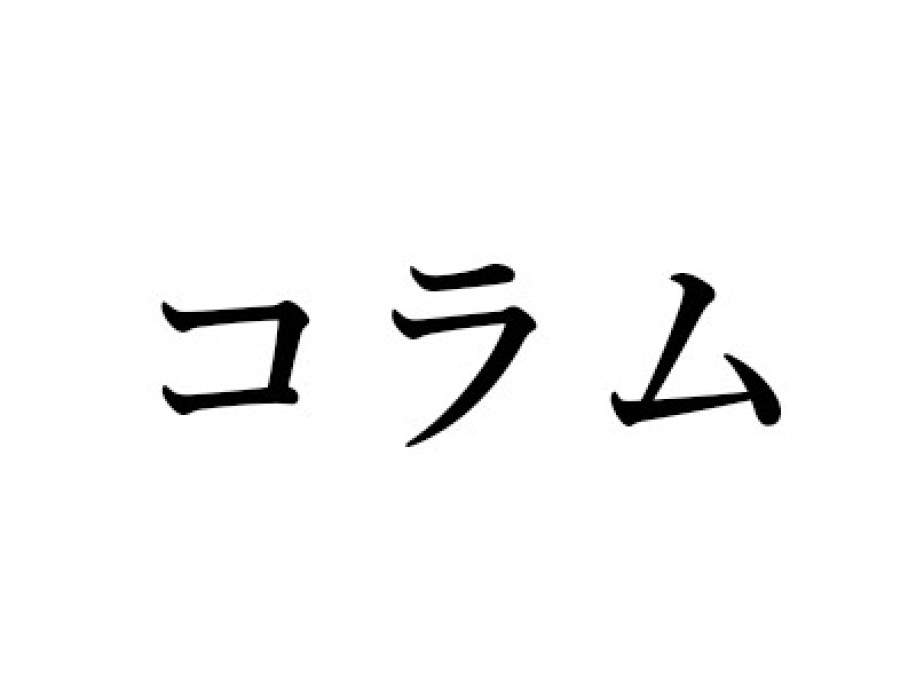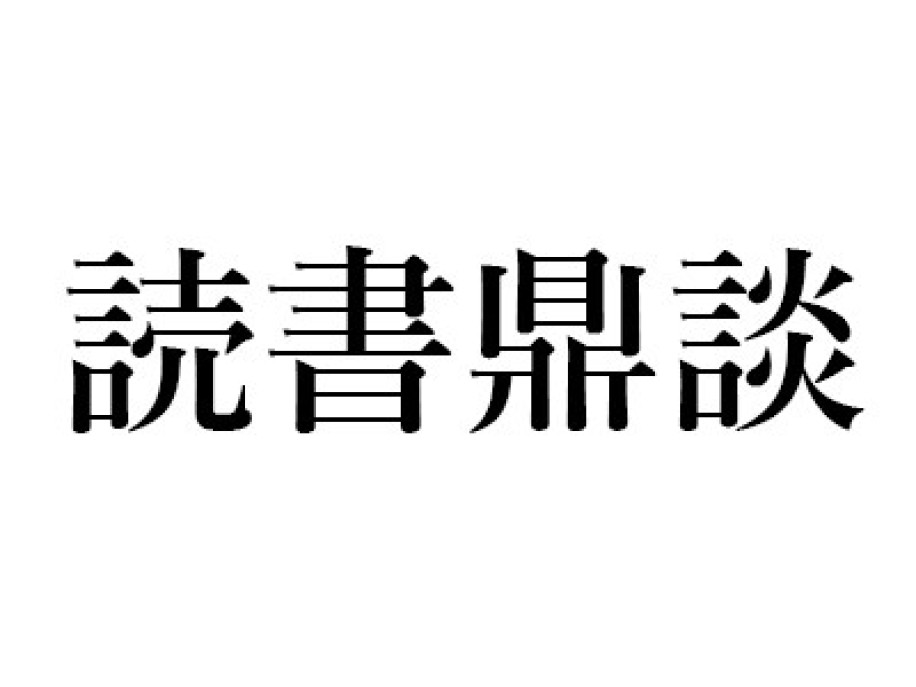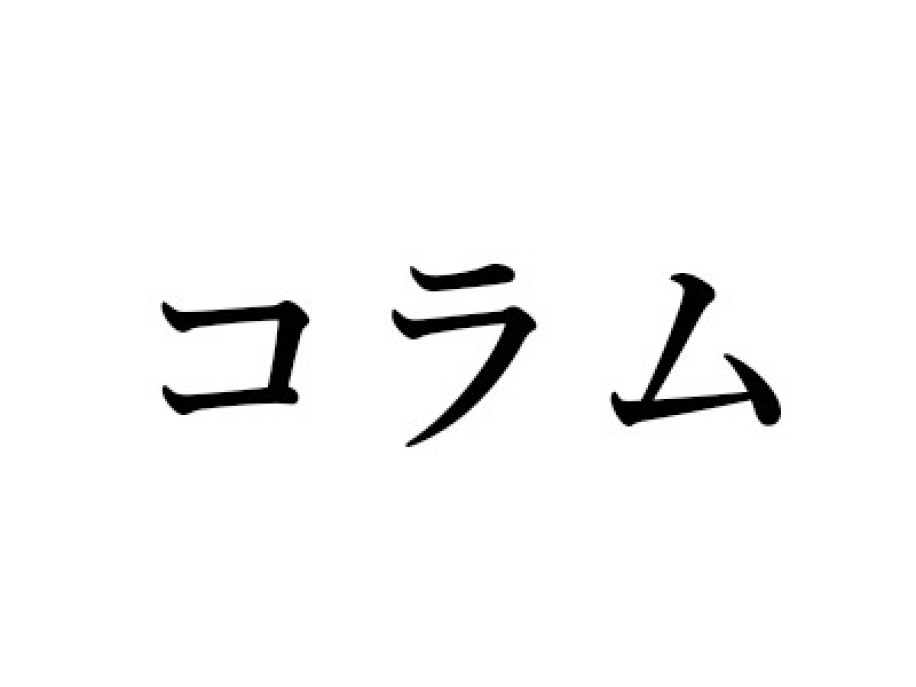書評
『DISCONT不連続統一体―吉阪隆正+U研究室』(丸善)
建築の根源を求め続けた吉阪隆正の生涯
日本の建築家についての本を取り上げるのは楽じゃない。丹下健三と黒川紀章と安藤忠雄の三人のほかはあまりに名が知られていなさすぎる。英語にたとえるなら、ペンとブックとノートの三つしか単語を知らない人に英文の読み方、味わい方を教えるのに似た困難がある。ここに紹介する本は、書名も著者名も、英語、漢字、カタカナが混在し、いったい誰が何について書いたのかにわかに判別しがたいが、テーマは、吉阪隆正(よしざかたかまさ)という十八年前に六十三歳で亡くなられた建築家。書いたのはその弟子のグループ(丸善刊)。
私は吉阪さんのことを直接は知らないが、学生の頃見たことはある。彼が日本建築学会の会長として大会であいさつした時、最初のお言葉は「ハイ、皆さん、両手を上にあげて、ブラブラ~~」。会場に居並ぶ謹厳な学者先生たちは、吉阪さんじゃ仕方ないナアと苦笑いしながら、会長に倣って両手を上げたのだった。
エピソードにはことかかない。弟子の重村力が、病床に最後の別れを告げに行った時、これからは国際交流が大事と言われ、先生のように(戦前、ジュネーブの国際学校を卒業)外国語が上手じゃありません、と言うと、「人間の交流は、吐く息と吸う息があればできます」。
一度でも接した人は忘れることはできない、そういう人だった。
建築家としては、戦後すぐ、フランスのコルビュジェの許で学び、帰国後は、早稲田の建築の今和次郎につづく名物教授として、幾多の学生の人生をアヤマラセつつ、設計事務所を開設して、社会的に比較的知られた作品としては八王子の大学セミナー・ハウス、日仏会館などを作った。私が好きなのは、富山の呉羽中学校と青山のヴィラ・クゥクゥで、コンクリートの塊が地面から突き出してきたような姿をしている。
吉阪は建築というものについて次のように考えていた。
雨が降って来た。
バナナの葉を一枚もいで頭にかざした。
雨のかからない空間ができた。
バナナの葉は水にぬれて緑にさえている。
バラバラと雨の当たる音がひびく。
相当な雨らしい。
新しい空間とは、こんな風にしてできるのだ。おそらくこれ以上の方法で、新しい空間は生まれない。
葉っぱは傘になり、傘は屋根になり、屋根は住居になって、それからまた、諸々 の公共の場所にもなっていった。(一九五九年)
師のコルビュジェは、一九二〇年代、科学と技術の二〇世紀にふさわしい建築を求めて、四角な白い箱に大きなガラス窓を開けた“モダニズム”とよばれる合理的なデザインからスタートするが、途中で疑問を覚え、大きく方向を転換して、大地と血(土俗的伝統)に建築の根源を求めてゆく。吉阪はこうした後期のコルビュジェの思想を受け継いで、さらに深く、遠くまで行こうとした。しかし、彼が生きた戦後の日本は科学技術と経済成長まるだしの時代で、時代の制約の中でしか実現しない建築の設計においては存分に生きることはできず、言葉を遠くに投げるしかなかった。
しかし、さいわい弟子や孫弟子の世代が、彼の言葉を拾って、駆け出した。どこに行きつくかは分からないが。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする