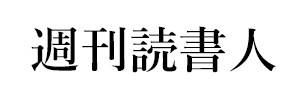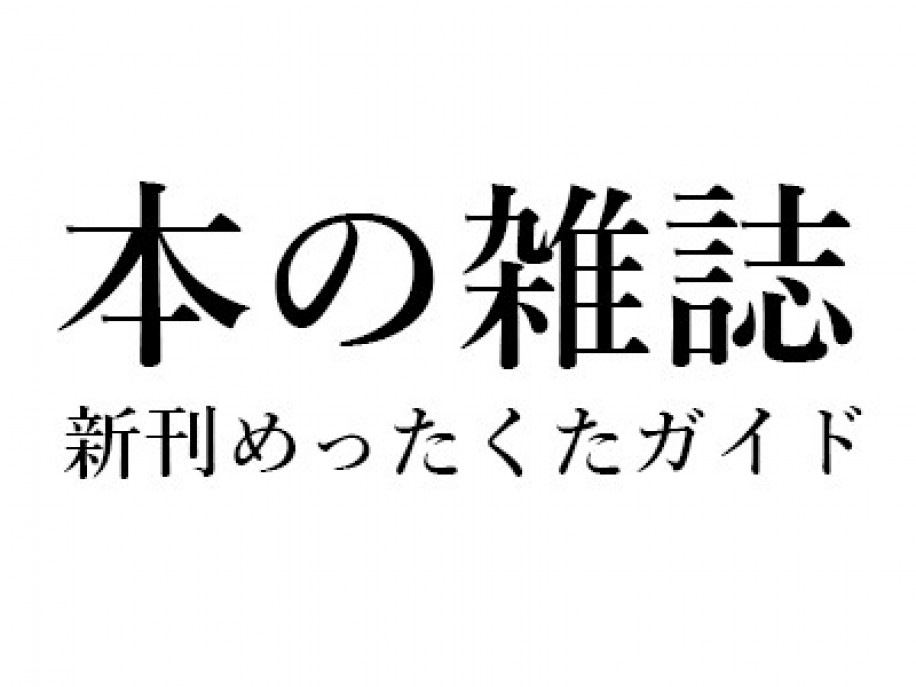書評
『近代的世界の誕生―日本中世から現代へ』(弘文堂)
オーソドックスなタイトル。中身もそれに相応しく、諸大家からの引用を縦横にちりばめている。文体は抑制ある語り口ながら、その時々の流行思想と無縁なところで、情況の与える課題に応え、時代の制約を超えて行こうとする志をのぞかせている。
日本近代(の挫折)については、もはや語り尽くされた感があろう。しかし、著者奥井氏は、ここに新しい図柄をひき直そうとする。それは、丸山眞男をはじめとする、日本近代主義者の言説を片端から覆すに等しい。その力業の根拠となるのが、網野善彦、勝俣鎮夫ら日本史学の新しいうねりであり、また、著者一流の社会学的考察である。
全体は、理論的/思想的/歴史的/世界的考察の、重量的構成をとる。相関社会科学出身の著者らしい、複線の張り方だ。内容は、日本と西欧の対比が軸になる。日本は日本なりに近代への道をたどってきた。西欧に較べて特殊すぎるわけでも、遅れていたわけでもない。そう著者は主張する。
論理の展開に、独特なものがある。著者も言う、「本書でもさかんに用いた、対立物を対立物のまま統一するといった論理」。通説を、著者はまず、対立しあう二項に分解して捉える。ウェーバーとブレンターノ。丸山眞男と吉本隆明。あるいは、エゴイズムとモラル。西洋的なものと日本的なもの。公家的なものと武士的なもの、等々。つぎに著者は、その表面的な対立の背後に、対立を成り立たせる隠された共通基盤を探りあてる。それこそ、近代のあり方を支える当のものであるはずだ。
社会科学の権威が失墜し、常識の多くが立枯れている今、戦後日本社会の位置を、歴史的・空間的に測り直そうとする著者の試みは、なかなか結構である。個々の論点にも賛成できるところが多い。もちろん主張の全てに同意するわけではないが、日本の近代像を描き直そうとする著者の企図は、なかば以上成功しているように思う。
もの足りなく思った点もあげよう。引用によってまず足許を固めようとするせいか、著者自身の手による論理展開の緻密さ、周到さ、厳しさが、いくぶん殺がれているように思う。著者が愛書家であることはよく分かるのだが、現実社会と直面しているというより、著者の読書空間を追体験しているだけのような印象を与えてしまって、損な文体だ。文も長く、言い回しが彎曲している。奇をてらっているわけでは毛頭なく、見かけと違って難しいことをのべていない。誠実な味わいがあり、慣れればむしろ微笑ましくさえある文章なのだが、特に若い読者が、その前に放り出してしまわないか心配になる。
本書は時代的にも空間的にも、広い範囲をカヴァーするので、議論が大股なものになるのはやむをえない。それにしても、たとえば結章「近代からの脱出」のあたりなど、もう少し粘って書きこんでもらえたら、と歯痒く感じた。
それでも本書は、十分に目的を達しているのだろう。中世から近世にかけての日本社会に、西欧史学の引写しでない、新たな分析の光をあてること。そこに、日本近代をかくあらしめた来歴をさぐること。それには、西欧・日本を等距離から記述できる普遍性と抽象度をそなえた、社会学的考察を鍛えるべきこと。本書が訴えるのは、こうしたメッセージである。これにはもとより、異存ない。引き続く研究プランをすでに用意してあるという著者奥井氏の、次作を楽しみに待ちたい。
【この書評が収録されている書籍】
日本近代(の挫折)については、もはや語り尽くされた感があろう。しかし、著者奥井氏は、ここに新しい図柄をひき直そうとする。それは、丸山眞男をはじめとする、日本近代主義者の言説を片端から覆すに等しい。その力業の根拠となるのが、網野善彦、勝俣鎮夫ら日本史学の新しいうねりであり、また、著者一流の社会学的考察である。
全体は、理論的/思想的/歴史的/世界的考察の、重量的構成をとる。相関社会科学出身の著者らしい、複線の張り方だ。内容は、日本と西欧の対比が軸になる。日本は日本なりに近代への道をたどってきた。西欧に較べて特殊すぎるわけでも、遅れていたわけでもない。そう著者は主張する。
論理の展開に、独特なものがある。著者も言う、「本書でもさかんに用いた、対立物を対立物のまま統一するといった論理」。通説を、著者はまず、対立しあう二項に分解して捉える。ウェーバーとブレンターノ。丸山眞男と吉本隆明。あるいは、エゴイズムとモラル。西洋的なものと日本的なもの。公家的なものと武士的なもの、等々。つぎに著者は、その表面的な対立の背後に、対立を成り立たせる隠された共通基盤を探りあてる。それこそ、近代のあり方を支える当のものであるはずだ。
社会科学の権威が失墜し、常識の多くが立枯れている今、戦後日本社会の位置を、歴史的・空間的に測り直そうとする著者の試みは、なかなか結構である。個々の論点にも賛成できるところが多い。もちろん主張の全てに同意するわけではないが、日本の近代像を描き直そうとする著者の企図は、なかば以上成功しているように思う。
もの足りなく思った点もあげよう。引用によってまず足許を固めようとするせいか、著者自身の手による論理展開の緻密さ、周到さ、厳しさが、いくぶん殺がれているように思う。著者が愛書家であることはよく分かるのだが、現実社会と直面しているというより、著者の読書空間を追体験しているだけのような印象を与えてしまって、損な文体だ。文も長く、言い回しが彎曲している。奇をてらっているわけでは毛頭なく、見かけと違って難しいことをのべていない。誠実な味わいがあり、慣れればむしろ微笑ましくさえある文章なのだが、特に若い読者が、その前に放り出してしまわないか心配になる。
本書は時代的にも空間的にも、広い範囲をカヴァーするので、議論が大股なものになるのはやむをえない。それにしても、たとえば結章「近代からの脱出」のあたりなど、もう少し粘って書きこんでもらえたら、と歯痒く感じた。
それでも本書は、十分に目的を達しているのだろう。中世から近世にかけての日本社会に、西欧史学の引写しでない、新たな分析の光をあてること。そこに、日本近代をかくあらしめた来歴をさぐること。それには、西欧・日本を等距離から記述できる普遍性と抽象度をそなえた、社会学的考察を鍛えるべきこと。本書が訴えるのは、こうしたメッセージである。これにはもとより、異存ない。引き続く研究プランをすでに用意してあるという著者奥井氏の、次作を楽しみに待ちたい。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする