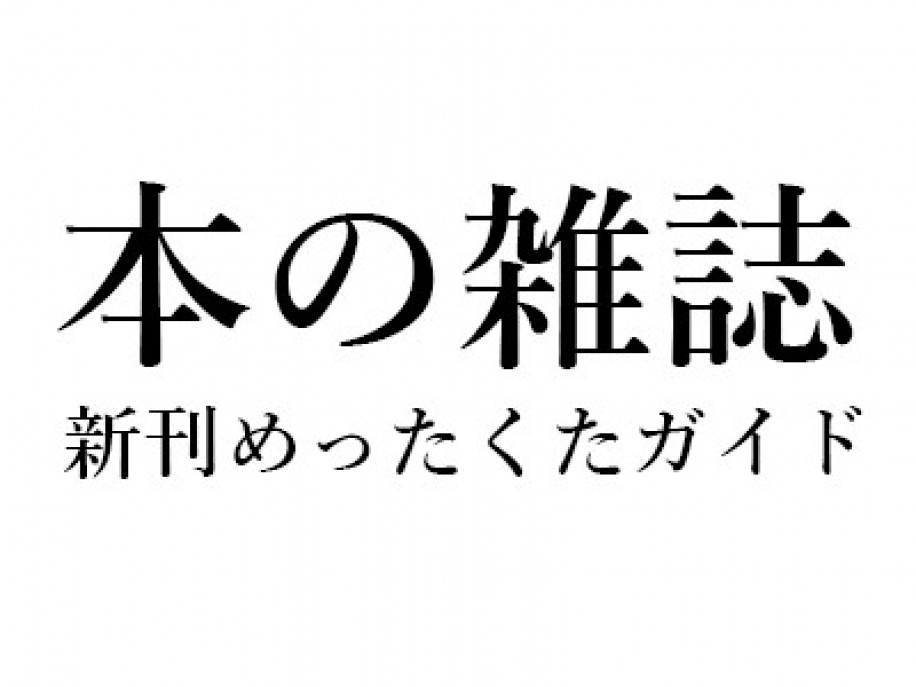読書日記
米光 一成「新刊めったくたガイド」本の雑誌2005年3月号―デビッド・フリードマン『ペニスの歴史』(原書房)、柳父章『近代日本語の思想 翻訳文体成立事情』(法政大学出版)他
ちんことかうんことか書いて、ぎゃーぎゃー喜ぶのは中学生までで限界という説に賛成。であるが、でも、ちんこうんこと書いて、それが活字として紙に固着し、大量生産されるのを夢想すると、ちょいと喜びたくもなってくる。「米光のちんこ」とか書くと、膨大な数の「米光のちんこ」という言葉が、この世にばらまかれるわけだから。米光のちんこ万歳! わいわーい。
という枕で紹介するのは、デビッド・フリードマン『ペニスの歴史 男の神話の物語』(井上廣美訳 原書房/二八〇〇円)。古代神話から勃起産業までの長いペニスの歴史を紹介している本であり、「人間とペニスの思想史」として真剣に読むこともできちゃいますが、「ちんこトリビア本」として楽しんじゃっても可。
話は、古代エジプトの創造神アトゥム(私は私のこぶしと交わり世界を創造したとか言い出しちゃう豪の者)から始まり、ダ・ヴィンチのちんこ研究、包皮縫合や尿道電極といった恐怖の自慰行為防止策、サルの睾丸移植や人工陰茎や勃起薬など、驚愕のネタが満載。特に偉人に関するちんこ発言や事件は、偉人であればあるほど、ちんことのコラボレーション(略してチンコラ)の妙が際立っちゃう。
キリスト教のチンコラも強烈で、イエスが割礼で取っちゃったちんこの皮は、唯一地上に残っている彼の肉体だってことで、もう教会の人たちおおさわぎ。十以上の教会が「聖なる包皮」を持っていると主張、鑑定家が出現して味見テスト。ぺぺぺっ。記録にある話では、包皮からはこの上ない芳香が放たれるし、司祭が調べようとしてちぎり取ると大嵐がにわかに襲い国じゅうが突然暗黒に包まれるし、自分の指輪は包皮の形だと主張する聖女は出てくるし、包皮入り財布の模造品が中世ヨーロッパ各地で流行しちゃうし。
ぜひダン・ブラウンに読んでもらって、『ダ・ヴィンチ・コード』のノリで、キリストの包皮をめぐる大争奪戦を描いたスリリングで(さっと読める)小説を書いてもらいたい!
となると、ヒーロー・ラングトン教授とヒロインは、途中で日本の秘宝館に迷い込むというシーンが必要だ。秘宝館は、一九六九年に徳島につくられたものがもっとも古いのだが、「秘宝館」の語彙が普及したのは一九七八年以降。「11PM」に「元祖国際秘宝館」の館長が出演して注目されたことが大きかったらしい。というのは、井上章一&関西性欲研究会『性の用語集』(講談社現代新書/八六〇円)からのネタ。性に関する言葉の歴史をまとめた本書は、「ボボ・ブラジル」という名に潜む差別や、「猫をかぶる」の語源にちんこが絡んでくる珍説(でも説得力がある)など、51項目、どこからでも読めて楽しい。
池田清彦『生きる力、死ぬ能力』(弘文堂/一六〇〇円)は、生と死に関する生物学の書。講演の採録かと思わせる文体で読みやすい。第二部は、「構造主義生物学とは何か?」という内容の個人史を交えたインタビューで、清彦入門に最適だ。
この本に登場するアンテキヌスというフクロネズミの一種は、交尾を始めると無我夢中でやりつづけ、急激に老化して、交尾しながら死んでしまう。セックスイズデッドなライフなのだ。そういった例をあげながら、生物の進化や「生きる」というシステムを解説していく。生物というシステムは、どんどん変化してしまうものだが、それだと、とっちらかってクチュクチュバーンしてしまってまずい。そこで遺伝子が保守的に抑えているのだという考え方が面白い。遺伝子によって自分が操作されているように感じられる生物学と見かたが逆なんである。
で、今月最大のオススメは、柳父章『近代日本語の思想 翻訳文体成立事情』(法政大学出版/二五〇〇円)。目からウロコ落下枚数では、ここ数年最多。
もともと日本語には主語などなくて、明治期、翻訳によって「主語」がつくられたというのだ。日本文化の伝統では、「主語」は発言されず、秘められていたのだけど、翻訳という異文化の侵入のために「主語」が生み出され、「文(センテンス)」が作りださられた。しかし、日本の伝統もしぶとく、「主語」じたいに不透明な陰を組み込み、文に「秘」の仕組みを作ったのだ!
などと要約して紹介すると、強引な印象を受けるかもしれない。たしかに、後半の三章は、駆け足すぎてアクロバティックな感じもするのだけど(←でも、そういう所も十分面白い)、大日本帝国憲法の翻訳を例にあげ、さらに夏目漱石、志賀直哉、谷崎潤一郎などの文章から、新しい文体が生み出される経緯を具体的に例示し展開していく論は説得力がある。へぇ『吾輩は猫である』ってそんなふうに面白かったんだぁ? としみじみ感じられるような目ウロコ本、大推薦。
『吾輩は猫である』の文体の謎に迫る本をもう一冊。清水義範『漱石先生大いに悩む』(小学館一二〇〇円)は、夏目漱石のものと思われる手紙を「私」が手に入れて調べ始める「虚の章」と、漱石が『吾輩は猫である』を書く頃の「実の章」を交互に描く。楽しく読めて、漱石さんの秘密を、ちょっと知ってしまいました……みたいな読後感が、いい。
町山智浩『USAカニバケツ』(太田出版/一四八〇円)は、アメリカの犯罪やスポーツ、芸能、TV番組からアメリカを覗き込むコラム集。浮浪者にギャラを与えてお互いに殴り合わせたアングラビデオの話や、チャック・パラニュークの父親惨殺事件、裁判生中継チャンネル、マイケル・ジャクソンの栄枯盛衰など、ぎっしり約百本、ちんこも生も死も何もかも、ぎゅー詰め! すっげー面白い。
最後に漫画だけど、ぞわぞわするので紹介。河井克夫『日本の実話』(青林工藝舎/一五〇〇円)は、体験談漫画集。中国のカラオケマッサージという奇怪なサービスを描いた話、人妻マニアの夫と人妻としてメールを交わしてしまう妻の顛末、尻の匂いで彼女ができた男のエピソードなどなど。都市伝説が含有するいかがわしさとリアルさを持つ体験談が二十六本。虚実の狭間をふらふらと泳ぐようなスタイルがたまりません。
【この読書日記が収録されている書籍】
という枕で紹介するのは、デビッド・フリードマン『ペニスの歴史 男の神話の物語』(井上廣美訳 原書房/二八〇〇円)。古代神話から勃起産業までの長いペニスの歴史を紹介している本であり、「人間とペニスの思想史」として真剣に読むこともできちゃいますが、「ちんこトリビア本」として楽しんじゃっても可。
話は、古代エジプトの創造神アトゥム(私は私のこぶしと交わり世界を創造したとか言い出しちゃう豪の者)から始まり、ダ・ヴィンチのちんこ研究、包皮縫合や尿道電極といった恐怖の自慰行為防止策、サルの睾丸移植や人工陰茎や勃起薬など、驚愕のネタが満載。特に偉人に関するちんこ発言や事件は、偉人であればあるほど、ちんことのコラボレーション(略してチンコラ)の妙が際立っちゃう。
キリスト教のチンコラも強烈で、イエスが割礼で取っちゃったちんこの皮は、唯一地上に残っている彼の肉体だってことで、もう教会の人たちおおさわぎ。十以上の教会が「聖なる包皮」を持っていると主張、鑑定家が出現して味見テスト。ぺぺぺっ。記録にある話では、包皮からはこの上ない芳香が放たれるし、司祭が調べようとしてちぎり取ると大嵐がにわかに襲い国じゅうが突然暗黒に包まれるし、自分の指輪は包皮の形だと主張する聖女は出てくるし、包皮入り財布の模造品が中世ヨーロッパ各地で流行しちゃうし。
ぜひダン・ブラウンに読んでもらって、『ダ・ヴィンチ・コード』のノリで、キリストの包皮をめぐる大争奪戦を描いたスリリングで(さっと読める)小説を書いてもらいたい!
となると、ヒーロー・ラングトン教授とヒロインは、途中で日本の秘宝館に迷い込むというシーンが必要だ。秘宝館は、一九六九年に徳島につくられたものがもっとも古いのだが、「秘宝館」の語彙が普及したのは一九七八年以降。「11PM」に「元祖国際秘宝館」の館長が出演して注目されたことが大きかったらしい。というのは、井上章一&関西性欲研究会『性の用語集』(講談社現代新書/八六〇円)からのネタ。性に関する言葉の歴史をまとめた本書は、「ボボ・ブラジル」という名に潜む差別や、「猫をかぶる」の語源にちんこが絡んでくる珍説(でも説得力がある)など、51項目、どこからでも読めて楽しい。
池田清彦『生きる力、死ぬ能力』(弘文堂/一六〇〇円)は、生と死に関する生物学の書。講演の採録かと思わせる文体で読みやすい。第二部は、「構造主義生物学とは何か?」という内容の個人史を交えたインタビューで、清彦入門に最適だ。
この本に登場するアンテキヌスというフクロネズミの一種は、交尾を始めると無我夢中でやりつづけ、急激に老化して、交尾しながら死んでしまう。セックスイズデッドなライフなのだ。そういった例をあげながら、生物の進化や「生きる」というシステムを解説していく。生物というシステムは、どんどん変化してしまうものだが、それだと、とっちらかってクチュクチュバーンしてしまってまずい。そこで遺伝子が保守的に抑えているのだという考え方が面白い。遺伝子によって自分が操作されているように感じられる生物学と見かたが逆なんである。
で、今月最大のオススメは、柳父章『近代日本語の思想 翻訳文体成立事情』(法政大学出版/二五〇〇円)。目からウロコ落下枚数では、ここ数年最多。
もともと日本語には主語などなくて、明治期、翻訳によって「主語」がつくられたというのだ。日本文化の伝統では、「主語」は発言されず、秘められていたのだけど、翻訳という異文化の侵入のために「主語」が生み出され、「文(センテンス)」が作りださられた。しかし、日本の伝統もしぶとく、「主語」じたいに不透明な陰を組み込み、文に「秘」の仕組みを作ったのだ!
などと要約して紹介すると、強引な印象を受けるかもしれない。たしかに、後半の三章は、駆け足すぎてアクロバティックな感じもするのだけど(←でも、そういう所も十分面白い)、大日本帝国憲法の翻訳を例にあげ、さらに夏目漱石、志賀直哉、谷崎潤一郎などの文章から、新しい文体が生み出される経緯を具体的に例示し展開していく論は説得力がある。へぇ『吾輩は猫である』ってそんなふうに面白かったんだぁ? としみじみ感じられるような目ウロコ本、大推薦。
『吾輩は猫である』の文体の謎に迫る本をもう一冊。清水義範『漱石先生大いに悩む』(小学館一二〇〇円)は、夏目漱石のものと思われる手紙を「私」が手に入れて調べ始める「虚の章」と、漱石が『吾輩は猫である』を書く頃の「実の章」を交互に描く。楽しく読めて、漱石さんの秘密を、ちょっと知ってしまいました……みたいな読後感が、いい。
町山智浩『USAカニバケツ』(太田出版/一四八〇円)は、アメリカの犯罪やスポーツ、芸能、TV番組からアメリカを覗き込むコラム集。浮浪者にギャラを与えてお互いに殴り合わせたアングラビデオの話や、チャック・パラニュークの父親惨殺事件、裁判生中継チャンネル、マイケル・ジャクソンの栄枯盛衰など、ぎっしり約百本、ちんこも生も死も何もかも、ぎゅー詰め! すっげー面白い。
最後に漫画だけど、ぞわぞわするので紹介。河井克夫『日本の実話』(青林工藝舎/一五〇〇円)は、体験談漫画集。中国のカラオケマッサージという奇怪なサービスを描いた話、人妻マニアの夫と人妻としてメールを交わしてしまう妻の顛末、尻の匂いで彼女ができた男のエピソードなどなど。都市伝説が含有するいかがわしさとリアルさを持つ体験談が二十六本。虚実の狭間をふらふらと泳ぐようなスタイルがたまりません。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする