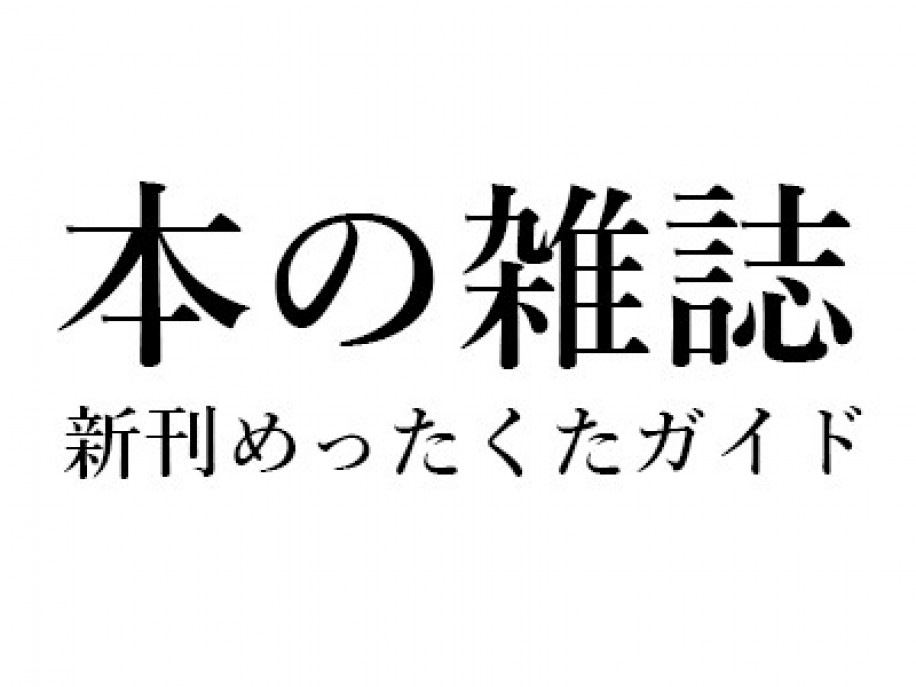書評
『構造主義と進化論』(海鳴社)
明快かつ豪放なおもしろさ。しっかりものを考える確かな足取りについていくだけでも、ハイキングで見晴らし台に立てたような爽快感を味わえる。進化論や生物学に縁のうすい読者でも、科学という営みの哲学的なありかにいろいろ思い当たることがあるはずで、有益このうえない。
圧巻はまず、ギリシャ哲学を扱うかわきりの第一章。ここだけで、木戸銭(二二〇〇円余り)は元が取れたも同然だ。
著者池田氏は、科学の本質からおもむろに説きおこす。科学とは、現象(変なるもの)を、なんらかの形式(不変なるもの)によって、コード化するものだ。これには当然、無理がともなう。ゆえにわれわれは、形式(たとえば名辞)と独立に、時間がその外側を流れていく、というふうに理解するのだー。
だいたいこんな枠組みに乗せて、池田氏は、タレス、アナクシマンドロスから、デモクリトスを経て、アリストテレスにいたるギリシャ自然哲学の滔々たる歩みを概説する。古代の学者たちの大胆な洞察と、その論理必然的な行き詰まり。それが再び、つぎの洞察をうみ……という、知のダイナミズムが脈動する。
*
ギリシャ哲学が進化論に、何の関係があるんだろう、といぶかるなかれ。《本書は「構造主義」という時間とは最も無縁なものと、「進化」という時間に最も関係深いものを架橋しようとする試み》(五頁)なのだ。時間とコード(遺伝子、種、もそうである)との関係を、原理上突き詰めたのが、ギリシャ哲学なのだから。
つぎに池田氏が目を転ずるのが、ラマルク、ダーウィン、メンデルといった、進化論、遺伝学説のおおどころである。
古典は、後世の相当いい加減な解釈に汚染されているのが常だ。その例にもれず、上記三人の思想も、慎重な磨き出しが必要である。その手がかりが、フーコーの『言葉と物』(新潮社)。十七~十八世紀古典主義時代のエピステーメーと、十九世紀(われわれの時代)のエピステーメーの、断層をきちんと踏まえることが重要になる。
たとえば、用不用説で有名なラマルクだが、実はこれは補助仮説にすぎない。彼の進化論の正体は《進化時空間斉一説とでも呼ぶべきもの》(七四頁)、つまり、生物は自然発生する端から、分岐せず等速で進化を続ける、という説なのだ。いっぽう、一九世紀のエピステーメーを体現するダーウィンの学説の要点は、池田氏によると、《自然選択説という論理形式を記述することにより、「生物」と「進化」が実はトートロジーであることを発見した》(一一〇頁)ところにある。『種の起源』は、ネオ・ダーウィニズムの単純な教条などには収まりきらない、生命現象の洞察にみちた多義的な書物なのだ。
メンデルも同様である。彼の考えた「エレメント」は、いわゆる遺伝子でなく、《形質発現のための原因の総体》(一四三頁)、つまり、池田氏のいう「構造」を含むものなのである。《天才的な科学者の常として、ダーウィンと同じようにメンデルもまた、彼自身の理論のなかにさまざまな可能性の萌芽を含蓄していた》(一四七頁)
*
進化論の古典学説に溯るのは、好事家の気まぐれでない。分子遺伝学が成功したおかげで、《DNA=遺伝子(複製子)=遺伝するすべて、という図式》(一七一頁)を大方の生物学者が信じこんでしまった。その図式が、根拠のない憶見にすぎないことを暴くためである。
さて、池田氏の唱える「構造主義進化論」はつぎのような、さしあたりの《理論的予測》(二一四頁)だ。まず、《生物固有の構造は物理化学法則を下位構造とする、その上位構造》(二一五頁)であると考える。しかも《上位構造のルールは必ず下位構造における可能性の限定であり……限定自体は必ず無根拠》(二一六頁)なのだ。無根拠な、つまり恣意的な構造によって現象を説明するところが、「構造主義」たるゆえんだ。
その構造だが、氏は、《真核生物のDNAの中には……全DNAの変化範囲を定めている特別な塩基配列(群)》(二二九頁)、つまり「安定化中枢遺伝子」が存在する、とまず仮定する。つぎに、安定化中枢それ自体を安定させる「保持遺伝子」の存在を、仮定する。さらに《全保持遺伝子の変化範囲を定めている遺伝子》(二四〇頁)、すなわち「P遺伝子」があり、それが最初の「安定化中枢遺伝子」に安定を保証されている、と仮定する。
この多段階の構造を考えると、生物の形態変化や進化を、かなりうまく説明できる。というより、《進化の一般理論は私がここでやっているのと同型になる他はないと私は思っている》(二四一頁)。論理的に考えて、それ以外の可能性がないからだ。
専門にわたる議論の細部を、私は判断しかねるが、大枠において大変説得的で有望な研究プランと思われた。このように大胆で刺戟的な議論が登場したことを喜びたい。社会学にとってさえ、示唆深い記述が数々ある。仮に本書の具体的な仮説が反証されてしまうようなことがあっても、本書の生命は永続する、とのべておこう。
【この書評が収録されている書籍】
圧巻はまず、ギリシャ哲学を扱うかわきりの第一章。ここだけで、木戸銭(二二〇〇円余り)は元が取れたも同然だ。
著者池田氏は、科学の本質からおもむろに説きおこす。科学とは、現象(変なるもの)を、なんらかの形式(不変なるもの)によって、コード化するものだ。これには当然、無理がともなう。ゆえにわれわれは、形式(たとえば名辞)と独立に、時間がその外側を流れていく、というふうに理解するのだー。
だいたいこんな枠組みに乗せて、池田氏は、タレス、アナクシマンドロスから、デモクリトスを経て、アリストテレスにいたるギリシャ自然哲学の滔々たる歩みを概説する。古代の学者たちの大胆な洞察と、その論理必然的な行き詰まり。それが再び、つぎの洞察をうみ……という、知のダイナミズムが脈動する。
*
ギリシャ哲学が進化論に、何の関係があるんだろう、といぶかるなかれ。《本書は「構造主義」という時間とは最も無縁なものと、「進化」という時間に最も関係深いものを架橋しようとする試み》(五頁)なのだ。時間とコード(遺伝子、種、もそうである)との関係を、原理上突き詰めたのが、ギリシャ哲学なのだから。
つぎに池田氏が目を転ずるのが、ラマルク、ダーウィン、メンデルといった、進化論、遺伝学説のおおどころである。
古典は、後世の相当いい加減な解釈に汚染されているのが常だ。その例にもれず、上記三人の思想も、慎重な磨き出しが必要である。その手がかりが、フーコーの『言葉と物』(新潮社)。十七~十八世紀古典主義時代のエピステーメーと、十九世紀(われわれの時代)のエピステーメーの、断層をきちんと踏まえることが重要になる。
たとえば、用不用説で有名なラマルクだが、実はこれは補助仮説にすぎない。彼の進化論の正体は《進化時空間斉一説とでも呼ぶべきもの》(七四頁)、つまり、生物は自然発生する端から、分岐せず等速で進化を続ける、という説なのだ。いっぽう、一九世紀のエピステーメーを体現するダーウィンの学説の要点は、池田氏によると、《自然選択説という論理形式を記述することにより、「生物」と「進化」が実はトートロジーであることを発見した》(一一〇頁)ところにある。『種の起源』は、ネオ・ダーウィニズムの単純な教条などには収まりきらない、生命現象の洞察にみちた多義的な書物なのだ。
メンデルも同様である。彼の考えた「エレメント」は、いわゆる遺伝子でなく、《形質発現のための原因の総体》(一四三頁)、つまり、池田氏のいう「構造」を含むものなのである。《天才的な科学者の常として、ダーウィンと同じようにメンデルもまた、彼自身の理論のなかにさまざまな可能性の萌芽を含蓄していた》(一四七頁)
*
進化論の古典学説に溯るのは、好事家の気まぐれでない。分子遺伝学が成功したおかげで、《DNA=遺伝子(複製子)=遺伝するすべて、という図式》(一七一頁)を大方の生物学者が信じこんでしまった。その図式が、根拠のない憶見にすぎないことを暴くためである。
さて、池田氏の唱える「構造主義進化論」はつぎのような、さしあたりの《理論的予測》(二一四頁)だ。まず、《生物固有の構造は物理化学法則を下位構造とする、その上位構造》(二一五頁)であると考える。しかも《上位構造のルールは必ず下位構造における可能性の限定であり……限定自体は必ず無根拠》(二一六頁)なのだ。無根拠な、つまり恣意的な構造によって現象を説明するところが、「構造主義」たるゆえんだ。
その構造だが、氏は、《真核生物のDNAの中には……全DNAの変化範囲を定めている特別な塩基配列(群)》(二二九頁)、つまり「安定化中枢遺伝子」が存在する、とまず仮定する。つぎに、安定化中枢それ自体を安定させる「保持遺伝子」の存在を、仮定する。さらに《全保持遺伝子の変化範囲を定めている遺伝子》(二四〇頁)、すなわち「P遺伝子」があり、それが最初の「安定化中枢遺伝子」に安定を保証されている、と仮定する。
この多段階の構造を考えると、生物の形態変化や進化を、かなりうまく説明できる。というより、《進化の一般理論は私がここでやっているのと同型になる他はないと私は思っている》(二四一頁)。論理的に考えて、それ以外の可能性がないからだ。
専門にわたる議論の細部を、私は判断しかねるが、大枠において大変説得的で有望な研究プランと思われた。このように大胆で刺戟的な議論が登場したことを喜びたい。社会学にとってさえ、示唆深い記述が数々ある。仮に本書の具体的な仮説が反証されてしまうようなことがあっても、本書の生命は永続する、とのべておこう。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
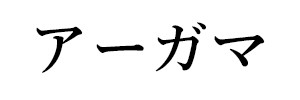
アーガマ(終刊) 1989年12月
ALL REVIEWSをフォローする