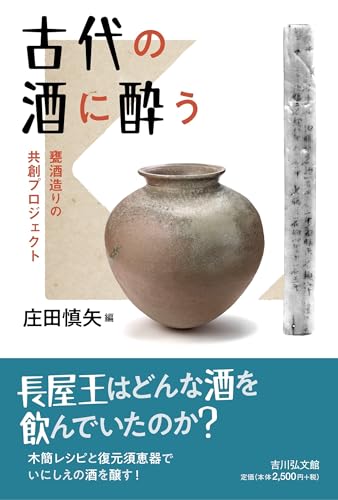書評
『歩くひと 完全版』(小学館)
めまぐるしく変化する世界の中で一歩ずつ「人間にもどる」
「完全版」と銘打ち、このたび刊行された『歩くひと』がすばらしい。本作は、谷口ジローが世界に羽ばたく契機となった記念碑的作品。ページをめくるたび、時空間のはざまに誘い込まれる読み心地を味わう。これといって派手な出来事やおかしな事件が起こるわけでもない。登場人物は、どこかで以前にすれ違ったことのあるような、眼鏡をかけた平凡な様子の男。気の向くまま、まちに溶け込んであっちへふらり、こっちへふらり、ひとり淡々と歩く。けれど、歩を進めれば空気の匂いが変わり、風景が変わり、目の前に現れる人間も建物も自然も変わる。その微細な変化を、ひとつひとつ掬(すく)い上げる谷口ジローの手つきから目が離せなくなり、いつのまにか自分もコマのなかに入り込んで「歩くひと」になっている……。「歩くひと」は『週刊モーニング』(講談社)の増刊『パーティー増刊』に連載した作品で、1990年から91年にかけて掲載された。平成二年、バブル景気終焉の年。天皇明仁の即位礼正殿の儀が皇居宮殿で執り行われ、TBS記者の秋山豊寛がソユーズTM―11で日本人初の宇宙飛行をし、年末に第二次海部改造内閣が発足。世界を見れば、東西に分裂していたドイツが再統一され、ベルリンが首都に復帰。そんな国内外の騒がしさを思うと、ただ歩くという「地味」な行為から離れることのない眼差しの強さがいっそう響いてくる。
連載当時、作者の「近況報告」が毎回掲載された。その文章が、別冊読本に再録されている。第1話「散歩礼賛」に寄せた文。
やっぱり歩くのはいい。車や自転車では見えないものも、歩いていれば、見えたり聞こえたりする。歩くのは楽しい。歩いていると、なんだか人間にもどれそうな気がするのは、僕だけだろうか。
「歩くひと」を描きながら、多忙な日々のなか、自身も深呼吸していたのだろう。ペン先の動きと足の動きがぴたりと呼吸を重ねる感覚が伝わってくるのは、きっとそのためなのだ。十七話いずれも、二本の足を自分で動かす意思によって、コマは進められてゆく。
また、別冊読本では、当時の担当編集者、講談社OBのY・T氏が、「歩くひと」というタイトルはあらかじめ先にあったと明かしている。ひな型はフランク・ペリー監督の映画「泳ぐひと」。バート・ランカスターが演じる主人公が次々とプールを泳いでいく作品から「歩くひと」の着想が生まれたと知って、なるほど映画的な時間が流れているのはそういうわけだったのか、と膝を叩いた。まあそもそも、歩くひとはつねに世界の主人公であるわけだけれど。
淡々と歩きながら、ときおり描かれる破綻に強烈に惹かれる。とつぜん降り始める雪。激しい夕立。しのびこんだプールに飛び込む裸体。散った桜の花の絨毯(じゅうたん)の上で現れた女人の記憶……日常のなかのひそやかな揺らぎが、ぱっくりと世界を割ってみせる。夜のまちを徘徊し、見知らぬ屋上で「歩くひと」が咆哮するとき、読者は、あらゆるしがらみが剝がれ落ちる感覚を共有するのだ。
造本は、左右のページのノドが全開になる糸綴(いととじ)並製本。糸綴の背がそのまま見える仮製本様式とともに、谷口ジローの世界にふかぶかと誘い込む。
ALL REVIEWSをフォローする