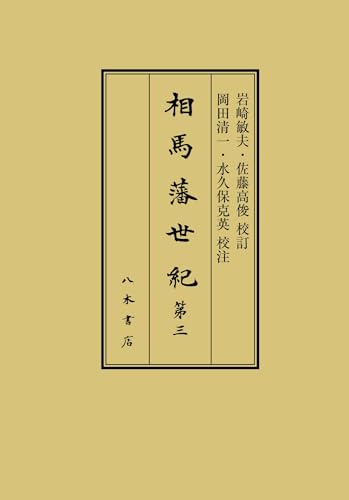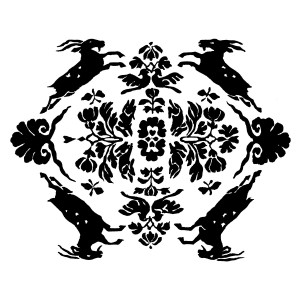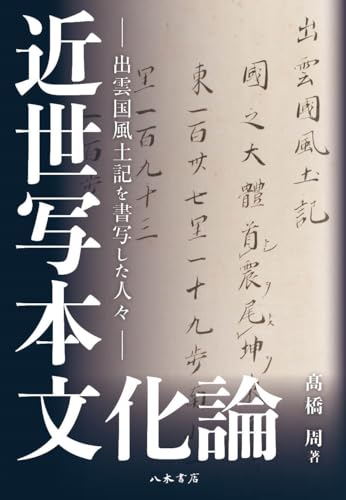自著解説
『相馬藩世紀 3』(八木書店出版部)
奥州中村城主(現在の福島県相馬市)相馬家の年譜を収める『相馬藩世紀(そうまはんせいき)』。23年ぶりに刊行された第三巻には、江戸中期の七代藩主・尊胤(たかたね)の治世を収録し、参勤交代や野馬追、江戸城での儀礼、領内の災害、将軍家の動向まで、大名の日常と幕府政治、地域社会が交差する具体的な出来事が細やかに記録されています。本書の概要と読みどころを、校注を担当した研究者がご紹介します。
江戸時代とはどのような時代か。それは将軍徳川家を頂点とする武士たちが権力を持ち支配していた時代です。ほかにも飢饉による農民たちの悲惨なイメージ、江戸文化にみられる庶民の艶やかなイメージなどもあり、多岐にわたり人によって捉え方が異なります。ただ、そこには身分制度が歴然と存在しました。身分によってそれぞれ社会があり、そこには人びとの暮らしがありました。
本書(『相馬藩世紀』)で中心的な対象となる大名も、武士身分になります。大名は、石高1万石以上の領国を支配する武士で、参勤交代により1年おきに江戸に住むことが義務づけられています。江戸では大名屋敷に住み、江戸城に登城して詰所に控え、年始や五節句などの儀式に参列します。一方、領内では大名の住む城を中心に、行政の多くが行われました。
本書は、奥州中村城主(現在の福島県相馬市)相馬家(石高六万石の大名)の年譜で、初代利胤(三胤・蜜胤)誕生の天正9年(1581)から15代誠胤没年の明治25年(1892)までの312年間を藩主ごとに編年形式で記録したものです。相馬家は、鎌倉時代から明治維新を迎えるまで当地方を支配しました。こうしたなか、政治、経済、社会、文化など、当地方をひとまとまりとした特質(独特な風土)が生まれています。そのもっとも顕著な例が「野馬追」ですが、現在、国指定重要無形民俗文化財「相馬野馬追」に引き継がれています。
相馬家の年譜は、これまで2冊刊行されています。今回の第三には、江戸時代中期の延享3年(1746)から宝暦4年(1754)までの七代藩主相馬尊胤の治世9年間が収録されています。尊胤は、五代昌胤の子で、六代叙胤(佐竹義処の子義珍)の養子に迎えられ、後に七代藩主となります。ちなみに、本書に登場する徳胤とその子恕胤は叙胤の子と孫で、徳胤は尊胤の養子に迎えられますが家督相続前に逝去、その子恕胤が八代藩主となります。福胤は昌胤の子、尊胤の弟です。将軍家では、前年から九代家重が就任するものの、実権は隠居して西ノ丸に入った大御所吉宗が掌握します。家重の嫡子は、後の十代家治です。
主な内容を挙げてみましょう。江戸屋敷の様子、参勤交代、野馬追や自然災害など領内の事項、領内の者の江戸での訴訟、誕生や縁組など近親者による祝儀、江戸城内でのふるまいを示す老中の通達、参詣供奉・御成警固や朝鮮通信使御用などの職務、幕府から出された触、徳川吉宗逝去による葬送儀礼や徳川家治の縁組など将軍家に関わる事項、将軍家への献上品、江戸で起きた事件、江戸の火事とその応対、他大名への贈答品、大名同士の養子縁組・婚姻と弔事、所替など隣領大名の動向、叙爵による禁裏との関係、地震など全国的なできごとがみられますが、当該期の資料を引用しており、信憑性は高いといえます。
さらに具体的にみていきましょう。延享3年は、尊胤五十歳誕生の祝に関する歌披講や近親者からの祝儀、武家諸法度の再触、老中に松平武元就任、紅葉山東照宮正遷宮、和国人参や朝鮮人参の専売。延享4年は、近くの大名屋敷の火事で外桜田上屋敷も類焼、桃園天皇即位、麻布善光寺出火による麻布中屋敷門塀焼失、江戸風邪流行、信濃国善光寺阿弥陀如来諸国巡行。延享5年(寛延元年改元)は、前年焼失の外桜田上屋敷新宅出来、朝鮮通信使帰りの鞍皆具御用、相馬昌胤二十一回忌、領内風雨大雨高波塩入田畑損毛。寛延2年は、恕胤具足初・祝儀、江戸風雨強く麻布中屋敷破損のほか浅草辺りや本所筋の洪水・昌平橋落下・小日向筋出水、領内熊川辺り風雨強く潰家出る、板倉勝承より陸奥国桑折代官所百姓騒動加勢依頼。寛延3年は、諸国人別改め触と届、徳川家光百回忌法要、恕胤が徳胤室の養子となる。寛延4年(宝暦元年)は、恕胤尊胤の嫡孫、徳川家治御袖留、越後国高田大地震、徳川吉宗没・葬送儀礼、領内大風雨による川々出水と破損田畑損毛、恕胤前髪取祝。宝暦2年は、徳胤室父の浅野吉長没、尊胤の外桜田門番勤、徳川吉宗霊前への石燈籠献納、徳胤没、恕胤嫡孫承祖となる、恕胤と青山幸道妹縁組、徳川家治疱瘡、恕胤叙爵讃岐守、鰊・数の子を食し死者数千人。宝暦3年は、徳川家治疱瘡快然、恕胤官位の口宣頂戴、徳川家治縁組、野宮定俊大納言勅許。宝暦4年は、麻布中屋敷付の下水普請、尊胤の桜田組防ぎ場就任、領内唐国漂流者の長崎着岸、火事の際のがさつ禁止令。
また、全体的に登城の際、大名の供で混雑するための人数制限など通達も多く出されています。祝儀に伴い、近親者同士および親戚関係の他大名の進物・返礼品も詳細に記されており、当時の大名生活の一端が垣間見えます。
本書は、その書名から当地方に限られた記録とみられがちですが、それだけではありません。大名の日常的な生活や空間、幕府への対応、さらに自然災害など、全国的なできごとや事件も詳細に記録されており、江戸時代をより深く知る手がかりになるものといえます。
[書き手]
岡田 清一(おかだ せいいち)
1947年生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士課程満期退学。
現在:東北福祉大学名誉教授[博士(文学)東北大学]
[主な著作]
「相馬文書の成立と発展」(『古文書研究』58、2004)
『中世東国の地域社会と歴史資料』(名著出版、2009)
『中世南奥羽の地域諸相』(汲古書院、2019)
『相馬一族の中世』(吉川弘文館、2024)
水久保 克英(みずくぼ かつひで)
1963年生まれ。法政大学大学院人文科学研究科日本史学専攻修士課程修了。
現在:福島県史学会役員、元南相馬市博物館学芸員
[主な著作]
『街道の日本史13 北茨城・磐城と相馬街道』吉川弘文館、2003)
「史料紹介『奥州中村藩泉家文書』」(『福島県立博物館紀要』17、2003)
「給人以下諸法度について」(『南相馬市博物館研究紀要』7、2005)
「嘉永七年奥州中村藩中郷海岸防備と『伺書』」(『南相馬市博物館研究紀要』11、2009)
「文久三年の奥州中村藩江戸警備と在郷給人郷士」(『福島史学研究』91、2013)
江戸時代の大名
江戸時代とはどのような時代か。それは将軍徳川家を頂点とする武士たちが権力を持ち支配していた時代です。ほかにも飢饉による農民たちの悲惨なイメージ、江戸文化にみられる庶民の艶やかなイメージなどもあり、多岐にわたり人によって捉え方が異なります。ただ、そこには身分制度が歴然と存在しました。身分によってそれぞれ社会があり、そこには人びとの暮らしがありました。本書(『相馬藩世紀』)で中心的な対象となる大名も、武士身分になります。大名は、石高1万石以上の領国を支配する武士で、参勤交代により1年おきに江戸に住むことが義務づけられています。江戸では大名屋敷に住み、江戸城に登城して詰所に控え、年始や五節句などの儀式に参列します。一方、領内では大名の住む城を中心に、行政の多くが行われました。
『相馬藩世紀』とは
本書は、奥州中村城主(現在の福島県相馬市)相馬家(石高六万石の大名)の年譜で、初代利胤(三胤・蜜胤)誕生の天正9年(1581)から15代誠胤没年の明治25年(1892)までの312年間を藩主ごとに編年形式で記録したものです。相馬家は、鎌倉時代から明治維新を迎えるまで当地方を支配しました。こうしたなか、政治、経済、社会、文化など、当地方をひとまとまりとした特質(独特な風土)が生まれています。そのもっとも顕著な例が「野馬追」ですが、現在、国指定重要無形民俗文化財「相馬野馬追」に引き継がれています。
『相馬藩世紀 第三』の概要
相馬家の年譜は、これまで2冊刊行されています。今回の第三には、江戸時代中期の延享3年(1746)から宝暦4年(1754)までの七代藩主相馬尊胤の治世9年間が収録されています。尊胤は、五代昌胤の子で、六代叙胤(佐竹義処の子義珍)の養子に迎えられ、後に七代藩主となります。ちなみに、本書に登場する徳胤とその子恕胤は叙胤の子と孫で、徳胤は尊胤の養子に迎えられますが家督相続前に逝去、その子恕胤が八代藩主となります。福胤は昌胤の子、尊胤の弟です。将軍家では、前年から九代家重が就任するものの、実権は隠居して西ノ丸に入った大御所吉宗が掌握します。家重の嫡子は、後の十代家治です。主な内容を挙げてみましょう。江戸屋敷の様子、参勤交代、野馬追や自然災害など領内の事項、領内の者の江戸での訴訟、誕生や縁組など近親者による祝儀、江戸城内でのふるまいを示す老中の通達、参詣供奉・御成警固や朝鮮通信使御用などの職務、幕府から出された触、徳川吉宗逝去による葬送儀礼や徳川家治の縁組など将軍家に関わる事項、将軍家への献上品、江戸で起きた事件、江戸の火事とその応対、他大名への贈答品、大名同士の養子縁組・婚姻と弔事、所替など隣領大名の動向、叙爵による禁裏との関係、地震など全国的なできごとがみられますが、当該期の資料を引用しており、信憑性は高いといえます。
『相馬藩世紀 第三』の主な事項
さらに具体的にみていきましょう。延享3年は、尊胤五十歳誕生の祝に関する歌披講や近親者からの祝儀、武家諸法度の再触、老中に松平武元就任、紅葉山東照宮正遷宮、和国人参や朝鮮人参の専売。延享4年は、近くの大名屋敷の火事で外桜田上屋敷も類焼、桃園天皇即位、麻布善光寺出火による麻布中屋敷門塀焼失、江戸風邪流行、信濃国善光寺阿弥陀如来諸国巡行。延享5年(寛延元年改元)は、前年焼失の外桜田上屋敷新宅出来、朝鮮通信使帰りの鞍皆具御用、相馬昌胤二十一回忌、領内風雨大雨高波塩入田畑損毛。寛延2年は、恕胤具足初・祝儀、江戸風雨強く麻布中屋敷破損のほか浅草辺りや本所筋の洪水・昌平橋落下・小日向筋出水、領内熊川辺り風雨強く潰家出る、板倉勝承より陸奥国桑折代官所百姓騒動加勢依頼。寛延3年は、諸国人別改め触と届、徳川家光百回忌法要、恕胤が徳胤室の養子となる。寛延4年(宝暦元年)は、恕胤尊胤の嫡孫、徳川家治御袖留、越後国高田大地震、徳川吉宗没・葬送儀礼、領内大風雨による川々出水と破損田畑損毛、恕胤前髪取祝。宝暦2年は、徳胤室父の浅野吉長没、尊胤の外桜田門番勤、徳川吉宗霊前への石燈籠献納、徳胤没、恕胤嫡孫承祖となる、恕胤と青山幸道妹縁組、徳川家治疱瘡、恕胤叙爵讃岐守、鰊・数の子を食し死者数千人。宝暦3年は、徳川家治疱瘡快然、恕胤官位の口宣頂戴、徳川家治縁組、野宮定俊大納言勅許。宝暦4年は、麻布中屋敷付の下水普請、尊胤の桜田組防ぎ場就任、領内唐国漂流者の長崎着岸、火事の際のがさつ禁止令。また、全体的に登城の際、大名の供で混雑するための人数制限など通達も多く出されています。祝儀に伴い、近親者同士および親戚関係の他大名の進物・返礼品も詳細に記されており、当時の大名生活の一端が垣間見えます。
本書は、その書名から当地方に限られた記録とみられがちですが、それだけではありません。大名の日常的な生活や空間、幕府への対応、さらに自然災害など、全国的なできごとや事件も詳細に記録されており、江戸時代をより深く知る手がかりになるものといえます。
[書き手]
岡田 清一(おかだ せいいち)
1947年生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士課程満期退学。
現在:東北福祉大学名誉教授[博士(文学)東北大学]
[主な著作]
「相馬文書の成立と発展」(『古文書研究』58、2004)
『中世東国の地域社会と歴史資料』(名著出版、2009)
『中世南奥羽の地域諸相』(汲古書院、2019)
『相馬一族の中世』(吉川弘文館、2024)
水久保 克英(みずくぼ かつひで)
1963年生まれ。法政大学大学院人文科学研究科日本史学専攻修士課程修了。
現在:福島県史学会役員、元南相馬市博物館学芸員
[主な著作]
『街道の日本史13 北茨城・磐城と相馬街道』吉川弘文館、2003)
「史料紹介『奥州中村藩泉家文書』」(『福島県立博物館紀要』17、2003)
「給人以下諸法度について」(『南相馬市博物館研究紀要』7、2005)
「嘉永七年奥州中村藩中郷海岸防備と『伺書』」(『南相馬市博物館研究紀要』11、2009)
「文久三年の奥州中村藩江戸警備と在郷給人郷士」(『福島史学研究』91、2013)
ALL REVIEWSをフォローする