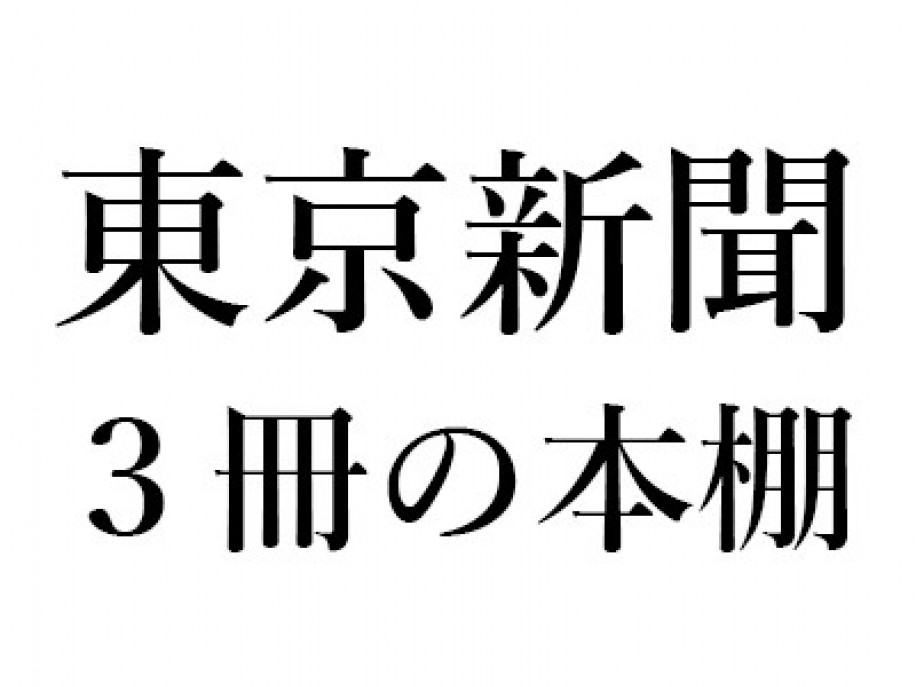対談・鼎談
『倫敦巴里』和田誠|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
丸谷 こういうふうな芸のある、遊び心のある言葉の使い方、これはある種の文学者たちを最も刺激するものだと思います。で、またそうでなければならないわけでしてね。近代日本文学の伝統ってものは、こういう言葉の使い方を否定するので、もし志賀直哉の弟子ならば、こういう言葉の使い方に対してはあくまでも反抗するのが正しいんですよ。
ここで思い出されるのは、赤塚不二夫という漫画家がいまして、『ギャグ・ゲリラ』って「週刊文春」に連載してる漫画がある。あの中で「王選手756号、おめでとう」っていう漫画を描いて、それが言葉遊びの連続なのね。たとえば、756号を記念して、町のご隠居さん二人が俳句をつくるときに、これから七・五・六でつくろうということになって「鐘が鳴るなり、柿食えば、後楽園」って俳句をつくるわけ。これは言葉遊びの最も漫画的な現われ方であって、日本文化の伝統をじつによく捉えてるとぼくは思うんです。
それでこの和田誠さんでしょう。三人とも絵描きでしょう。画家が言葉遊びにこれだけ遊ぶというのは、第一に文壇的迷信、言葉遊びを排撃する傾向に捉われていないということが第一の理由。第二に、絵というものは、常に色彩、線に還元して考えられるものである。それを文章に適用すれば、つねに言葉に還元される。線と色彩を歪曲するときにデフォルマシオンが生ずると同じように、言葉をちょっと直せば、言葉遊びが出てくる。当り前の話なんですが、日本のいまの漫画家たちは、日本文学に先んじた非常に前衛的なことをしているんじゃなかろうかと、まあ思ったんです。
山崎 わたくしが非常に唸らされたのは、なかでも映画のもじりでして、「兎と亀」でゴダールから黒沢明まで、古今東西の映画作家の作風をピタリと表現した。なかにはわたくしの見たことない監督もいて、無学を恥じなければならないのですけれども。
丸谷 見たことのない監督が、これを見てると全部見たような気がしてくる(笑)。
山崎 「兎と亀」でこれだけの話の筋がつくれるということは、芝居書きとしてシャッポを脱がざるを得ないですね。「兎と亀」というのは、最も単純な最も典型的な人間のドラマですから、それを素材にして作家の作風を浮かびあがらせるのは最もいい方法です。
木村 他人の文体とか、絵の描き方とかを、ちゃんと自分のものにしながら自分なりの判断とか批判も出しているでしょう。全体として、われわれが関心を持っているさまざまな事象というものに対する文明批評になっていますね。愉しくて恐ろしかった。
山崎 もちろん結果として、たいへんな文明批評になってるけど、おそらくこの筆者は、文明批評というようなことを最初に考えずに書いてると思うんだね。
木村 まったくそうですね、それが怖い。
山崎 これ見てて、ある種の恐怖感を感じたのは、ほかの漫画家の漫画によるパロディなんです。あんまりうますぎて、たとえば、トシコ・ムトー風というのをかくして、トシコ・ムトーがこれを書いたんだといわれて、そうじゃないといえる素人は、ほとんどいないだろうと思う。
丸谷 要するにパロディというもののむずかしさというのはこれなんで、つまり、もとのものがやっぱり真面目くさってるものでないと、パロディにしにくいのね。
山崎 わたくしは、これが失敗作だといってるんじゃないんです。これを見てて思い出したのは、展覧会に便器を持ち出して『泉』という題をつけた、アメリカの大芸術家デュシャン。わたしは、デュシャンの回顧展というのをニューヨークで見たことがあるんですが、彼は、若いときにあらゆるスタイルの絵を描いていたことがわかります。ほんとの写実、印象派風、フォーヴィズム、何でもある、どれもこれもうまい。おそらく一つポンと出せぱ、印象派の展覧会で二位とは下らない作品を描ける。その行き着く果てが、『泉』だったわけですね。何かそれがある種の現代の才能と栄光と不幸という感じがするでしょう。
丸谷 すでにダリって人が、そういう人なんでしょうね。
山崎 そうね。和田誠って人は、デュシャンの若いときであり、ダリだという感じがしますね。こんな才能があってこんなことがやれる人が、どうして自分というものをもち得るのか。これ、決して皮肉じゃないんですよ。非常に素直に、どうして自分のスタイルを確保し得るのか、不思議でしようがない。
丸谷 でも、ぼくがデュシャンとかダリとかいう、そういう男たちに感じる危険な感じ、不安定な感じ、そういうものを、和田誠に感じないのよね。とっても安定感の強い、付き合いいい生活人ですよ。
山崎 いや、わたくしはそれを聞いて、なおのこと納得がいくんです。わたくしがさっき不安だといったのは、何も本人が性格上不安定だなどということをいおうとしてるんじゃなくて、むしろそれは現代のもってる不安みたいなものでね。その中でダリは、やっぱり頭の上にウンコかなんか乗せて道化て見せなきゃならない状態に追いこまれたわけですよね。デュシャンはどうだったか知りませんけど、デュシャンは早くから筆を折ってますよね。回顧展を自分で開いた人ですから。ところが、二十一世紀があと四分の一というところへくると、そこで日常がまたもち直せるんですね。その感覚は非常によくわかる。
丸谷 この本の絵には動きがありますね。ぼくは、和田誠の絵はたいへん好きであるだけに、なおさらいいたいんだけども、この本の絵の生き生きとした動く感じ、これをちょっと思い出してもらいたい。最近の彼の絵はもっと静的なのね。敬愛するがゆえにあえて苦言を呈して、ロンパリ調で行ってもらいたいという気がするんです。
山崎 和田さん本人には、何の餌にもならない話ですけれども、こういう多彩なスタイルを股にかけながら安定していられるというのは、日本の伝統かもしれませんね。
一人の人間が漢詩をつくり、狂歌をつくり、和歌をつくり、私小説も書く。漢詩を読むと、もう世界は終わりだっていうような悲壮な感じが出る。狂歌なんかを見ると、何がどうなったって永遠に世界は安定しているように見える。それが一人の人間の心の中で何の矛盾もないわけですよ。そういうスタイルの使い分けっていうようなことについては、長い伝統をもっているわが民族なんですね。
木村 一方では欧米の技術文明をスパッとうまく取り入れて産業化を進めていき、もう一方ではあえかな文学の世界を説く、というふうにね(笑)。
山崎 ちゃんと義理人情で両方の辻褄を合わせたりね(笑)。
木村 そういう意味じゃ、和田さんはほんとうの日本人かもしれませんね。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ここで思い出されるのは、赤塚不二夫という漫画家がいまして、『ギャグ・ゲリラ』って「週刊文春」に連載してる漫画がある。あの中で「王選手756号、おめでとう」っていう漫画を描いて、それが言葉遊びの連続なのね。たとえば、756号を記念して、町のご隠居さん二人が俳句をつくるときに、これから七・五・六でつくろうということになって「鐘が鳴るなり、柿食えば、後楽園」って俳句をつくるわけ。これは言葉遊びの最も漫画的な現われ方であって、日本文化の伝統をじつによく捉えてるとぼくは思うんです。
それでこの和田誠さんでしょう。三人とも絵描きでしょう。画家が言葉遊びにこれだけ遊ぶというのは、第一に文壇的迷信、言葉遊びを排撃する傾向に捉われていないということが第一の理由。第二に、絵というものは、常に色彩、線に還元して考えられるものである。それを文章に適用すれば、つねに言葉に還元される。線と色彩を歪曲するときにデフォルマシオンが生ずると同じように、言葉をちょっと直せば、言葉遊びが出てくる。当り前の話なんですが、日本のいまの漫画家たちは、日本文学に先んじた非常に前衛的なことをしているんじゃなかろうかと、まあ思ったんです。
山崎 わたくしが非常に唸らされたのは、なかでも映画のもじりでして、「兎と亀」でゴダールから黒沢明まで、古今東西の映画作家の作風をピタリと表現した。なかにはわたくしの見たことない監督もいて、無学を恥じなければならないのですけれども。
丸谷 見たことのない監督が、これを見てると全部見たような気がしてくる(笑)。
山崎 「兎と亀」でこれだけの話の筋がつくれるということは、芝居書きとしてシャッポを脱がざるを得ないですね。「兎と亀」というのは、最も単純な最も典型的な人間のドラマですから、それを素材にして作家の作風を浮かびあがらせるのは最もいい方法です。
木村 他人の文体とか、絵の描き方とかを、ちゃんと自分のものにしながら自分なりの判断とか批判も出しているでしょう。全体として、われわれが関心を持っているさまざまな事象というものに対する文明批評になっていますね。愉しくて恐ろしかった。
山崎 もちろん結果として、たいへんな文明批評になってるけど、おそらくこの筆者は、文明批評というようなことを最初に考えずに書いてると思うんだね。
木村 まったくそうですね、それが怖い。
山崎 これ見てて、ある種の恐怖感を感じたのは、ほかの漫画家の漫画によるパロディなんです。あんまりうますぎて、たとえば、トシコ・ムトー風というのをかくして、トシコ・ムトーがこれを書いたんだといわれて、そうじゃないといえる素人は、ほとんどいないだろうと思う。
丸谷 要するにパロディというもののむずかしさというのはこれなんで、つまり、もとのものがやっぱり真面目くさってるものでないと、パロディにしにくいのね。
山崎 わたくしは、これが失敗作だといってるんじゃないんです。これを見てて思い出したのは、展覧会に便器を持ち出して『泉』という題をつけた、アメリカの大芸術家デュシャン。わたしは、デュシャンの回顧展というのをニューヨークで見たことがあるんですが、彼は、若いときにあらゆるスタイルの絵を描いていたことがわかります。ほんとの写実、印象派風、フォーヴィズム、何でもある、どれもこれもうまい。おそらく一つポンと出せぱ、印象派の展覧会で二位とは下らない作品を描ける。その行き着く果てが、『泉』だったわけですね。何かそれがある種の現代の才能と栄光と不幸という感じがするでしょう。
丸谷 すでにダリって人が、そういう人なんでしょうね。
山崎 そうね。和田誠って人は、デュシャンの若いときであり、ダリだという感じがしますね。こんな才能があってこんなことがやれる人が、どうして自分というものをもち得るのか。これ、決して皮肉じゃないんですよ。非常に素直に、どうして自分のスタイルを確保し得るのか、不思議でしようがない。
丸谷 でも、ぼくがデュシャンとかダリとかいう、そういう男たちに感じる危険な感じ、不安定な感じ、そういうものを、和田誠に感じないのよね。とっても安定感の強い、付き合いいい生活人ですよ。
山崎 いや、わたくしはそれを聞いて、なおのこと納得がいくんです。わたくしがさっき不安だといったのは、何も本人が性格上不安定だなどということをいおうとしてるんじゃなくて、むしろそれは現代のもってる不安みたいなものでね。その中でダリは、やっぱり頭の上にウンコかなんか乗せて道化て見せなきゃならない状態に追いこまれたわけですよね。デュシャンはどうだったか知りませんけど、デュシャンは早くから筆を折ってますよね。回顧展を自分で開いた人ですから。ところが、二十一世紀があと四分の一というところへくると、そこで日常がまたもち直せるんですね。その感覚は非常によくわかる。
丸谷 この本の絵には動きがありますね。ぼくは、和田誠の絵はたいへん好きであるだけに、なおさらいいたいんだけども、この本の絵の生き生きとした動く感じ、これをちょっと思い出してもらいたい。最近の彼の絵はもっと静的なのね。敬愛するがゆえにあえて苦言を呈して、ロンパリ調で行ってもらいたいという気がするんです。
山崎 和田さん本人には、何の餌にもならない話ですけれども、こういう多彩なスタイルを股にかけながら安定していられるというのは、日本の伝統かもしれませんね。
一人の人間が漢詩をつくり、狂歌をつくり、和歌をつくり、私小説も書く。漢詩を読むと、もう世界は終わりだっていうような悲壮な感じが出る。狂歌なんかを見ると、何がどうなったって永遠に世界は安定しているように見える。それが一人の人間の心の中で何の矛盾もないわけですよ。そういうスタイルの使い分けっていうようなことについては、長い伝統をもっているわが民族なんですね。
木村 一方では欧米の技術文明をスパッとうまく取り入れて産業化を進めていき、もう一方ではあえかな文学の世界を説く、というふうにね(笑)。
山崎 ちゃんと義理人情で両方の辻褄を合わせたりね(笑)。
木村 そういう意味じゃ、和田さんはほんとうの日本人かもしれませんね。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする