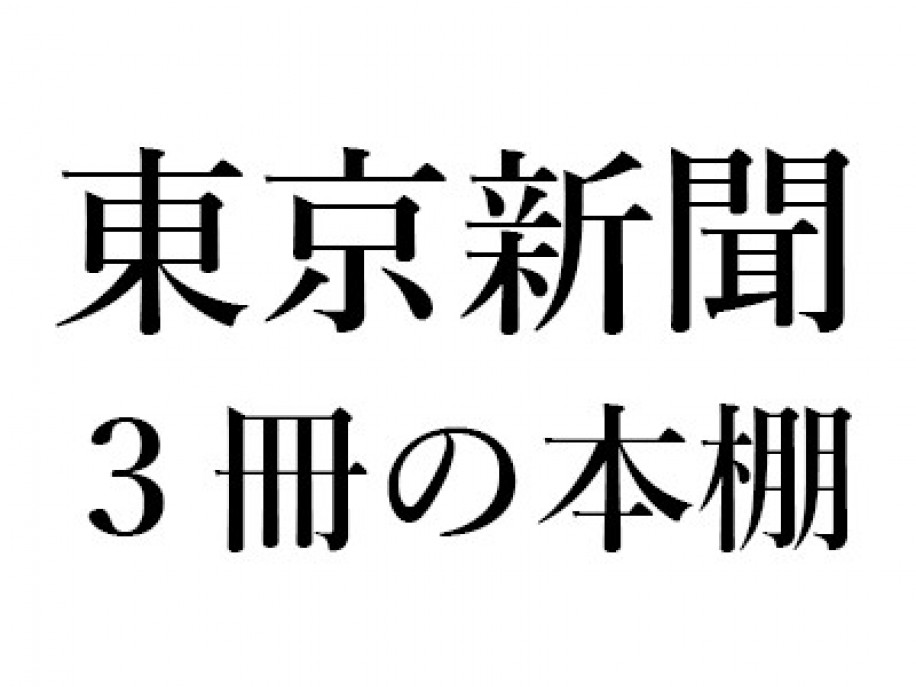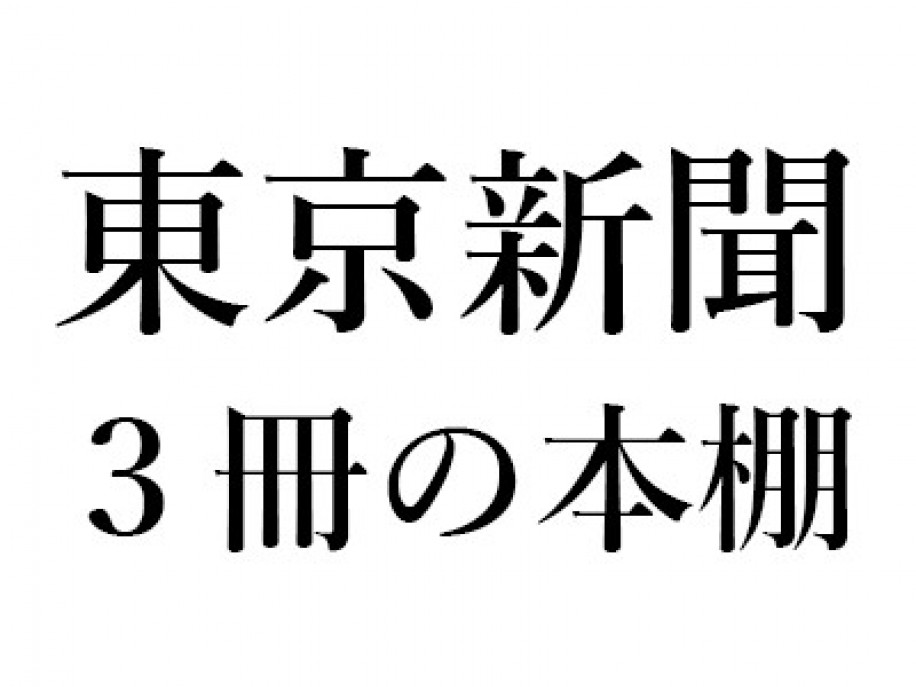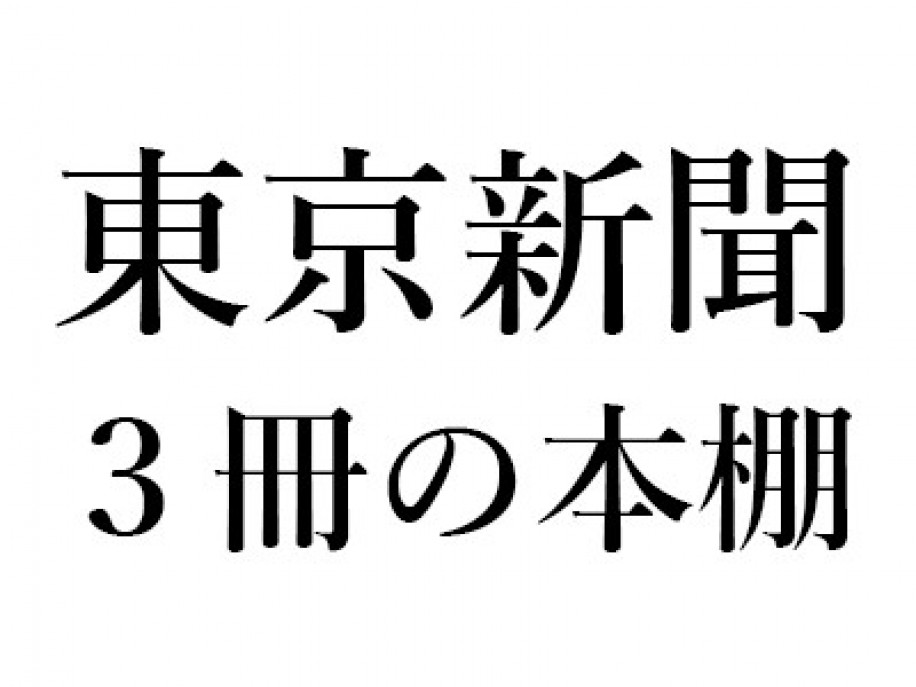読書日記
伊集院静『文字に美はありや。』(文藝春秋)、正岡子規『仰臥漫録』(岩波書店)、カート・ヴォネガット『国のない男』(中央公論新社)
文字に残る人の熱
三十代半ばで大学に入った際のことです。やる気十分で新しいノートを買いそろえましたが「も、文字が書けない!」…。この言葉には二つの意味があります。ひとつは筆圧が弱くなったこと。もうひとつは漢字を忘れてしまったこと。パソコンや携帯電話で文字を打つばかりになった結果でした。以降、ペンとノートを持ち歩き、思いついたこと、気になったことなどを意識的に書くようにしています。<1>伊集院静『文字に美はありや。』(文芸春秋・1,728円)。歴史に残る人々の名筆、名蹟(めいせき)から文字に美しい、美しくないということがあるのかを探った一冊。取り上げられる人物の実際の書が掲載され、エッセイとともに鑑賞できます。
第十八話「数奇な運命をたどった女性の手紙」で紹介される細川ガラシャと山内一豊(やまうちかずとよ)の妻の手紙を並べてみると、ガラシャの筆遣いの大胆さがわかります。読み難いのですが、書の流派を体得したガラシャの教養、当時の流行もあらわれている、と著者は説きます。一方、一豊の妻の文字はおおらかで読みやすい。美貌と悲しい最期が語り継がれるガラシャと、武士の妻の鑑(かがみ)とあがめられる一豊の妻。書に二人の運命が垣間見えるように思いました。
俳人正岡子規が死の直前までを綴(つづ)った<2>『仰臥漫録(ぎょうがまんろく)』(岩波文庫・583円)。日々の食事を中心に直筆の俳句、水彩画、墨絵が掲載されています。
以前、子規が最期を過ごした東京・根岸の「子規庵(あん)」を訪ねたとき、庭の糸瓜(へちま)棚を見ました。本書に収められた糸瓜棚の画は低い目線から描かれている。画には「病室前ノ糸瓜棚 臥シテ見ル所」とありました。子規が布団に仰向(あおむ)けで描く姿が浮かびます。先の『文字に美はありや。』にも子規の字を確認しました。夏目漱石が子規宛(あて)の手紙に自分の俳句をしたため、子規は丁寧に添削して送り返しました。友人子規を俳句の師とした漱石。二人の深い信頼関係が伝わってきます。
アメリカ文学を代表する作家、カート・ヴォネガットの<3>『国のない男』(金原瑞人訳、中公文庫・778円)には、一頁(ページ)丸ごと使ったヴォネガットの熱っぽい手書きのメッセージがいくつもあります。墓石らしい碑のイラストには「いまの地球は、どんな生き物にとっても絶望的だ」。本書の単行本は十年以上前に発売されましたが、いまだに切実な言葉です。
文字は書いた人の熱がいつまでも残り、読む者を熱くさせてくれます。
ALL REVIEWSをフォローする