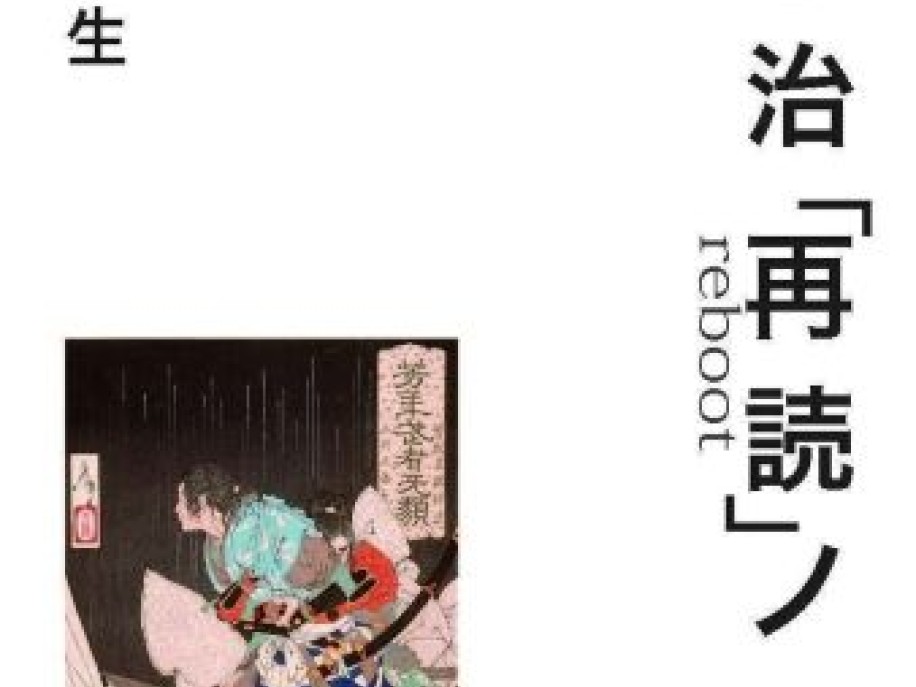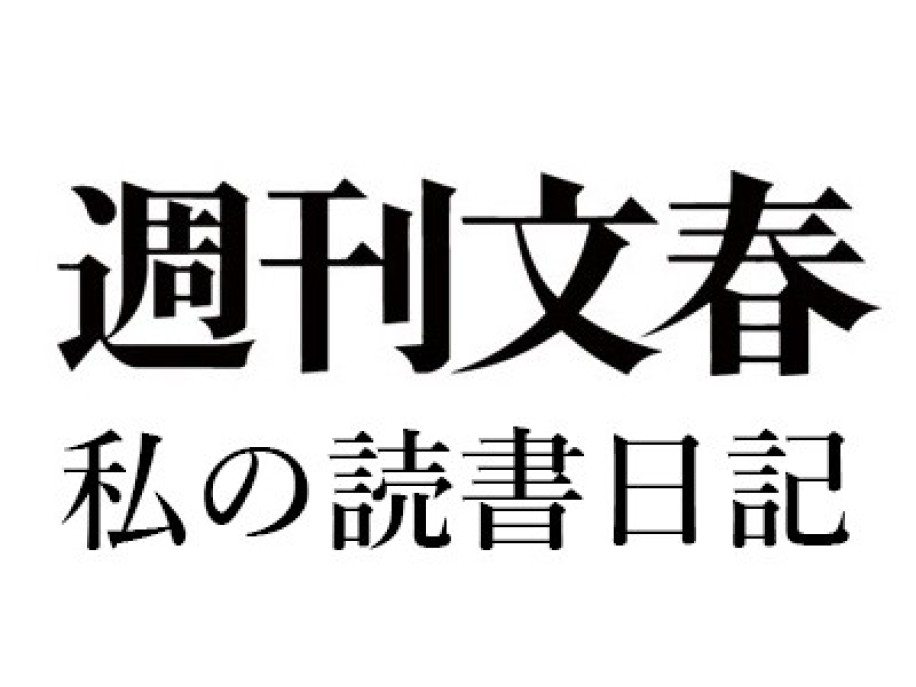読書日記
橋本治『思いつきで世界は進む』(筑摩書房)、山崎ナオコーラ『文豪 お墓まいり記』(文藝春秋)ほか
今年1月29日に橋本治が死去。享年70。各紙誌での訃報の扱いも大きく、影響の大きさを感じさせた。小説に始まり、エッセー、評論、美術論、古典の新訳と幅広く自在な活動を続けていた。
『思いつきで世界は進む』は、PR誌『ちくま』に2014年7月号から連載された時評50編を収録。「はじめに」に「遠い地平を俯瞰(ふかん)的に眺めて、想像力だけを地に下して現実を低く見る」と、時評するスタンスを説明している。
扱うテーマは、政治を中心に「東大卒のすごい人達」「忖度(そんたく)」「ボブディランのノーベル文学賞」「平成30年」など、ほとんど全方位。我々は「戦後」をまだ確立できていない。なぜなら、愚かな総理大臣が「あれほど恥知らずな論理矛盾」を犯して平気だから、と現政権への批判は鋭い。
データの借用や社会学者の説の引用は皆無。すべて自前で、考え抜くのが著者だった。複雑な問題も、真っすぐ一本の線を引くように論じる。 爽快な思想家だった。
墓を詣でる趣味を「掃苔(そうたい)」と呼ぶ。やや陰気で湿っぽいが、山崎ナオコーラ『文豪 お墓まいり記』は、雑談や寄り道ありきで楽しい散歩エッセーだ。
夏目漱石、永井荷風、谷崎潤一郎、太宰治、遠藤周作などの墓へ出かけ、花を手向け手を合わせる。作家案内の役目も担うが、「人生」への嫌悪感、食リポ、創作活動への迷い、死んだ父親の思い出と、頭の中は忙しい。
終戦前日、荷風が谷崎の疎開先・岡山を訪ねて食事をした。手土産は「肉」だったことを「最高の反戦活動」と著者は見る。澁澤龍彦の作品に触れ、「軽妙洒脱(しゃだつ)な死生観」と評するあたり、ちゃんと作家と向き合っている。漱石『こころ』批評も素晴らしい。
ところで、毎回のように掃苔のお伴をするのが書店員の夫君。エッセー『かわいい夫』に書くごとく夫婦とも「かわいい」。幸田文の墓で著者が「愛読しております」と言うと、夫はすかさず「本を売ります」。これには笑いました。
日比谷図書館資料課長だった池田信(あきら)が、生前に趣味で撮りためた2万点超えのネガプリント。『新装版 1960年代の東京』は、銀座を水路が巡り、路面を電車が走っていた都市が甦(よみがえ)る。佃島(つくだじま)には渡し舟、烏森(からすもり)には花街の名残、玉川上水にはなみなみと水があふれ、浅草国際通りから仁丹塔が見える。渋谷駅前は優雅でさえある。モノクロの力であろう。解説で松山巖は「六〇年代の東京の風景は、これほど静かで落ち着いていたのだろうか」と書く。記憶とともに消えていく町が愛(いと)おしい。
1978年生まれの加藤崇(たかし)の経歴はすごい。ヒト型ロボットのベンチャーを起こしたかと思うと、同社をグーグルに売却、単身渡米した。彼が今挑むのが、朽ちゆく水道管のインフラ整備だ。『クレイジーで行こう!』は、その悪戦苦闘と試行錯誤の1000日の記録。オンボロ住宅を拠点に、アメリカ人の相棒を得て、前人未到のチャレンジが始まった。著者にあったのは「志と有り余るバイタリティー、その場の判断能力」、そして「クレイジー」さだった。現代のサムライスピリットをそこに見る。
もうすぐ新しい「日本の象徴」が誕生する。根岸豊明『新天皇 若き日の肖像』は、元皇室担当テレビ記者が新米時代の1985年、イギリス留学中の浩宮に同行取材した時から始まる回想記。文庫書き下ろしである。オックスフォード駅頭、初対面の当時皇太子は、ジーンズをはいた心優しき青年であった。寮で友人たちと語らい、自由な空気を吸い、各国を歴訪。そこで「新天皇」は何を見て、何を語ったか。昭和天皇崩御、雅子さまとの結婚、そして現在へと、直近の目でつぶさに伝えられる。
『思いつきで世界は進む』は、PR誌『ちくま』に2014年7月号から連載された時評50編を収録。「はじめに」に「遠い地平を俯瞰(ふかん)的に眺めて、想像力だけを地に下して現実を低く見る」と、時評するスタンスを説明している。
扱うテーマは、政治を中心に「東大卒のすごい人達」「忖度(そんたく)」「ボブディランのノーベル文学賞」「平成30年」など、ほとんど全方位。我々は「戦後」をまだ確立できていない。なぜなら、愚かな総理大臣が「あれほど恥知らずな論理矛盾」を犯して平気だから、と現政権への批判は鋭い。
データの借用や社会学者の説の引用は皆無。すべて自前で、考え抜くのが著者だった。複雑な問題も、真っすぐ一本の線を引くように論じる。 爽快な思想家だった。
墓を詣でる趣味を「掃苔(そうたい)」と呼ぶ。やや陰気で湿っぽいが、山崎ナオコーラ『文豪 お墓まいり記』は、雑談や寄り道ありきで楽しい散歩エッセーだ。
夏目漱石、永井荷風、谷崎潤一郎、太宰治、遠藤周作などの墓へ出かけ、花を手向け手を合わせる。作家案内の役目も担うが、「人生」への嫌悪感、食リポ、創作活動への迷い、死んだ父親の思い出と、頭の中は忙しい。
終戦前日、荷風が谷崎の疎開先・岡山を訪ねて食事をした。手土産は「肉」だったことを「最高の反戦活動」と著者は見る。澁澤龍彦の作品に触れ、「軽妙洒脱(しゃだつ)な死生観」と評するあたり、ちゃんと作家と向き合っている。漱石『こころ』批評も素晴らしい。
ところで、毎回のように掃苔のお伴をするのが書店員の夫君。エッセー『かわいい夫』に書くごとく夫婦とも「かわいい」。幸田文の墓で著者が「愛読しております」と言うと、夫はすかさず「本を売ります」。これには笑いました。
日比谷図書館資料課長だった池田信(あきら)が、生前に趣味で撮りためた2万点超えのネガプリント。『新装版 1960年代の東京』は、銀座を水路が巡り、路面を電車が走っていた都市が甦(よみがえ)る。佃島(つくだじま)には渡し舟、烏森(からすもり)には花街の名残、玉川上水にはなみなみと水があふれ、浅草国際通りから仁丹塔が見える。渋谷駅前は優雅でさえある。モノクロの力であろう。解説で松山巖は「六〇年代の東京の風景は、これほど静かで落ち着いていたのだろうか」と書く。記憶とともに消えていく町が愛(いと)おしい。
1978年生まれの加藤崇(たかし)の経歴はすごい。ヒト型ロボットのベンチャーを起こしたかと思うと、同社をグーグルに売却、単身渡米した。彼が今挑むのが、朽ちゆく水道管のインフラ整備だ。『クレイジーで行こう!』は、その悪戦苦闘と試行錯誤の1000日の記録。オンボロ住宅を拠点に、アメリカ人の相棒を得て、前人未到のチャレンジが始まった。著者にあったのは「志と有り余るバイタリティー、その場の判断能力」、そして「クレイジー」さだった。現代のサムライスピリットをそこに見る。
もうすぐ新しい「日本の象徴」が誕生する。根岸豊明『新天皇 若き日の肖像』は、元皇室担当テレビ記者が新米時代の1985年、イギリス留学中の浩宮に同行取材した時から始まる回想記。文庫書き下ろしである。オックスフォード駅頭、初対面の当時皇太子は、ジーンズをはいた心優しき青年であった。寮で友人たちと語らい、自由な空気を吸い、各国を歴訪。そこで「新天皇」は何を見て、何を語ったか。昭和天皇崩御、雅子さまとの結婚、そして現在へと、直近の目でつぶさに伝えられる。
ALL REVIEWSをフォローする