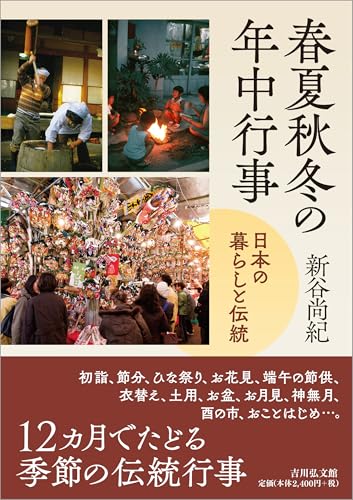読書日記
原田マハ『常設展示室』(新潮社)、木下直之『動物園巡礼』(東京大学出版会)、小松左京『やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記』(新潮社)
「見せる」という思惑
美術館、博物館、動物園、水族館。その手の、何かを見るための施設が私は苦手なのですが、短編集〔1〕原田マハ『常設展示室』(新潮社・1,512円)を読んでいたら、美術館に行きたくなってきました。主人公は、懸命に生きる女性たち。一枚の絵に出会うことによって、彼女たちは目覚め、気づき、そして振り返ります。一冊の本によって人生が変わることがありますが、絵もまた同じ力を持つと教えてくれるこれらの物語の佇(たたず)まいも、名画のように静謐(せいひつ)なのでした。
「さあ見ろ」と言われると見る気がうせるという天邪鬼(あまのじゃく)な性格のせいで、その手の施設に行かない私。動物園はさらに、限られた場所で人間に飼育される動物を見ると胸が痛むという理由もあって、苦手です。
〔2〕木下直之『動物園巡礼』(東京大学出版会・3,024円)は、さまざまな動物園を巡りつつ、動物園の過去、現在、未来をも巡る書。動物園の動物達(たち)は、動物園で生まれ育つケースがほとんどで、野生動物を連れてくるケースは少ないこと。種の保存という意味でも、動物園は大きな役割を担っていること…。と、眺めているだけではわからない動物園事情の数々が示されます。
動物を展示することの意義を重視するが故に動物園が背負うのは、動物の幸福には少々目をつぶるという「業」だと、著者は記します。第二次大戦中は、各地の動物園で動物たちを殺さなくてはならなかったわけですが、それもまた人間の都合。動物園から見えてくるのは、飼育する側の人間の姿でもあることをこの本は示すのであり、人間の業が見えすぎるから、私は動物園が苦手なのかもしれません。
「見せる」ための一大イベントである万博が大阪で開催されることが決まりましたが、SF作家の小松左京が、1970年の大阪万博にブレーンとして関わっていたことを、〔3〕小松左京『やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記』(新潮文庫・680円)で知りました。私的な万博の研究会を作っていた小松達は、万博のビジョンを考えるようになります。
この本の前半は、戦争中に学生時代を過ごした記録ですが、そのような時代に青春を送ったからこそ、著者は万博で日本を世界にどのように「見せる」かを、懸命に考えたのではないか。
ALL REVIEWSをフォローする