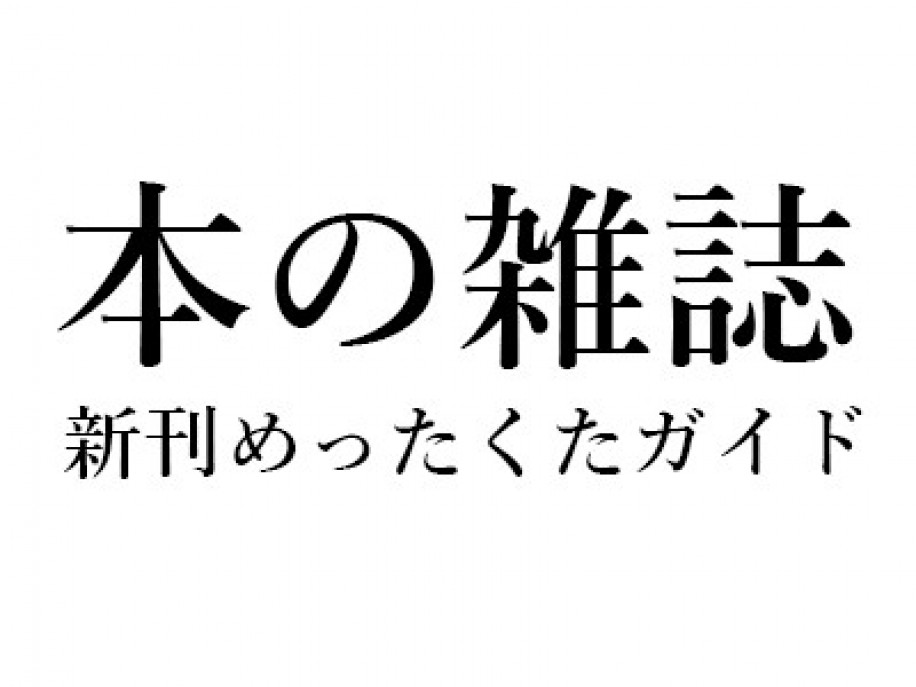読書日記
又吉直樹『劇場』(新潮社)、大竹昭子『間取りと妄想』(亜紀書房)、今村夏子『星の子』(朝日新聞出版)、深谷かほる『夜廻り猫』(講談社)
読書仲間と話したとき「ダメ男小説だよね」と安直に言ってしまったのだけど、又吉直樹『劇場』(新潮社一三〇〇円)は、読み終えてしばらく経った今、ある種の恐怖小説なのではないかという気がしている。
語り手の永田は、道を歩くときでも「ただ歩く」ということができない。「僕の肉体は明治通りを南へ歩いて行くようだったけど、一向に止まる気配を見せなかった」「歩かなければいけない理由があったのかというと、そんなものもなく、かといって止まらなければいけない理由も特になかったので歩き続けることしか思いつかなかった」というように、ただそれだけのことを逐一言語化する。無意識に歩くことを自分に許さないかのようだ。無名の劇団を主催している永田は、女優を目指して青森から上京してきた女子大生・沙希と一緒に暮らしている。「靴、同じやな」と、違う靴を履いている沙希に声をかけたことから始まった関係だが、彼女をひと目見たときの思い込みがすごい。「その人が幼かった頃から今日までに、どのような生活を送り、どのように容貌を変貌させてきたのかがわかった。これは、気のせいではなかった」と内心で断言するのだ。しかし口から出てくる言葉はしどろもどろでとんちんかん。なのに沙希は永田にアイスコーヒーをごちそうする。な、なぜ……? 彼女は奇妙な人・もの・ことを面白がれる女性だった、としか解釈のしようがない。沙希のそんな稀有なすこやかさは、永田によってすこしずつ削り取られ損なわれてゆく。
沙希が男子学生からもらって来た原付を破壊したり、偶然同じ雑誌を買っていたことが分かっただけで腹を立てたり、実は永田は典型的なDV男だ。彼の沙希への態度を非難するある人物に永田が送るメールの、攻撃的で独善的な文面には身震いがする。そもそも、自分がいかに自分の大事な人を大事にせずだめにしたか、を語りたい欲望というのはかなり怖い。エクスキューズが詰まったラストシーンはほとんどホラーだ。ああもう、うっかり感動させちゃうところがDV男の巧さだよ……。
永田が、アパートの一室を舞台に、そこに住んだ人々のエピソードを時系列でなく連ねていく芝居を書こうと考える場面がある。お、これは去年、谷崎潤一郎賞を受賞した長嶋有の『三の隣は五号室』(中央公論新社一四〇〇円)のようではないか。部屋といえば今月はこんな小説も紹介したい。間取りを起点とする13の物語が収録されている、大竹昭子『間取りと妄想』(亜紀書房一四〇〇円)。冒頭に置かれている「図」にまず見入ってしまう。間取り図ほどリアルな夢を見させてくれるものって、そうそうないですよねえ。ここに住むとしたら……と想像して物語に入ると、酩酊するような心地になったり、そう使うのか、と意表をつかれたりしていちいち楽しい。中でもぞくぞくさせられたのは、数学の女教師ミツコ(あえてここは「女」をつけたい)の話だ。勤めていた高校をやめ、世界一周旅行から帰って来た彼女は、塾を開こうと家探しをする。見つけたのは、中庭を挟んで独立した2つの部屋がありダイニングに1メートルのカウンターが設えられている、理想ど真ん中の物件。ミツコはこのカウンターを使って、生徒と向き合うかたちで(つまり「お店みたいな雰囲気で」)教えようと考える。〈そうすれば妄想が浮かんでも、手足の動きが阻まれ実行に及ぶことは避けられるだろう〉と。ミツコはあることに〈手を貸してやりたくなる〉性分だったのだ──。
平凡な独身女性事務員が、ひとり暮らしの自宅の隠し部屋に入ると別人になる物語も面白かった。「この家でなければならない」家に住んでいる人は幸せだなあと思う。かろやかに住み替えることのできる人も。
こちらの物語の主人公の家族は致しかたなく家を替え続けなければならなかった。今村夏子『星の子』(朝日新聞出版一四〇〇円)。少女ちひろの両親は「特別な生命力を宿した水」を知人に薦められたことがきっかけで、怪しげな宗教にのめりこむ。途方に暮れるほどひどかったちひろの湿疹が治ったのは、その水のおかげだと信じ込んだのだ。白いタオルを頭に乗せ、ペットボトルに入れた水をお互いにかけあう儀式を、人目に付く場所でも行う夫婦。ちひろの叔父は水を水道水に入れ替えるという策で彼らの目を覚まさせようとするが、激しい抵抗に遭う。両親に反抗し続けた姉は高1で家出し、行方をくらます。
学校の友だち、憧れの先生、甘いものやおいしいものに関心を寄せるちひろの中学生としての日々に、教会や教会にまつわる人々のコミュニティが重なる。将来は分からない、けれども今はそこでしか──そのような両親のもとでしか──生きられないちひろにとって、姉のように「したいことをする」ことができる日はやってくるのだろうか、と、両親と3人でひたすら流れ星を探す(「みんなで流れ星を見るまで部屋に戻らないぞ」と父が言うのだ)最後の場面を読みながら思わずにはいられない。
ちひろの家に彼が来たら何というだろう。人や生き物の涙の匂いを探して夜の町を歩く夜廻り猫こと遠藤平蔵の「寄り添い」の姿を描いた深谷かほる『夜廻り猫』(講談社一〇〇〇円)を、毎晩ちびちびと読んでいる。エッセイだったか小説だったか忘れてしまったが、遠藤周作の作品中の言葉「神は、罪深き人の隣をとぼとぼと歩く犬」を思い出した(猫だけど)。
語り手の永田は、道を歩くときでも「ただ歩く」ということができない。「僕の肉体は明治通りを南へ歩いて行くようだったけど、一向に止まる気配を見せなかった」「歩かなければいけない理由があったのかというと、そんなものもなく、かといって止まらなければいけない理由も特になかったので歩き続けることしか思いつかなかった」というように、ただそれだけのことを逐一言語化する。無意識に歩くことを自分に許さないかのようだ。無名の劇団を主催している永田は、女優を目指して青森から上京してきた女子大生・沙希と一緒に暮らしている。「靴、同じやな」と、違う靴を履いている沙希に声をかけたことから始まった関係だが、彼女をひと目見たときの思い込みがすごい。「その人が幼かった頃から今日までに、どのような生活を送り、どのように容貌を変貌させてきたのかがわかった。これは、気のせいではなかった」と内心で断言するのだ。しかし口から出てくる言葉はしどろもどろでとんちんかん。なのに沙希は永田にアイスコーヒーをごちそうする。な、なぜ……? 彼女は奇妙な人・もの・ことを面白がれる女性だった、としか解釈のしようがない。沙希のそんな稀有なすこやかさは、永田によってすこしずつ削り取られ損なわれてゆく。
沙希が男子学生からもらって来た原付を破壊したり、偶然同じ雑誌を買っていたことが分かっただけで腹を立てたり、実は永田は典型的なDV男だ。彼の沙希への態度を非難するある人物に永田が送るメールの、攻撃的で独善的な文面には身震いがする。そもそも、自分がいかに自分の大事な人を大事にせずだめにしたか、を語りたい欲望というのはかなり怖い。エクスキューズが詰まったラストシーンはほとんどホラーだ。ああもう、うっかり感動させちゃうところがDV男の巧さだよ……。
永田が、アパートの一室を舞台に、そこに住んだ人々のエピソードを時系列でなく連ねていく芝居を書こうと考える場面がある。お、これは去年、谷崎潤一郎賞を受賞した長嶋有の『三の隣は五号室』(中央公論新社一四〇〇円)のようではないか。部屋といえば今月はこんな小説も紹介したい。間取りを起点とする13の物語が収録されている、大竹昭子『間取りと妄想』(亜紀書房一四〇〇円)。冒頭に置かれている「図」にまず見入ってしまう。間取り図ほどリアルな夢を見させてくれるものって、そうそうないですよねえ。ここに住むとしたら……と想像して物語に入ると、酩酊するような心地になったり、そう使うのか、と意表をつかれたりしていちいち楽しい。中でもぞくぞくさせられたのは、数学の女教師ミツコ(あえてここは「女」をつけたい)の話だ。勤めていた高校をやめ、世界一周旅行から帰って来た彼女は、塾を開こうと家探しをする。見つけたのは、中庭を挟んで独立した2つの部屋がありダイニングに1メートルのカウンターが設えられている、理想ど真ん中の物件。ミツコはこのカウンターを使って、生徒と向き合うかたちで(つまり「お店みたいな雰囲気で」)教えようと考える。〈そうすれば妄想が浮かんでも、手足の動きが阻まれ実行に及ぶことは避けられるだろう〉と。ミツコはあることに〈手を貸してやりたくなる〉性分だったのだ──。
平凡な独身女性事務員が、ひとり暮らしの自宅の隠し部屋に入ると別人になる物語も面白かった。「この家でなければならない」家に住んでいる人は幸せだなあと思う。かろやかに住み替えることのできる人も。
こちらの物語の主人公の家族は致しかたなく家を替え続けなければならなかった。今村夏子『星の子』(朝日新聞出版一四〇〇円)。少女ちひろの両親は「特別な生命力を宿した水」を知人に薦められたことがきっかけで、怪しげな宗教にのめりこむ。途方に暮れるほどひどかったちひろの湿疹が治ったのは、その水のおかげだと信じ込んだのだ。白いタオルを頭に乗せ、ペットボトルに入れた水をお互いにかけあう儀式を、人目に付く場所でも行う夫婦。ちひろの叔父は水を水道水に入れ替えるという策で彼らの目を覚まさせようとするが、激しい抵抗に遭う。両親に反抗し続けた姉は高1で家出し、行方をくらます。
過去四回引っ越しをし、そのたびに我が家はどんどんせまくなっていった。新しい引っ越し先を見にいくたびに、そのうち我が家は消えてなくなるんじゃないだろうかと思った。
学校の友だち、憧れの先生、甘いものやおいしいものに関心を寄せるちひろの中学生としての日々に、教会や教会にまつわる人々のコミュニティが重なる。将来は分からない、けれども今はそこでしか──そのような両親のもとでしか──生きられないちひろにとって、姉のように「したいことをする」ことができる日はやってくるのだろうか、と、両親と3人でひたすら流れ星を探す(「みんなで流れ星を見るまで部屋に戻らないぞ」と父が言うのだ)最後の場面を読みながら思わずにはいられない。
ちひろの家に彼が来たら何というだろう。人や生き物の涙の匂いを探して夜の町を歩く夜廻り猫こと遠藤平蔵の「寄り添い」の姿を描いた深谷かほる『夜廻り猫』(講談社一〇〇〇円)を、毎晩ちびちびと読んでいる。エッセイだったか小説だったか忘れてしまったが、遠藤周作の作品中の言葉「神は、罪深き人の隣をとぼとぼと歩く犬」を思い出した(猫だけど)。
ALL REVIEWSをフォローする