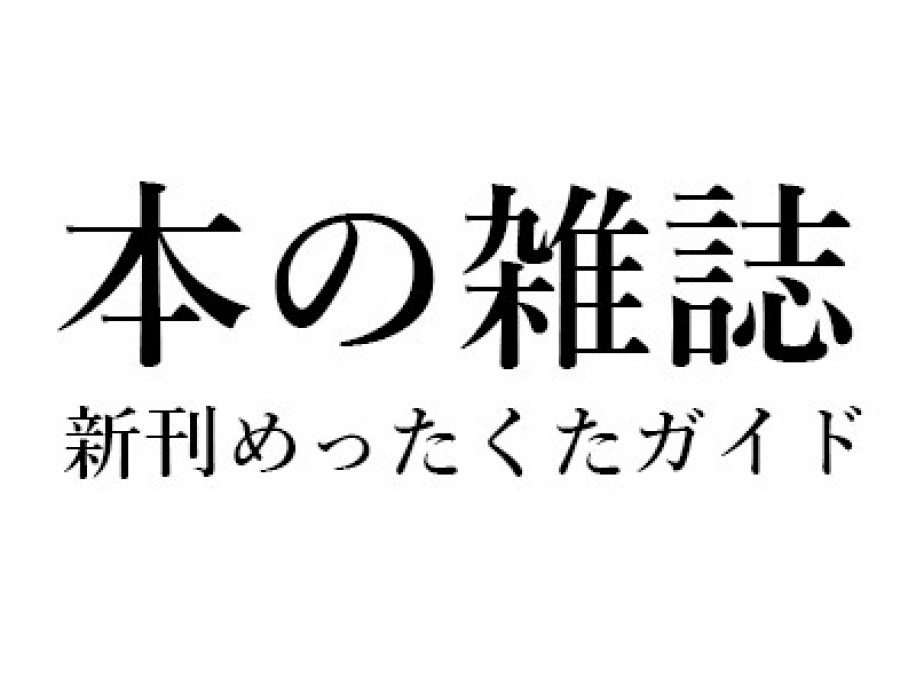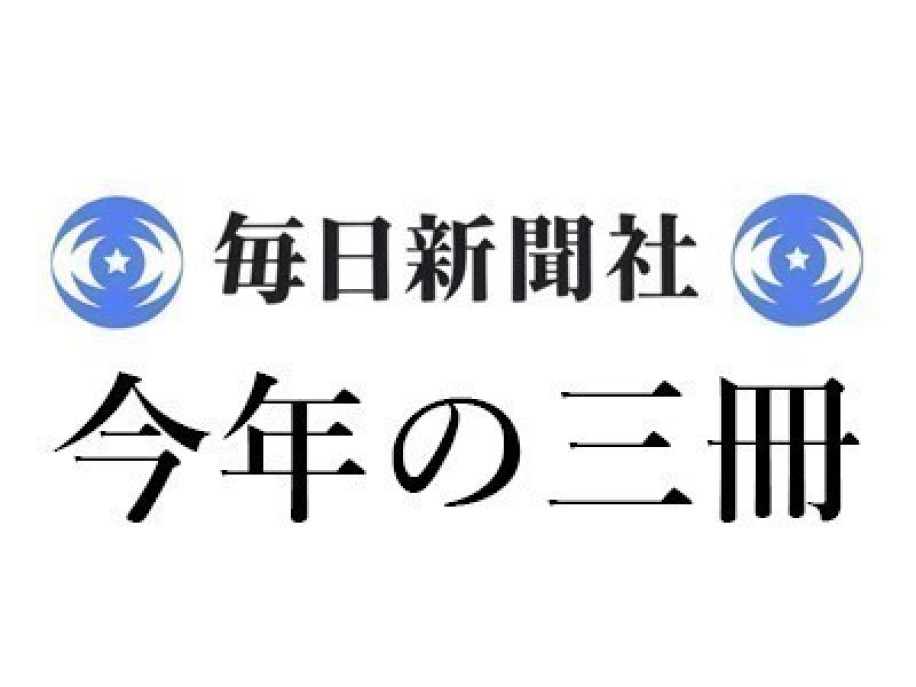文芸時評
北村浩子「新刊めったくたガイド」本の雑誌2017年2月号『あひる』『コンテクスト・オブ・ザ・デッド』『十年後のこと』『賢者の石、売ります』
シンプルにして不思議な今村夏子『あひる』
3つの作品が収められた今村夏子の『あひる』(書肆侃侃房一三〇〇円)の表題作は、易しい言葉で書かれたシンプルなお話と見えて、全然そうではなかった。老夫婦と独身の娘が山間の一戸建ての家に住んでいる。物語は娘の一人称で語られる。家族は父の知り合いからもらったあひるを飼い始める。名前はのりたま。近所の小学生たちがわいわいと見にきて、家はにぎやかになる。が、のりたまはまもなく元気をなくし、父が動物病院へ連れてゆく。戻ってきたあひるを見て娘は思う。「これはのりたまじゃない」。しかし彼女はそれを口には出さない。
同じことがもう2回繰り返される。つまりこの家には3匹のあひるが来ては去ってゆくのだ。終盤、そう遠くない場所で妻と暮らしている元不良の弟が実家に乗り込んできて、家が子どもたちの溜まり場になっていることを両親と姉に長々と説教する。弟が帰った後、母は「赤ちゃんよ、赤ちゃんよ」と歌うように言う。結婚して8年、やっと弟夫婦に赤ちゃんが誕生する、と。
へえ、「子どもができた」じゃなくて「赤ちゃんが誕生する」なんだ……。その小さなひっかかりは、そこまで語られてきた中にあったいくつかの不思議な場面を喚起させ、ゆるく束ねる。やがてある想像が浮かんでくる。3匹ののりたまは、もしかして──。
死者の物語だったのかもしれない「あひる」、死者がわらわら出てくるのが『コンテクスト・オブ・ザ・デッド』(羽田圭介/講談社一六〇〇円)。「あれ、ゾンビじゃね?」「ああ、ゾンビね」「なんだゾンビか」なんて会話が、渋谷のスクランブル交差点で交わされているのである。死者がよみがえり、生者を襲う(噛む)事件(現象)が世界で同時多発的に起きているという設定なのだが、パニックものかと思うとちょっと違う。
メインの登場人物は6人。世間からほぼ忘れ去られているデビュー10年目の作家K、彼と「同期」で、寡作ながらその美貌によって生き残っている作家の桃咲、文芸誌編集者の須賀、長崎に住む作家志望のアルバイター南雲、ゾンビ(公的には「変質暴動者」)の駆除を担当させられる地方公務員の新垣、同級生に迎合できずいじめを受けている女子高生の希(のぞみ)。6人中4人が出版絡みの人物なのには理由がある。ゾンビ小説であるのと同時に、これは文壇内幕小説でもあるのだ。かつて出版社を潤わせた老作家が編集者たちを呼びつけて開催するハラスメントまみれの恩着せクルージングは、ある意味ゾンビよりゾッとさせられる。
ゾンビの出現で思いがけず潤うことになったのはKだ。原稿を落とす作家たちが相次いだため、穴埋め仕事が回ってくるのである。どのようなものを書けば、と尋ねるKに編集者は言う。「面白ければなんでもいいんで」。前半の第一部に出てくるこの言葉が、ゾンビ発生の謎が明かされる第二部の伏線のひとつになっている。タイトルの「コンテクスト」は、直訳すれば文脈、広く言えばコミュ力という意味だが、空気を読まない、周囲が期待する行動を取らない女子高生の希が、ゾンビのいる世界での希望となるという展開がその伏線に表裏一体的に重なる。実は普遍的なテーマが内包されていることが徐々に分かってくる。
十年後、というテーマで35人の作家の短篇を収録している『十年後のこと』(河出書房新社)。SFもホラーもエッセイ的なものもあり、十年という時間の扱い方もいろいろで楽しかった。風呂場で〈茂りかけの陰毛を入念に残らず剃り〉、リビングで〈左右の手を用いて、淫裂の秘境を満開にし〉て(どちらも88ページ)、陰部の色と形状を満足気に確かめてから女性がテレビをつけると、「十年後の社会について真摯に考える」番組がやっていて……「死者の棲む森」というシリアスなタイトルが付けられたこの掌編の作者は、そう、フルクリだ。木下古栗はいつでも読者を裏切らない。また、学生時代の友人エリナから結婚の知らせをもらった29歳の女性が、エリナの「分かるはずのない」内心と、恋人と別れたばかりの自分の「分かっているはず」の心境を俯瞰する岡田利規の「エリナ」、初めての恋人とよく行った24時間年中無休のラーメン屋に、彼と別れてからも折々に足を運ぶ女性の十年を一人称で綴った彩瀬まるの「大自然」も、とてもよかった。
十年ならぬ数億年前の、不純物が入ったままの鉱物を愛するがゆえに、原石のダイヤモンドを贈って恋人にふられた30男が主人公なのは『賢者の石、売ります』(朱野帰子/文藝春秋一六〇〇円)。彼、一流家電メーカーに勤める科学オタクの羽嶋賢児は、ゲルマニウム温浴とか、疲労回復に酸素吸入がいいとか、効果が実証されていない「科学の皮をかぶった偽物」を信じてしまう人たちを、未開人と呼んで軽蔑している。妊娠中の姉の美空が「お腹を痛めて産まないと母乳も出なくなるし、母性も湧いてこないんだって」などと言うのをいちいち訂正し、嫌がられつつも正論を吐かずにはいられない。ところがそんな賢児が、異動先の商品企画部で、社の主力商品であるマイナスイオンドライヤーの企画開発を担当することになってしまう。似非科学の片棒を担いだりはすまい、と孤軍奮闘する賢児だったが──。
したいことを実現するのが仕事なのか、したくないことをするからこその仕事なのか。賢児が上司とやり合う場面、ほとんどの読者は上司の言葉にうなずきながら読むだろう。肩入れはできないけれど気持ちはわかるよ、そんな風に思わせる賢児のキャラクター造形がいい。夢と現実を二極対立にせず、商人の自分が科学者を後押しする方法はないかと考える彼の、ラスト近くの暴走もいとおしい。それにしても、コラーゲンは効かない、らしい……自分は未開人だな、とつくづく思ったことであります。
ALL REVIEWSをフォローする