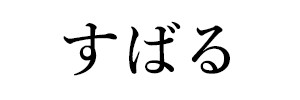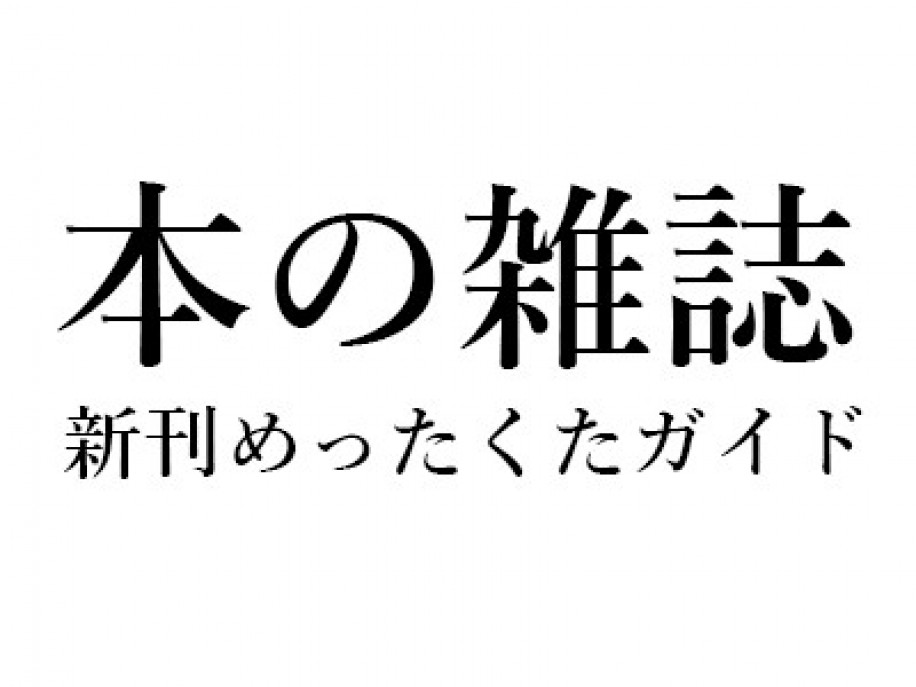書評
『コンテクスト・オブ・ザ・デッド』(講談社)
純文学というコンテクスト
登場人物がゾンビ映画を観ながら、画面の向こうにこんな突っ込みを入れる。「最新のApple製品が浸透している世界で、どうして貴様らはゾンビの弱点が頭であるということも知らないのだ?」
私はゾンビ映画に興味がなく数えるほどしか観ていないが、ゾンビの急所が頭であることはもちろん、ゾンビに噛まれると感染することも知っている。そうしたお約束はもはや文脈だからだ。
純文学も文脈の支配する世界である。主役の一人である純文学作家Kは、文壇バーの気楽さは文芸誌に似ていると思う。
「純文学文芸誌向けに原稿を書く際に生じる、説明しなくても文芸誌の読み手はちゃんと受け入れてくれるはずだという前提に立つ、あの感覚と同じだ」
同様の文脈の支配はいたるところにある。反原発デモも、ニコ動やまとめサイトのコメントも、熱狂的愛国心もどれもこれも、参与する者たちが文脈を過敏に読み過剰に適応することでさらに文脈を生み、ますます文脈に支配される構造に陥っている点で相似の現象なのだ。
羽田の芥川賞受賞第一作となったこの長篇小説は、物語の大枠にゾンビ映画の文脈を採用しながら、そのなかで日本社会を覆うそうした文脈を批判的に相対化することを目論んだ、一種のメタフィクションである。タイトルはネタバレに近い。本作のゾンビとは、文脈に魅入られた者たちの成れの果ての姿のことだ。
数々の文脈が織り込まれているとはいえ、やはり主眼は、純文学の文脈を批判し乗り越えることにある。出版業界や編集者に対する悪意と怨嗟に満ちた筆致は、羽田本人の体験が注ぎ込まれているのだろう、リアルである。登場する作家や評論家、書評家などについても「これはあの人がモデルだな」と文芸事情に明るい読者なら見当がつく程度に生々しい。
だが、そういう業界批判やモデル当てっこを喜んでしまうこともまた、文脈のゾンビ的振る舞いにほかならない。
同じことは提示される純文学の理想についても言える。「文脈の力に頼らない真に新しい小説」。登場人物の口を借りて、そんなものが可能なのかという留保がつけられるが、むろん不可能であり、そう考えてしまうこと自体が文脈に囚われていることの証でしかない。
したがってクライマックスは、どこまでも文脈のゾンビでしかありえない純文学にどう落とし前をつけるかとなる。スペクタクルな盛り上げに比して腰砕けな落着に見えるかもしれない。しかしその慎ましさには作家の心境が映っている。
ALL REVIEWSをフォローする