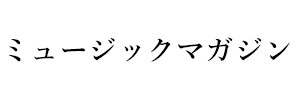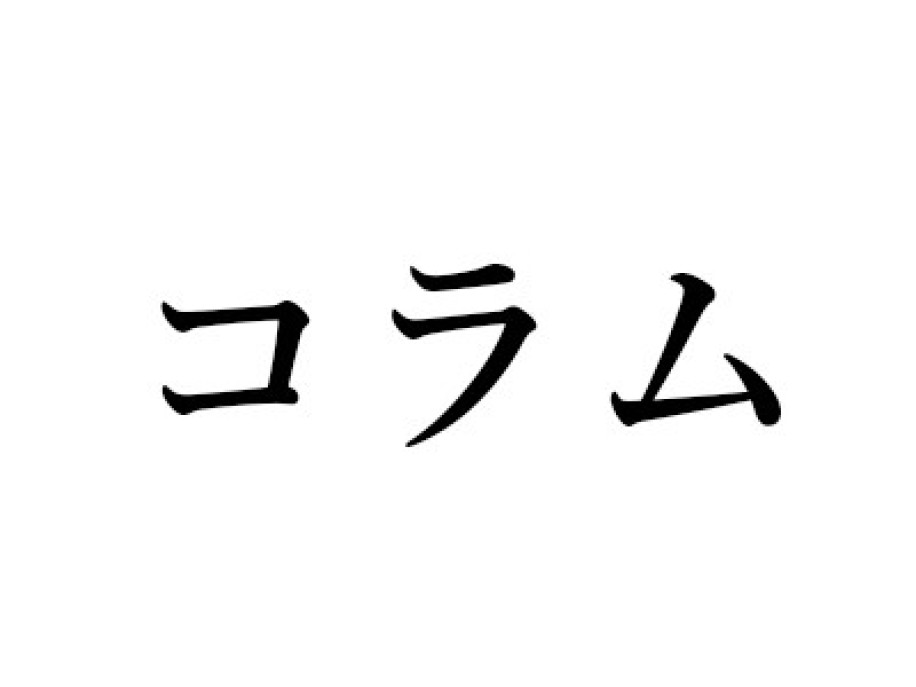書評
『物語消滅論―キャラクター化する「私」、イデオロギー化する「物語」』(角川書店)
思いがけず行き着いた「文学」擁護論
たとえば“セカチュウ”、最近だと『電車男』、こんな単純なお話ばかりがなぜバカ売れするのかと人は首を傾げる。音楽にもその傾向があるが、「萌え」「泣き」といったサプリメント的な機能に表現が特化しつつある。あるいは「ウヨサヨ」「嫌韓」、ハリウッドのシナリオみたいなイラク戦争の大義など、世界が書割じみてきたとみな口を揃える。大塚によれば、それは、ベタな「物語」が社会を動かし始めたからだ。人は「因果律」でしか世界を把握できない、だが、冷戦が崩壊し「イデオロギー」が費えた今、「因果」を律する根拠として求められるのはもはや「物語」だけなのだと。
この本は三部構成だが、第1、2章は『物語の体操』や『キャラクター小説の作り方』の反復に終始している。つまり、いま見た「物語」批判(第3章)は、彼がしつこくやってきた純文学批判の延長線上にある。「物語」が「イデオロギー」化するとは、近代文学的な「私」が拠り所を失うこととパラレルだ。「物語」の「因果律」に抗い世界に対峙するためには、「文学」が「私」を立て直し、「文芸批評」が「物語」を工学的に分析し批判する必要があるのだ、と論は結ばれる。
もちろん、ここでいわれている「文学」は「文芸誌的文学」からは一周捻れた別物である。でも、それにしても、自身「予想外」と書いているけれど、近代文学批判がまさか文学の擁護へ行き着くとは! このパースペクティヴに拮抗する言説を文芸プロパーは提出できるだろうか。
ただ、語り下ろしのせいか、トートロジーあり飛躍ありで議論が荒すぎる。より精緻に書かれたものが出るまで判断は保留かな。「大塚英志」という「物語」に足を掬われないよう眉に唾をつけつつ。
ALL REVIEWSをフォローする