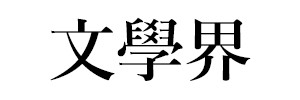書評
『おはなしして子ちゃん』(講談社)
本当に恐れるべきは
さながらショーケースのような短篇集だ。作者自身、講談社のサイトにアップされている本書刊行記念動画で、いろんな種類の小説に挑戦するつもりで書いたと語っている。『群像』にニ〇一二年から一三年にかけて発表された十篇が収められている。うち八篇は同誌八月号に「8月の8つの短篇」と題して一時に掲載されたものだ。ところで本誌九月号は藤野可織芥川賞受賞記念号で、作者の受賞記念エッセイも載っているのだが、これが八割方ゾンビの話しかしていない。芥川賞の受賞会見でも「キューバのゾンビ映画を観ながら結果発表を待ちました」と話していて、そのせいで「藤野可織=ホラー映画好き」という認識がすっかり広まったわけだが、それが「藤野作品=ホラー」にすり替わったような感触がある。「爪と目」の感想もホラー小説という前提で書かれたものが多い。ちなみに件の映画はアレハンドロ・ブルゲス監督の『ゾンビ革命 フアン・オブ・ザ・デッド』だったそうだ。二〇一一年度の作品で、キューバ初のゾンビ映画だ。
受賞が決まったとき「爪と目」はすでに読んでいて、というか仕事でもあったので熟読していたのだが、ホラーという意識は一片たりとも浮かばなかったし、藤野作品は八割くらい読んでいるけれど、これまで一度もホラー小説とか恐怖小説であると考えたことがなかったので「え? みんなそんなふうに読んでるの?」と驚いた。もっとも評者は「伽椰子を出す前に毎度予告音を鳴らしたら怖がりようがねえじゃねえか」と毒づきながら『呪怨』シリーズを一気見したようなホラー音痴であり、そうかホラーか、なるほど、と意表を突かれたということなのだが。
本短篇集もホラー要素を含んでいる。理科準備室のホルマリン漬けニホンザルがお話をねだる「学校の怪談」的な「おはなしして子ちゃん」、類まれな心霊写真の写し手が主人公の「今日の心霊」、通り魔の内面が主題の「逃げろ!」あたりはモチーフ的にもホラーに区分することがつつがなく可能であるだろうし、SNSで自己実現と承認欲求を肥大させる主婦の「ホームパーティーはこれから」などもサイコホラーと見ることができなくはない。二人の女子高生(一人は天才探偵)の周囲に陰惨な事件が引っ切りなしに起こる「ピエタとトランジ」や、美術館で血と暴力が飛び交う「ハイパーリアリズム点描画派の挑戦」もスプラッタホラーの範疇にあるといえばいえそうだし、乾燥させた猿の頭と鮭の体を縫い合わせた工芸品の人魚が主役の「アイデンティティ」や、人工知能搭載の宇宙船と人類最後の胚盤胞の交流を描いた「美人は気合い」、本が有機物である世界で本が血を流しながら死ぬ「ある遅読症患者の手記」などもSFホラーといえなくもない。一日に正確に一回だけ嘘をつかないと死ぬ少女を巡る「エイプリル・フール」は設定自体が形而上的な恐怖をはらんではいる。
なんだい結局、この短篇集はほとんど全部ホラーなんじゃないかという話になりそうだけれど、だが、私はやはり、どれ一つとしてホラーのようには読まなかったのである。
もちろん、「藤野作品はホラーである」という命題の真偽がホラーの定義によって変わる以上、どちらが正解という話ではない。成り行きとしてはホラーとは何かを考えるべき局面だが、書評のスペースでやることでもまとまる話でもないのでそれはしない。代わりにといってはなんだが、藤野のホラーに対する考えを見てみよう。芥川賞の受賞会見から。
ホラーは美しさの一つの形態であると思っていますし、怖いものは逆に笑えたりもするのでお得感があって好きです。ホラー映画でもホラー漫画でも本当に怖いのに笑えるものはたくさんあるので、大して珍しい意見ではないと思います。
また前出『文學界』の堀江敏幸との対談では、ホラー小説とレッテルを貼られがちなことについて、そういうつもりで書いたことは一切なかったのでびっくりした、と話している。
藤野の小説はマジックリアリズムとされることも多く、評者も日常に異界が介入してくる点に特徴を見ていたのだが、むしろ、常なるものと常ならざるものが常に重ね合わせになっていて、地と図が入れ替わると見え方が変わるという認識であると解したほうが近いようだ。顕著なのは「今日の心霊」である。
「今日の心霊」は、カメラのシャッターを押すと、見るものにトラウマを残さずにいないクオリティの心霊写真が漏れなく写ってしまう女子micapon17の話だ。しかし彼女自身はそこに写っているものをどうしてか見ることができず、懲りずに写真を撮るので騒動が起こる。写真愛好者の組織らしい「我々」と名乗る語り手が彼女に目をつけているのだが、それは、彼女の写真では――世間に流布する心霊写真とは反対に――生者は不鮮明なのに、心霊たちはこれ以上ないほど鮮明だからだ。
生の鮮烈さに比べ、死はあまりにも謎めいていて、我々の手には負えない。だがひとたび写真に捉えられると、死こそが明るく照らし出され、生は死が地面に落とす長い影でしかない。micapon17は、写真技術の発展に浮かれ騒ぐ我々に、写真の本質を鋭く突きつけているのである。
micapon17の写真の心霊たちはおぞましい姿をしているのだが、ポーズを決めカメラ目線まで寄越してくっきりと写る心霊たちは、映画に出てくるゾンビのようにユーモラスで「生と死のコントラストをはっきりと写し出して我々を喜ばせ」るが、同時に「生きることの意味を深く問いかけて我々を沈黙させ」もする。ここでもまた地と図は重なり合い反転している。この短篇は題材的にもホラーらしい結構を備えたものではあるけれど、ホラーと読むことに特段の優位性はあるまい。
そのような二重写しの反転の、いろいろなかたちが陳列されたのがこの短篇集だ。そんなシンプルな認識の原理が、これほどに多彩な短篇たちを生み出してしまっているという事実。本当に怖れるべきはそこだ。
ALL REVIEWSをフォローする