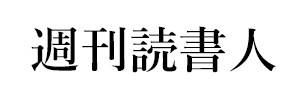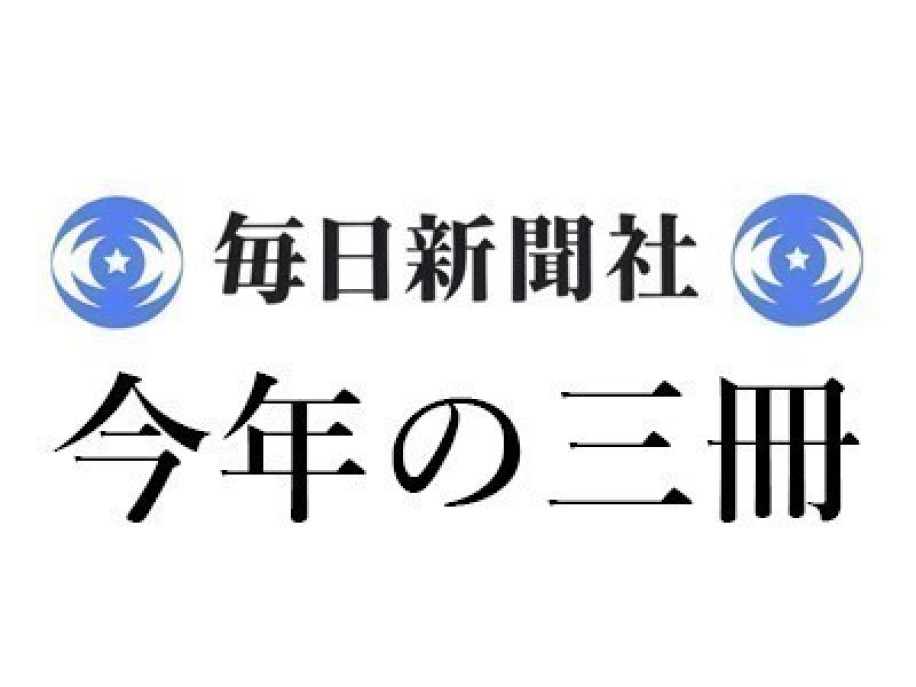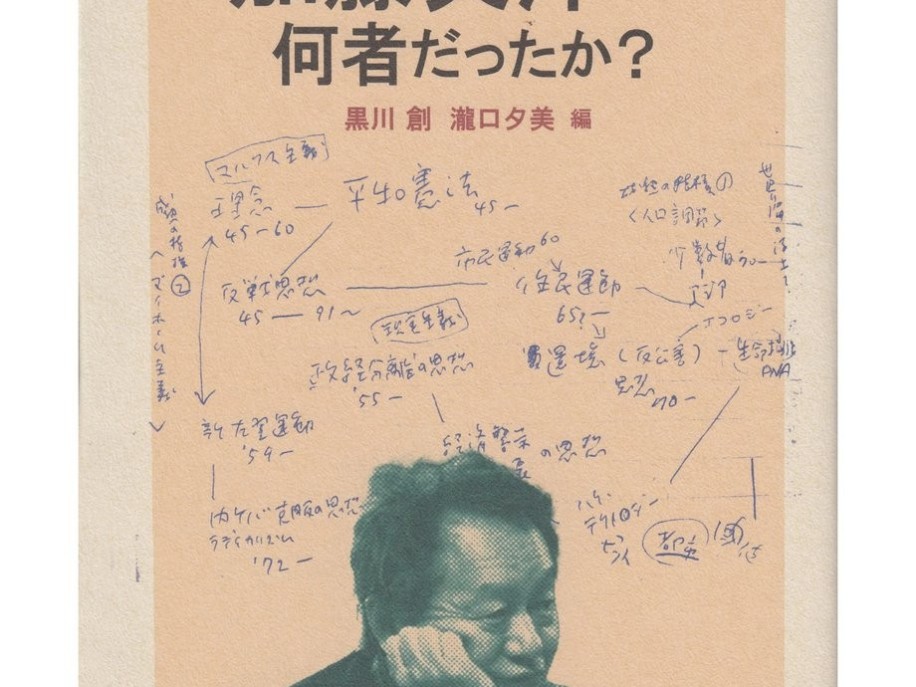書評
『足ふみ留めて---アナレクタⅠ』(河出書房新社)
誤解にまみれた作家 「反動」について考える手引きに
佐々木中はすでに誤解にまみれている。デビューは二〇〇八年の『夜戦と永遠』(以文社)だが、広く読者の目に触れはじめたのは昨年一〇月に出て何万部かのヒットとなった『切りとれ、あの祈る手を』(河出書房新社、以下『切手』)以降のことでまだ半年強に過ぎないから、登場からつねに誤解とともにあったともいえる。
例をあげよう。去る五月一七日、第二四回三島由紀夫賞・山本周五郎賞発表の様子がニコニコ生放送で生中継された。選考結果を待つあいだ、大森望、豊﨑由美、枡野浩一の三氏が両賞および候補作の解説をしていたのだが、三島賞候補の大澤信亮『神的批評』(新潮社)を説明するさいに、豊﨑が「「私批評」ですよね、佐々木中さんと似た感じの」という主旨のことを述べていた。大澤はたしかに『神的批評』のあとがきに「自分を問うこと。これが私の批評原理である」と記しており、「私批評」という解説は大澤については外れていない。
しかし佐々木中は、その意味ではまったく「私批評」的ではない。癖の強い文体や、『切手』で強調された「革命」といった言葉のせいで誤読されがちだけれど、『夜戦と永遠』巻末に一六八六個もの註が嫌みのように――実際、日本の思想・批評状況に対する嫌みなのだが――並んでいることからもわかるとおり、佐々木の説くことは、基本的にはラカン、ルジャンドル、フーコー三人の思想を、原典をあらため典拠をいちいち示しながら再検討していった末に導き出された結果に基づいており、そこに佐々木という「私」の存在や介在はきわめて薄い。
もうひとつ「誤解」を見てみよう。批評家・福嶋亮大による『切手』書評だ(紀伊國屋ウェブ「書評空間」二〇一〇年一二月一日)。福嶋はここで、「革命」という字面および「文学の勝利」という章題にまんまと躓き、佐々木をロマン主義的な「反動」に過ぎないと断じている。典型的な誤読の例である。
佐々木のいう「革命」はこういうものだ。ルジャンドルによって一二世紀の「中世解釈者革命」という「最初の革命」「情報技術革命」が示された。我々はいまだそのときにローマ法の書き換えにより産みだされた「統治」のシステム下に留まっており、現在を覆う「統治」もそのバリエーションに過ぎない。ローマ法の書き換えにより「テクスト」が「情報」に切り詰められたことで「革命」は起こったが、「テクスト」とは本来、歌や踊り、挙措や挨拶や表情など様々な広がりを含むものであった。ならば「テクスト」を読み―書き換えることで、何度でも「革命」は起こりうるはずではないか。
佐々木の問題意識がなにより「統治性」にあることは『夜戦と永遠』を一読すれば誰にでもわかる。統治性を書き換える「文学」が文芸誌に載るような「文学作品」だけを意味していないことも。福嶋は、「情報」と「文学」を矮小化して捉えるかたちで佐々木を誤読しているのだ。だいたい“現代”の思想家たちを愚直に読み―書き換え、現在へ繋げることのいったい何が「反動」だというのか。
さてようやく『足ふみ留めて』だが、インタビューや講演、書評、エッセイなどの寄せ集めで、前二著で語られたこととの重複が多すぎる。佐々木の主張を知るには『切りとれ、あの祈る手を』のほうがいい。ただし、見たように誤解を招きやすいところがあるので、これに留めず『夜戦と永遠』にあたるべきだ。本書はそのあとに眺めればよい。ヒップホップ・ユニット、ライムスターの宇多丸との対談は、「反動」について考える手引きになるはずである。
ALL REVIEWSをフォローする