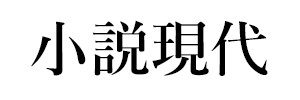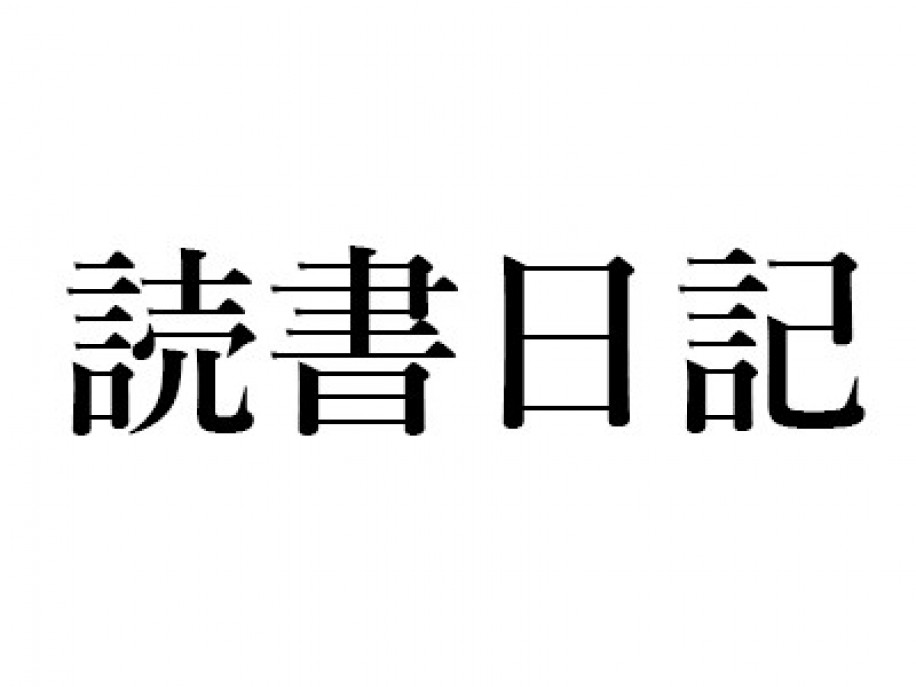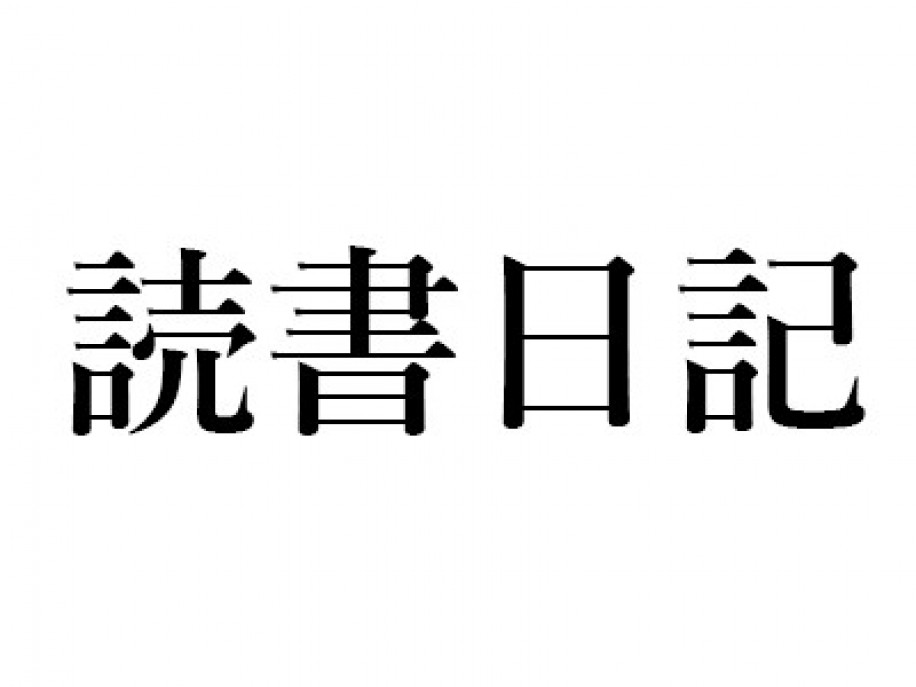読書日記
日乃詩歩子『田舎暮らしはもうたいへん』(洋泉社)、鷲田小彌太『過疎地で快適に生きる方法』(学習研究社)、高田宏『田舎者の東京暮らし』(筑摩書房)ほか
あこがれの田舎暮らし
移動をともなう仕事で、宿泊先として信州の山の中のホテルが指定されていた。時間的にそのあたりでちょうど夜になるから選ばれたようだが、行ってみれば、ホテルではなくペンションだった。四十代半ばくらいか、ダンガリーシャツにバンダナを巻いた、ペンションオーナーの定番というべきスタイルの男性が出迎える。夕飯はすませていたので、各自、直接、部屋に案内された。花柄のカーテンに、木の風合いのベッド。枕もとにはポプリ。都会人が「高原のペンション」に期待するであろうものを、「こんなの、好きでしょう」とばかりに揃えてある。
この家が、実は「注意書きの館」だったのだ。いたるところに貼り紙がしてある。
「室内禁煙。きれいな空気を汚さないで下さい」にはじまって、
「電気のスイッチは、こまめに消して下さい。限られた資源を守りましょう」
ゴミ箱の上には「なるべく捨てないで下さい。田舎ではゴミの処分もたいへんです。収集車が回ってくる都会とは違います」。
トイレに座れば目の前に、「洗浄式汲み取りであり、水洗ではありません。便をするときは、下に紙を敷いてから、ペダルを一回だけ踏んで下さい、便利な都会とはすべてにおいて違うことを忘れないで下さい」。
(いちいち、うるさい!)
ひっぺがしたくなった。言いたいことはわかるが、こう一挙手一投足にいたるまで指図されると、嫌み以外の何ものでもない。都会人=環境に関心がない=ムダつかいするものと、決めてかかる「教育的態度」も、鼻につく。人が来るのがそんなに迷惑ならば、「客、お断り」と書いておけばいい。
朝飯は、吹き抜けのダイニングで「森のきのこのキッシュ」を出される。黙々とフォークを動かしていると、オーナーがそばに来て、外を指さし、
「ほうら、リスが来てますよ。シマリスかな、エゾリスかな」
とまたも「教育的」に語りかけるが、一刻も早く立ち去りたい私には、窓の向こうにリスがいようがクマがいようが、どうでもいいのだった。
「あの主人の、自然に関する知識はめちゃくちゃ」
車で宿を発つや否や、同行のひとりが待っていたように話し出す。
「エゾリスが信州にいるわけないだろ」
私もリスには詳しくないが、言われてみれば、そんな気が。
(ありゃ、にわかエコロジストだわ)
もろもろから、そう結論した。
日乃詩歩子著『田舎暮らしはもうたいへん』(洋泉社)には、飯綱高原の通称「ビバリーヒルズ」で出会った、困った人たちがいっぱいだ。肉眼では見えない遠くの家から「近所に挨拶もない」と、引っ越し早々文句を言いにくる人。「地球にやさしい生活」にこだわり、人の家のメニューにチェックを入れる人。無農薬有機野菜をめざす夫婦は、下肥(しもごえ)の何たるかを知らず、人糞をじか撒きした畑の泥付き野菜を、段ボール箱いっぱい送りつけてきた。ハーブ作りとパッチワークに精を出す奥さまがたとの付き合いもたいへん。
著者の友人は、嘆く。こまかいことがいちいち気にならなかった、都会の人ごみと喧騒の中に帰りたい、と。
やがて、林にチェーンソーの音が響き、好評分譲中ののぼりが立つ。あこがれのカントリーライフは、どこにある?
「自然がいっぱい、環境がいい、景色がきれい、だからといって人間も自動的にきれいになるわけじゃない」。田舎暮らしの夢と現実がありのままに描かれる。
札幌から四十キロ余りの馬追山に住む鷲田小彌太著『過疎地で快適に生きる方法』(学習研究社)は「田舎」と「過疎地」とを区別する。
「田舎」は集落をなしていたりと、人間関係が濃いけれど、「過疎地」は人が少なくて、過密な都会で働く人が、居を構えるにはちょうどいい。「一生の使い方も、一日の使い方も、ヒートとクールの、緊張と弛緩のバランスをとる」。職場は都会に、生活の拠点は過疎地にと、空間的にも時間的にも、距離をとるのだ。
著者がすすめる過疎地暮らしのコツは、いわゆる田舎暮らしとは、趣を異にする。家は「ふつう」を旨とする。ログハウスや別荘ふうはもってのほか。食住に変わったスタイルを持ち込もうとしないこと。自給自足しようなどいう気は、間違っても起こすな。車には金をかけろ。過疎地だからこそ、便利さを自分で確保するための、設備投資が必要だ。
わざわざ過疎地に住まうのは、「原始的な生活方法への同化」ではない。「個人の快適さ」を誰はばかるところなく追求するという、高度消費社会的な価値観と、ハイテク社会の上に成り立つ、きわめて現代的な生き方であるとの理論が、本を貫いている。
八ケ岳と東京の家との行き来を二十年近く続ける高田宏は『田舎者の東京暮らし』(筑摩書房)の中で、フランスの現代作家ミシェル・ビュトールの「高次な形態の住所不定」
なる言葉を、たびたび引く。高田いわく、『森の生活』のソローも『方丈記』の鴨長明も、深山幽谷に身を隠したのではなく、しばしば町まで出かけていた。
「複数の土地で暮らすというのは、それぞれの土地で異質の時間を生きるということだ」。
町と田舎を交互に住み分けることの、精神にもたらす効用は、古代ローマですでに指摘されているという。住み方に関する知恵を含んだ、東西の古典を紹介する、読書案内ともなっている。
岡村健編『田舎暮らしの達人たち』(晶文社)は、著名人十二人が、移り住んだきっかけやエピソードを語る。読むほどに立ち現れてくるのが、日本の土木行政の実態だ。美しい川のそばで暮らしたいと、求め求めて鹿児島まで行った野田知佑も、ついに自然の川はみつけられなかった。ことごとくコンクリートが張られていて。過疎地の方が人目につかないだけ、好き放題、護岸工事ができるのだ。「日本国内でどんな理想的な場所を見つけても、それはいつか国や地方の行政によって壊される運命にある」。
C・W・ニコルは、黒姫山に終(つい)の住み処を構えたがため、森林破壊との闘いに、多くのエネルギーを費やすこととなった。
いいことばかりではない、十二人の体験談だが、それでも編者の人生を変えた。「年をとったら都会に住むのが一番」とマンションまで買ってあったが、南会津の山奥に移住することにしたという。
田舎暮らしには、やっぱり何か抗しきれない魅力があるようだ。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする